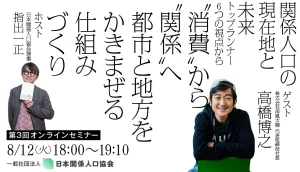プレイスメイカー・田中元子さんとの新しい挑戦
2025年3月の準備段階からおもしろい企画を行っています。それは、まったりインターネットラジオ 「サシデとモトコ」です。「1階づくりはまちづくり」をモットーに、建物やまちのあり方を問い続けている『グランドレベル』代表の田中元子さんからお声をかけていただいて、だいたい月1回のペースで、毎回1時間ほどのトークセッション、ゆるやかで自由なおしゃべりを楽しんでいます。YouTubeにアップされているので気軽に見てみてください。
元子さんは僕が尊敬してやまない、かっこよくて、素敵な方です。東京・墨田区にあるランドリーを併設したカフェ『喫茶ランドリー』や、同じく墨田区のマンションの1階にあるシェア型カフェ&ショップ『オラ・ネウボーノ』をプロデュースされていて、まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」はそういう楽しさ満点のスペースなどから配信しています。
以前に『ソトコト』にご登場いただきましたし、いくつかのプロジェクトにもご一緒させていただいています。BS朝日の特別番組で対談を収録させてもらったり、元子さんがママで僕がマスター役を務めて奈良県・吉野町でスナックイベントを開催させてもらったり、山形県南部の置賜地域のやまがたアルカディア観光局のプロジェクトである「ライク・ア・バードokitama」っていう映像の企画で僕がプロデューサーを務めさせてもらったんですけど、それにも長井市編でご出演いただいたり、何か事あるごとに元子さんに助けてもらっています。

元子さんにご登場いただくと、その場にいるみんながすごく明るく、楽しそうな顔つきになりますが、それは元子さんの天性の才能なんでしょうね。「プレイスメイカーって、誰?」と尋ねられたら、僕は「元子さんじゃないかな」って答えますね。元子さんはまったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」の中で僕に、「指出さんという人がどうやって出来上がってるのか知りたい」って興味を持って尋ねてきてくれるんですけど、僕としては、「元子さんはなぜこんなに人を幸せで、楽しい気持ちにできるのか」ということを聞いてみたいですね。元子さんはたぶん、「指出さんは買いかぶりすぎだよ」って言うかもしれませんが、買いかぶってはいません。場をつくったから人が幸せになるんじゃなくて、この場が生まれるその前の段階にはやっぱり人がいるんだろうなと思います。
『喫茶ランドリー』のオープニングイベントでは、元子さんにお招きいただいて、僕とその施設を施工した『ブルースタジオ』の建築家・大島芳彦さんの3人でトークセッションをやらせてもらったりもしています。ご一緒することが頻繁というわけじゃないんですけど、都度都度、定点でお会いすることが多いので、その間の変化みたいなものを拝見していてうれしいなと思う中で、今回こうやってまだ1回目ではありますが、楽しい企画が始まっています。
2回目の収録は、渋谷のスクランブルスクエアの15階にある『SHIBUYA QWS』というかっこいいスペースで行います。僕は今年からそこのメンバーにならせていただいているのですが、その目的のひとつは、『SHIBUYA QWS』の会員で、新しく起業したり、スタートアップに挑戦したりしている若い皆さんの壁打ち役みたいな側面を担うこと。多死社会を考える「Deathフェス」など、時代をつかんだプロジェクトがいっぱい生まれていて、動きのある場所です。まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」をゆくゆくは公開配信もしたいなと思っているのですが、今後は『オラ・ネウボーノ』と『SHIBUYA QWS』を中心にやっていく感じかなと。
14歳の僕が始発で向かった東京──釣具店という聖地
まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」の1回目で話したのは、東京に対するスタンスです。僕は中山間地域とか源流域とか、水循環を感じられる地域や、過疎と向き合う地域のお話をしてくださいといった依頼が多いんですけど、そういう地域はもちろんのこと、18歳で上京してからずっと暮らしている東京も好きなんですよ。じゃあ東京のどんなところが好きなのか、元子さんが「東京の話を聞きたい」っていうふうにおっしゃってくださったんで、東京に関する蔵出しの話を結構しました。
10代の頃、僕は東京をあまりにも神格化しすぎていました。東京に遊びに行くとなったら緊張のあまりJR高崎駅から必ず始発に乗って東京へ行くようにしていたのです。「遅れちゃまずい」と思ったのです。何に対して遅れちゃまずいのか自分でもよくわからないんですけど(笑)、それが東京に対する礼儀だろうと考えて。中学生、高校生のときは友達3人くらいで誘い合って、高崎線の始発で東京へ遊びに行っていました。
僕らの楽しみは、渋谷と新宿の釣具店に行くことでした。年に何回か、土曜とか日曜、「何時集合な」って言って、高崎駅に5時半に集合しました。超早すぎ。当時の高崎線は今みたいに熱海駅とかまでは通ってないから、上野駅で止まるわけですよ。2時間ほどはかかったから、7時半くらいに渋谷や新宿に着きますが、店はもちろん開いてないわけです。坊主頭でアイビーのジャケットを着てる集団が駅前をウロウロしているのですが、「少年たち、何しに来たんだ」みたいな感じで東京と向き合ってました。
釣具店が開店するまでの間、まちでぶらぶらしているのですが、喫茶店とかには入らないのです。1個1000円のルアーを買うために我慢しなければいけないから。だから、まだ夜の匂いが残っている早朝の新宿や渋谷、カラスがゴミを狙って路上に降りてきているような道をウロウロしていたんです。補導されてもおかしくないような3人組。その話を元子さんがすごくおもしろがってくれて。「可愛いね」って。中学生のときって、僕はそのくらいの単純な思考で生きていたんです。
東京はインプットのまちだから、1日いればいろんなものを吸収できます。絵画鑑賞もできるし、ライブも行けるし、友達の個展にも行けるし、もしかしたら古本屋さんで70年代のかっこいい本も買えるし、神田でカレーも食べられるし。朝から夕方まで滞在したら、5つか6つぐらいの楽しいことを体験できるんですけど、そういう情報がほとんど手元になかった1980年代の中学生は、もう1点張りです。新宿のサンスイっていう釣具店か、渋谷のサンスイっていう釣具店か、代々木のカディスっていう釣具店に行くことしか考えてません。だから、それが終わるともう後は帰るだけなんです。
物質文化の80年代が教えてくれた幸福のかたち
その3店舗を回ることもありますけど、お金は修学旅行と同じで、「おやつはいくらまで」みたいな感じだから、使えても5000円くらい。最初にサンスイに行ったら、欲しいものしかない店なので、あっという間に5000円が飛ぶんですよね。だから、もう帰るしかない。昼飯も食べないで帰る。でも、心はお花畑ですよ。カタログでしか見たことがないアメリカやフィンランド製のルアーがついに手に入った、みたいな。もう感極まってます。下りの高崎線のボックスシートで、フィンランド語の説明書とか読めないのに「すげえ!」みたいにして広げて。
あんなに何か物の価値が高まったのは80年代だから。物の消費文化の80年代を悪く言わないでほしいってのは僕の考えでもあります。みんな、欲しい物を手に入れたくて毎日すごくエネルギッシュに生きてたから、それはそれでいいんじゃないのかな。夢が生きてた時代っていうんでしょうか。これを買うと何か自分の中に大変幸せなことが起きる、スーパーウェルビーイングな感じになれる、そんな幸福感が1000円の舶来の釣り具にあふれていたから。
僕にとっては、その幸福感が勉強の起爆剤にもなりました。学校の勉強とか受験勉強を頑張れるじゃないですか。だから物文化、物質文化がNGってわけでも僕はないんですよ。物が人を幸せにしてくれてるのもあるし。僕は高校受験、大学受験は自分の机でも勉強したし、こたつに入っても勉強していました。うちは掘りごたつで、しかも練炭なんです、今も。大丈夫かな、母親危なくないかなと思うんですけど、母親は煉炭のじんわりとくる温かさが好きみたいで、毎朝、練炭に火をつけてこたつに入れてるんです。僕も練炭の掘りごたつが好きで、こたつに足を入れて勉強していたのですが、横には新宿や渋谷で買ってきたルアーの入ったタックルボックスが置いてあるんです。それで、問題を1問解くとルアーを1回触っていいっていうマイルールをつくって、勉強のモチベーションを上げていたのです。僕はルアーでしたけど、人によってはレコード盤かもしれないし。そういう物を手に入れるために、東京に行っていたんです。
「ローカルVS東京」ではない──みんなでつくったコモンズ
東京はやっぱりおもしろくって、僕は東京はローカルの人たちがつくった「夢の国」だっていうふうに常々言っていて、「こうなったらいいな」っていうものをみんなが集めた集合知の具体がたぶん東京じゃないのかな。「ローカルVS東京」ってよく言いがちですが、「ローカルVS東京」ではないのではって。東京って、たぶんコモンズなんですよ。地域のみんながつくったものだから、地域のみんなが、「ここは俺たちがつくったもの」と思って共有して楽しめばいいっていうのが僕の考えです。それは不便を味わわないと生まれなかったまちだから。不便とか、貧困とか、社会保障とか、何かそういうものを考えていった結果、東京が生まれて成長してるんだっていうふうに思います。
「不寛容社会」っていうテーマについて、『LIFULL HOME’S総研』所長の島原万丈さんが、「寛容でないところから人は出ていく」といったことをレポートにまとめられておられるし、東京とかは「ブラックホール型自治体」というふうに書かれることも多いですが、特に女性に関して、東京にどんどん若い人たちが自発的に来るっていうのはさもありなんなわけですよ。なぜなら、寛容な社会をつくりたいとみんなが思っている中で東京が生まれてるからなんですよ。みんなの夢が自分たちのまちの中では結実しにくくって、東京だとそれができたから、東京がローカルの写し鏡みたいになっていると思います。なので、「ローカルVS東京」ではないんです。VSなのは、おそらく東京のライバルとなる世界の巨大なまちではないでしょうか。「東京VSパリ」でもいいし、「東京VSニューヨーク」でもいい。そういうもの。東京をライバル視はしないで、東京はあくまで外付けのハードディスクだって思えばいい。そのメンタリティだけで、たぶん都市の政策とか地域の政策って変わっていきます。「東京に負けないように」っていう視軸と視座が既にすごく閉じられてますよね。
「ライバルが台北です」とかの方がもっとワイドでおもしろい。台北の中山を夜歩いていると、おしゃれな女の子たちが3人とかで、明るい声で大笑いしながらこちらに向かってくるんです。「何でみんな、こんなに快活なんだ?」って不思議になるくらい、楽しそうなんです。普通のみんなですよ。休みの日だから遊びに来てるみたいな。台湾だけじゃなくて日本の人や他の国の人も来ているんだろうなって考えると、これは東京がつくれなかったまちだなって思っちゃうんですよ。かと言って、東京がビハインドかっていうとそんなことはなくて、東京は東京のカルチャーがあってそれでいいんですけど、最近、台湾に続けて2回行っていたので、「台湾ってすごい。20年間でここまで変わっていったんだな」という驚きと、東京にない、前に力いっぱい進んでいくエネルギッシュさを感じたこともあって、ちょっと引き合いに出してみました。
ザ・モンキーズから「THE MANZAI」へ──僕の音楽遍歴が止まった瞬間
まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」では音楽のこととか、僕があんまりしてこなかった話についても言及していただいています。元子さんから、「指出さんはどんな音楽を聴いてきたの?」って尋ねられて。元子さんって、質問がうまいんですよ。みんなが喋りたくなるような質問の仕方をされます。それで振り返ってみたら、僕が最初に買ったレコードは、ザ・モンキーズの「デイドリーム・ビリーバー」だったことを思い出しました。コダックのフィルムのテレビCMで流れていて、英語の歌なんですが、僕はなぜか郷ひろみが歌っていると勘違いしたのです。「郷ひろみ、すごいいい歌を歌ってるな」と思いながら新星堂っていう高崎にあるレコード屋さんに行って、郷ひろみのコーナーを探したんですけどもちろんなくて。店員さんに「コダックのCMで郷ひろみが歌ってる歌のレコードがほしいんですけど」って言ったら、「え?」という顔をされたので、もしかしたら郷ひろみじゃないかもと思っていたら、「ザ・モンキーズっていう、昔のバンドだよ」って教えてくれたので、「そうなんですか」と、洋楽のコーナーにあった「デイドリーム・ビリーバー」のドーナツ盤を買ったんです。
ちょうどそのときザ・モンキーズがテレビ番組でリバイバルしたんですよ。ザ・モンキーズの、ちょっとモンティ・パイソンっぽいコミカルなやつ。「ザ・モンキーズ・ショー」です。ビートルズもそうですけど、自分たちが出るコミカルな番組、たぶん人気のバンドって持ってたんでしょうね。モンキーズもそれをやってて、吹き替えで、TBSだったかな、やってるのを見てすごくおもしろくって、「ザ・モンキーズ、いいな」と思って、その後ベスト版も買いました、2枚組の。
でも、その2枚組を買う前に、スーッと僕のところに入ってきたレコードがあるんです。それは、「THE MANZAI」なんです。2番目に買ったレコード。春やすこ・けいことか、西川のりお・上方よしお、島田紳助・松本竜介、B&B、ザ・ぼんちも入ってたかな。たくさんの漫才がレコードになってて、それを買ってきて部屋でヘッドホンをつけて聞きながらゲラゲラ笑ってたんです。のりおの「ホーホケキョ」みたいなギャグで大笑いしていました。元子さんからの質問は、僕の「思春期を彩った音楽はどんな音楽なの?」っていう話だったんですが、ザ・モンキーズから始まったのは悪くなかったんですけど、急に「THE MANZAI」が入ってきたせいか、そこで会話が終わりました。
「THE MANZAI」を何で買ったのかは覚えていないのですが、すごいおもしろかったです。たぶん、ナイーブな心を持つ、イケてる当時の中学生とか高校生はスネークマン・ショーとかYMOに行くはずが、僕は「THE MANZAI」に行っちゃった。空前の漫才ブーム。その頃から、ちょっと関西に憧れを抱いた可能性がありますね。
元子さんのジャジーな青春と僕の釣具店──すれ違う東京体験
まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」の中では、その音楽の話が「THE MANZAI」によって途中で終わっているので、またもう1回音楽の話に戻して、僕のやりきれない、うつむきながら音楽を聴いていた遍歴を話そうかなと思っています。「高崎は日本のマンチェスターだ」っていうのが僕の持論です。やりきれない不満をぶつけている鬱屈とした若者たちが集まっているまちみたいな。
元子さんの出身は茨城県です。たしか、筑波山が美しく見えるところ。元子さんは僕の音楽の話に合わせてくださって、「私はね」と話してくれました。学校の近く、駅の中かな、コインロッカーに制服を入れて、私服に着替えてピットインにジャズを聴きに行っていたそうです。六本木だったか、新宿だったか。
ちなみに、僕の行っていた新宿のサンスイっていう釣具店はピットインの下か上にあったんですよ。僕の中にはピットインなんていうジャジーな言葉は一切なかった。サンスイしかなかった。なので、東京っていうとやっぱり怖いんだけど行ってみたい、一歩踏み出さないと入れないんだけど、入ると何倍も幸せをもたらしてくれるみたいな、そういうまちという印象で付き合い始めました。14歳とかかな。今でもその気持ちはありますね。
『POPEYE』のライカが見せた憧れ──雑誌編集者になりたかった理由
僕のメンタリティは、常に東京に褒めてほしかった。「東京に褒められる」という言い方はすごく抽象的ですよね。雑誌の編集者になりたいっていう根底には、「東京に褒められた感がある職業だから」という思いがありました。特に80年代後半くらいとかだと花形の仕事みたいに感じましたね。今思えば、それは出版業界が勝手に煽ってただけなのかもしれません。世の中にはもっと花形と呼ぶにふさわしいいろんな仕事がありましたから。ただ、当時の若者にとっての雑誌っていうのは、今で言うTikTokみたいなもので、雑誌に出ている人たちがやってることは憧れの対象になりやすかったのです。
僕は今でも覚えている一文があって、これは『POPEYE』の編集後記だったかな、一番最後に載っていた文章なんですけど、「編集部員のみんなは胸元にライカを下げてお互いにパチパチ撮り合ってる」って書いてあって。「ライカ、持ってんのか」って思ったんです。おしゃれっていうか、どうやってそういうスタイルにたどり着いたらいいのか、群馬の中学生にはわからないんですよ。何がおしゃれかもわからないし、坊主頭でVANのジャケットとか着てるのは全然おしゃれじゃないんですけど、『POPEYE』の皆さん、もしくは『POPEYE』をつくっているマガジンハウスの皆さんは、おしゃれの答えを持ってるんだなっていうことがそのときに僕は何か埋め込まれたんでしょうね。きっと、僕だけじゃないはずです。いろんな人がそういうふうに感じていた。「雑誌をつくっている人たちはカルチャーの先端を行っている」みたいな、そういうイメージがあったので、自分も雑誌の編集者になりたいと思ったのが、今の仕事に就く大きな理由のひとつかもしれません。
もちろん、小さな頃から本に親しんでいたっていうのもあります。文章を読むことが好きだったのに加えて、雑誌っていうメディアの何かフリーな感じに惹かれていました。当時は本当にフリーだったと思うんですよ。そして、フリースタイルの雑誌とクラシックな近代文学の本が入り乱れて部屋に置いてあるような中学・高校時代の中で、アメリカの西海岸のライフスタイルのことをいっぱい載せてくれているようなメディアに惹かれていったんです。今で言うと、それってどんなカルチャーなんでしょうね。ヒップホップになるのかな。
東京の話はそんなところかな。まったりインターネットラジオ「サシデとモトコ」に関しては、連載が続いていく中で、いろんな気づきが生まれるだろうから、この「オン・ザ・ロード」でも発表していきたいと思います。
秩父と高崎の似ているところ
年度が変わるタイミングで、僕は関東のあるまちにお招きいただいて、珍しく1泊2日で伺ってきました。そのまちは秩父です。秩父って、高崎と商圏が一緒なんですよ。秩父の皆さんは東京に行くよりも高崎の方が近いので、高崎に買い物に来られたりしていて、僕の話すイントネーションとか、僕の高崎の方言もあるんですけど、それと秩父はすごく似てるんです。だから、お話をするときも、笑いどころとか、呼応するタイミングみたいなのが通じている気がして、お互い何か尊敬し合ってるっていうか、関東の一大小麦文化圏なんで、特に何か秩父と、高崎などの群馬の西部は同じ文化のエリアというのもあって、楽しみに行ってきました。
秩父には「FIND CHICHIBU」っていうプロジェクトがあり、商工会のメンバーとか首長さんとかが集まるような勉強会なんですけど、そこで二拠点生活の話をしてほしいと言われたので二拠点思考の話をしました。秩父は亡くなった父親が日曜になると、仕事であったり、趣味の目的があったりして通っていたので、その車に僕も乗せてもらって遊びに行っていた場所でした。そんな話をしながら和やかに二拠点生活の話をした後、宿に泊まりました。静岡県の下田でも1泊しましたが、それは夜のイベント出演だったからという理由もありました。この秩父のイベントは午後に終わったので、そのまま帰ることもできたんですけど、「よかったら『まちやど』を勧めているので、お泊まりになってみてはいかがでしょうか?」ってお誘いいただいたのです。イタリアのアルベルゴ・ディフーゾという考え方が日本では「まちやど」として広まりつつあるのですが、秩父もそれを広めようとしていたので興味が湧き、泊まることにしました。
イチローズモルトとミズナラの記憶──アルベルゴ・ディフーゾの夜
秩父はとてもウォーカブル・シティだなっていうふうに感じました。西武秩父駅と秩父鉄道の秩父駅の間のエリアには、昔ながらのお店や新しいお店が混在しているんです。また、秩父には「ベンチャーウイスキー」という会社があり、イチローズモルトというブランドのウイスキーをつくっています。そのイチローズモルトが飲める、イギリスのスコットランドに本店を置く「ハイランダーイン秩父」というバーがオープンしていて、そこに夕方4時ぐらいから行って、イチローズモルトのソーダ割りを一杯、いただきました。とてもおいしかった。僕が泊まらせていただいた『町住客室 秩父宿』という宿はアルベルゴ・ディフーゾを推奨していて、その宿に泊まるといくつかの特典があって、まちの中で提携しているお店で使える木のコインをもらえるんです。そのコインを使える場所の一つが「ハイランダーイン秩父」でした。この夜は、「FIND CHDICHIBU」のメンバーを中心としたみなさんとおいしい中華屋さんでご飯会をするという予定があったのですが、その前の1、2時間ほど、僕は「ハイランダーイン秩父」で過ごしました。1杯目のスタンダードを飲んだ後に、「イチローズモルトはなかなか飲むチャンスがないから、珍しいのも飲みたいな」と思ったら、ミズナラの樽で貯蔵したMWR(ミズナラウッドリザーヴ)というブレンドのウイスキーがあったので注文しました。もう、それにやられてしまって。
なんで僕はミズナラに興味があるかっていうと、僕が釣りをしているイワナがいる川ってミズナラが植生としていっぱいある場所なんです。その香り高いブレンドウイスキーをゆっくり飲んでいたら、まるでミズナラのある渓流の風景に身を置いたような感覚に包まれました。しかも午後の仕事が終わった直後ですから、日も沈んでいなくて、桜がまだ満開のような状態だったことも相まって、「なんか本当に桃源郷のようなところだな、秩父は」みたいに思い、すごく楽しく過ごさせていただきました。
翌日の朝は、例の木のコインで駅前のコワーキングスペースが無料で使えました。オンライン会議にも便利でした。滞在してゆっくりとまちを楽しみながら、仕事もできて、しかも西武新宿線で1時間半で来れるし、いいなと思ったんですが、これが実はとんでもない路線だったんです。
大学生たちが「着陸」した場所
何がすごいかというと、3月末の春休みのシーズンですから、平日でしたがいろんな方が乗っているんだろうなとは思っていたんです。僕は講演に間に合うよう、会場に開場20分ぐらい前に到着できるような時間の電車に乗りました。建築家の妹島和世さんがデザイン監修をしたラビューっていう超かっこいい宇宙船みたいなデザインの特急なんですけど、初めて乗って心が躍りました。その乗車料金も、いつも高崎の実家に帰る上越新幹線の値段とかに比較するとそこまでかからない。「秩父までこの金額で行けるんだ」と感心しながら、線路沿いを名栗川とかすごく綺麗な川が流れているのでそれを眺めながら乗っていたんですが、後ろの席も、前の席も、車内が賑やかなんですよね。
賑やかな理由は、学生の皆さんの乗車率の高さにありました。大学生たちがいっぱい乗っていて、僕は横瀬町の富田町長さんとも市町村サミットでご一緒していたので、きっと産官学連携の取り組みが秩父の自治体で先進的に取り組まれているから、地方創生とか探究型学習みたいな形で学生のみんなもゼミとかで来られてるんだろうなと思ったんです。そうしたら、そういう方々もおそらくいたとは思うんですけど、大多数は遊びに来ていたんですよ。
溢れんばかりの大学生の男の子、女の子たちが、カップルというかグループで来ている人たちも多くて、みんな西武秩父駅に着くなり、駅に直結したクラフトビールのタップエリアに向かい、そこでとくに女の子たちがビールを買って飲みながらまちを歩いてるんです。「大盛況だな」って驚かされました。こんなに若者が来ているローカルは、もちろん長野とか人気のローカルっていう意味では、僕の頭の中には若い人たちがよく歩いている場所の知識はあるんですけど、秩父のこれだけの活況ぶりはプロットできていなかったので、とてもいい意味でアップデートさました。あらためて、すごかった。秩父は選ばれたローカルのひとつかもしれませんね。
そのことを夜のおいしい中華料理屋さんで台湾ビールを飲みつつ、商工会やまちづくりのリーダーの皆さんと話題にしたら、「そうなんですよ。大学生が大勢来てくれるんです。ただ、だいたい日帰りなんですよね」って話になりました。確かに日帰りで、夜になると泊まりがけの上の世代の大人たちが残っているみたいな感じなので、秩父はこれからその若い皆さんがどう定期的な形で滞在するかみたいなことを考えていくフェーズにあるんだろうなって思いました。
そこで、「なぜ、ここまで若いみんなが来るのか」っていうことを何人かに聞いたところ、秩父の人は「かつてのアニメでのツーリズムの影響もあるかもしれませんね」みたいなことは言っていたりするんですが、ちょっとそのあたりの事情を知っている人も、「秩父がアニメの舞台となったからは大きい」と東京で僕に教えてくれました。もうひとつの理由として、移動のコストとなる特急料金が安いことも考えられます。また、池袋というキャンパスタウンと直結しているからというのもありそうです。なので、今度行ったときに学生の皆さんと同じ店に居合わせたりしたら、どういう理由で秩父に来られたのか聞いてみたいですね。
おそらく、川越や秩父というエキゾチック感みたいなところに惹かれて来られてるんじゃないかな、川越と秩父ってのはたぶんお互いにすごくアウトスタンディングな立ち位置でまちの盛り上がりをつくっているところですけど、秩父はオオカミ信仰のまちでもあるんですよね。なので、少し独立国家っぽいところがあって、突然、武甲山と秩父の盆地みたいなのが現れるのを見ると、あの風景もすごく好まれているような気がします。
というのも、車内で僕の後ろにいた男子3人と女子3人のグループが特急からホームに降りたときに、「着陸しました」って言ったんですよ。彼らにとっては宇宙にやってきたみたいな感覚があるんでしょうね。「着陸」っていい言葉だなと思いました。ラビューという宇宙船のようなデザインの特急列車に乗ってきたというのもあるだろうけど、90分くらいの移動で「着陸」という異空間である秩父に来ている楽しさを味わっている彼らが、秩父のさらなる持続可能な盛り上がりをつくってくれると、秩父の皆さんも喜ばれるんだろうなと思いつつ、浮き足立って、楽しさに満ち溢れた若いみんなが秩父というまちをおもしろがっているのは、高崎出身の僕にとっては同じ文化圏のまちを褒めてもらえたような感じがして嬉しかったです。
「じゅうたんスナック魔法つかい」──北関東の間の取り方
最近、SNSでよく各地で食べたラーメンのことを発信してるっていうのもあるんですけど、地域へ行くと、「おいしいラーメン屋さんがあるんですよ」と連れて行っていただける機会が増えたんです。「ラーメン、好きですよね?」という感じで。幸せですよね。
あともう1つ、地元のスナックにご案内いただくことも多々あリます。秩父では地域の重鎮の方が、「指出さんにぜひ一緒に行ってもらいたいスナックがあるんですよ」と誘ってくださったので、「どこでも行きますよ」って中華を食べた後に連れていってもらったところが、「ジュータン・スナック 魔法つかい」っていう名前のスナック。奥に絨毯が敷かれていて、靴を脱いでみんなでベタッと座ってくつろげるようになっているんです。僕はスナックにそこまでたくさん行ったことがあるわけじゃないんですけど、居心地のいい異世界でした。
絨毯には7人くらいが座れました。空間の佇まいがとてもよかったです。北関東出身だから、北関東の人の間の取り方みたいなものがリズムが合うのかな。そういうの、あるのかもしれませんね。何ていうか、どの地域でももちろん間は合いますが、それ以上に自分自身と話してるみたいな感じ。カウンターでは地元の若い男性がback numberの「高嶺の花子さん」をカラオケで熱唱していて、ローカルの味わいを堪能した秩父の夜でした。これも、プレイスメイキングと言えそうです。