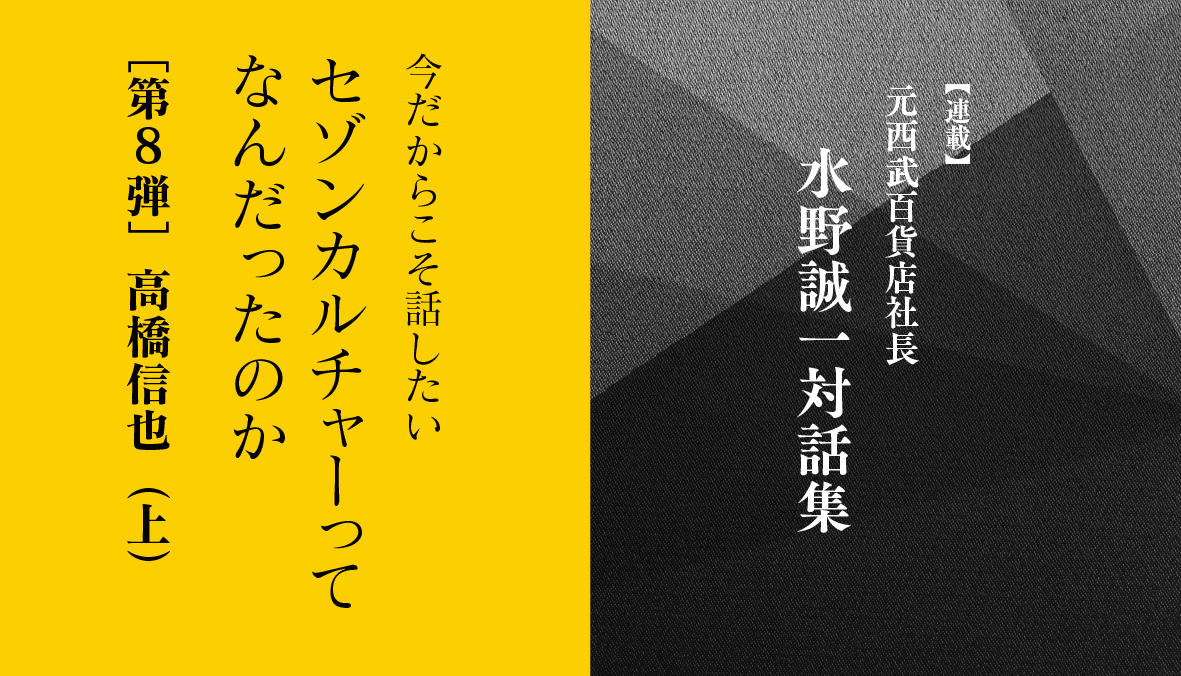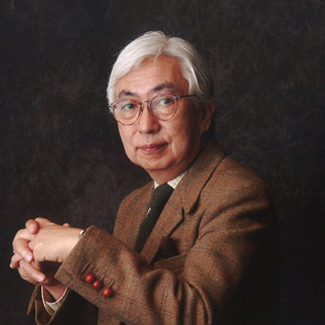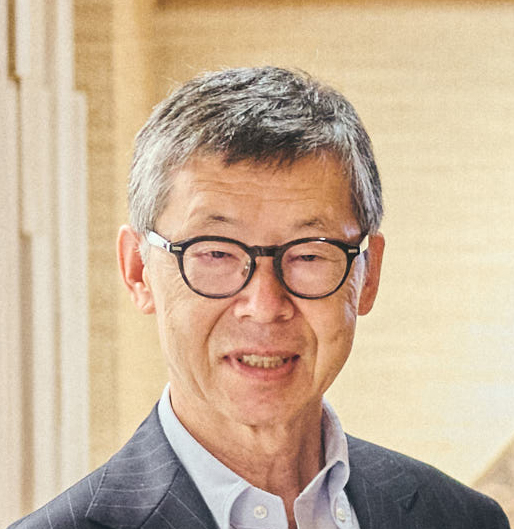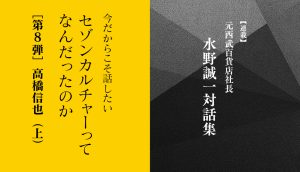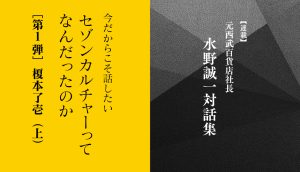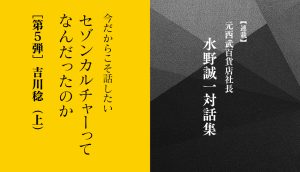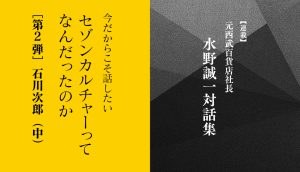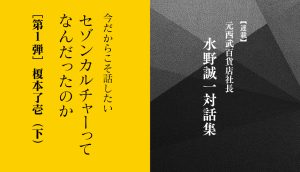日本では有数の美術洋書を集めた専門店・アールヴィヴァンが西武美術館のロビーに誕生したのは、1975年のこと。当時、西武百貨店の若手社員だった水野誠一が手がけた社内ベンチャーには、どんな事情があったのか。その経営に関わり、やがて美術界を牽引する一人となる高橋信也との対談は、与えられるミッションを真面目に引き受けて次の仕事になっていく高橋の青年期から始まる。

アールヴィヴァンは1975年の社内ベンチャーだった
水野 まずはアールヴィヴァン(ART VIVANT)から話を進めた方がいいかな。そしてそれ以降の展開へと思っています。
そもそも、僕と開成高校で同級だった芦野公昭がフランスからシャンソン歌手の薩めぐみと一緒に戻ってくるときに、美術書をたくさん仕込んできたと。それを売る場所をどこかに探したいんだけど、どうしたらいいかという相談が来たんですよ。
それで、もうすぐできる西武美術館のロビーに、美術洋書の専門店をつくったら面白いんじゃないかというアイデアを僕が出したんです。
最初は竹内さんという常務に話したら「そんなものね、君、 1年も持たないよ。すぐ潰れるからやめた方がいい」と、けんもほろろでね。3人いる常務のうちで、竹内さんが一番わかってくれると思ったんだけれど。
じゃあ、堤さんに話すしかない。それで堤さんのところに行って「芦野という友人がパリから持ち帰ってきた美術洋書のコレクションがなかなかすごいので、僕は彼と 2人で会社を作ろう思います」と言ったわけ。
高橋 なるほど。
水野 そうしたら「面白いから西武からも出資するよ」という話になった。
最初の資本金は1,000,000円ずつ出して2,000,000円くらいだった。
だけど、僕はまだ新入社員に近い状態ですから、それをいきなり会社に無断で会社を作るという話自体がとんでもない話なんだけど(笑)。
いろんな人が尾ひれをつけて、自分の手柄のように話していますが、実際は、そんなシンプルなことだった。
高橋 それで西武美術館のロビーに洋書が置かれるようになったんですね。
水野 その設計を堤さんの提案で杉本貴史がしたんです。そうしたら、なんと全部きれいなステンレスの正方形デザインで。
高橋 グリッドにしたんですね。
水野 「これでどう」というわけですよ。ところが、そのサイズだと美術洋書の半分ぐらいは入らないわけ。
正方形じゃないとプロポーションがおかしくなるとか、大きくなりすぎるとか、いろいろと議論があって、やっとできたのが、あの売り場だったんですね。
その後、僕の本業は西武の社員だったので、アールヴィヴァンのことには、ほとんどタッチはしてなかったんで、高橋さんの登場の経緯はよくわかっていなかった。
たしかその前は、安部公房スタジオにいたんだよね。それはどういう経緯だったの?。
そのあたりから聞かせていただこうかな。
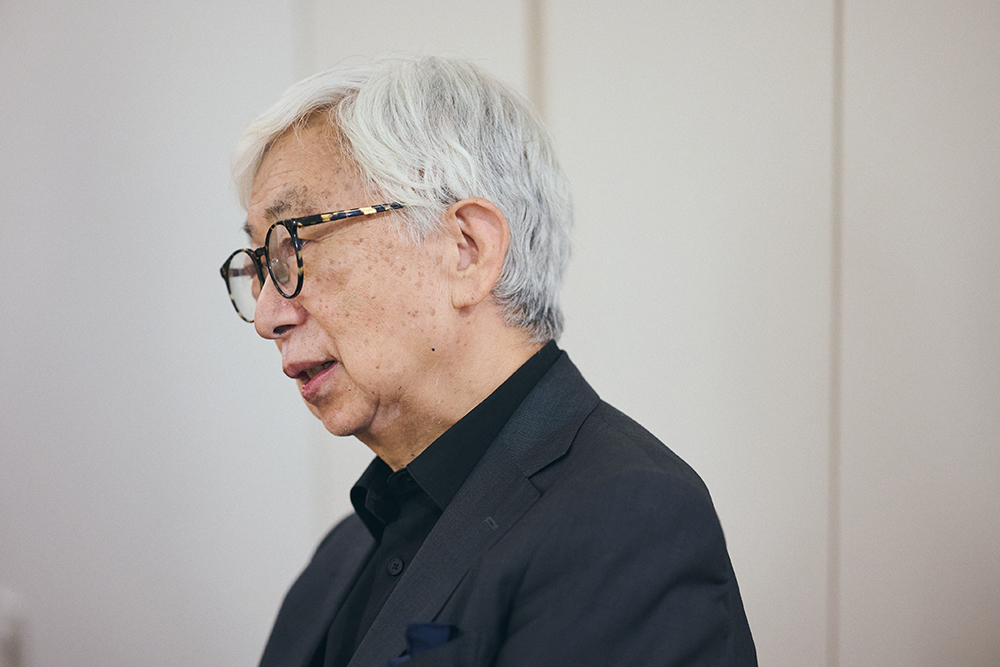
ひとつずつの信頼関係が次の仕事へと
高橋 安部公房スタジオには、僕は大学 4年ぐらいからコミットさせていただいておりました。それで、 1年半ぐらいで辞める話になりました。
水野 そのスタジオではどういう仕事をされていたの?。
高橋 実は僕は演出家になりたかったんです。でも演出ができるのは安部さんだけで、あとはもう全員、役者かスタッフですね。それで 4回ほど公演をお付き合いしました。
ただ ちょっと申し上げにくいこともありますが、結構、内輪でガタガタした事もあって。いろいろ考えるところもあって、これ以上続けられないかなと、思ったんです。
その頃に、当時の西武劇場で、薩めぐみさんの公演があったんです。フランス語で歌える数少ない歌手だし、君は中身が分かるだろうと、京都の母の友人が声をかけてくれて一緒に行ったんです。楽屋にも連れて行ってもらったら、プロモーターの芳賀詔八郎さんと薩さんが話しておられて「私、京都でやりたいから劇場探してよ。探してくれたら芳賀さんに連絡ください」という気楽な話になりまして。
じゃあ探します、と。僕は京都に何人も舞台関係の友人がいますから、 わりと早くに見つかったんです。それで薩さんと芳賀さんに連絡をして、打ち合わせしようということになりました。その打ち合わせで、芦野公昭さんにお目にかかったのが初めてでしたね。すごく印象的だったのは、芦野さんがなんか適当な電話をしてたんです。「今日はちょっと体調が悪くて。西武には行けないんだけど、また明日行きますから」みたいな(笑)。
水野 でも元気だったんでしょう(笑)。
高橋 はい。それで我々のミーティングに一緒に芦野さんが入り、ほとんど見ず知らずの僕が決めたブッキングで 京都公演が決まり、東京から2つ目のコンサートとして札幌で締めくくりたい。だから京都のプロデュースを僕に任せるよ、と、いきなり言っていただいたんです。
私はもう社会に出る前に安部公房スタジオを辞めたりなんかしていた、若気のいたりの人間ですから。そこまで信用してもらったことは、やっぱりとても嬉しかったんです。
それで、京都に先に入って、大阪の新聞社を回ったり、京都のプロモーターに挨拶したり。途中で芳賀さんも合流されて、みんなでコンサートをつくっている格好になっちゃったんですね。
ところが、そのコンサートの 2〜 3日後に「エリック・サティ没後 50年」ということで、東京の「キングスベンチ」という、パルコの裏側のクラブのような小劇場があって、そのための台本を作ろうということになり、薩めぐみさんと、エリック・サティを弾くピアニストの島田リリさんを中心にした台本を、私がつくり上げる形になりました。
それが終わって、1週間後ぐらい後に芦野さんから電話があって、「君、僕は本屋やるんだ。でも、まあ 3ヶ月で潰れる本屋なんで、人様には迷惑をかけられないからあのメンバーでやろうと思うんだけど。僕の姉と姉の友達と小林と、それから高橋さんとその友達とで立ち上げたい」と。

美術評論家を虜にしたアールヴィヴァン
水野 その本屋には、海外の展覧会のカタログであったり、普通の本屋が揃えないようなものは全部あったね。「本当に売れるのかよ」と、竹内常務が言ったのもよく分かる話で。僕は「売れないかもしれませんね。だけど、ここにしかないってことは確かです」と言いました。
高橋 私も後から知ったことですが、銀座のイエナっていう洋書屋、それから丸善にはある程度は、お取り扱いがあったようです。それから国内で、その洋書の取次をやってらっしゃるところもいくつかあって。それは開館前後に芦野と一緒に回らせていただいたりはしたんですが。そもそもまだ理解が浅いし、本気かどうかわからないところが相手に見えてしまったかもしれません。
水野 だけど、それがそのうち段々と海外で知られるようになって、海外から注文が来たりというような状況になった記憶があるんだけど。
高橋 海外から注文が来たわけではないんですけども、こちらからお声を掛けて、売り込んでいただいたってことがありました。
僕が驚いたのは、オープンしたら、哲学者で谷川俊太郎さんのお父様の谷川徹三さん、東野芳明さん、中原佑介さんといった美術評論家が来られたんですよ。シュールレアリズムを日本に紹介された瀧口修造さんも来られた。瀧口さんは美術評論家としては、キャリア、影響力ともに、もう第一人者でしたね。ご本人が来られたので、僕はもうびっくりしました。
そこでお相手をしたんですけれど、ご年配で「立って本を見ていられないから、椅子を出してくれないか」と。店内中から本をピックアップして、僕に持たせて、その机を前に置いて 1冊 1冊見ながら、お話をされるんです。
でも声が小さくて、聞き取れない。「これはマルセル・デュシャンがこういう時期にね」なんて、ひそひそ声で。
それがあるとき、瀧口さんから「ポンピドゥー・センター(Centre Pompidou)に、君らのことを話したので、声がかかると思うから」と連絡があったんです。
そうしたら本当に声がかかって、セゾングループのパリ支局を通じて、ポンピドゥー・センター(Centre Pompidou)で展覧会があった 2週間後には、ともかく 10冊だけ池袋の店に並べることができたんですね。
水野 10冊なら手で買ってもってきてもらえるしね。あの頃のパリ支局は絶対的なヨーロッパのネットワークをもっていましたね。あの当時はまだニューヨーク支局はなかったんだよね。
高橋 ええ、それでニューヨークは柳正彦さんというクリストのチームにいる若い知り合いがいて、彼に話をして、コミッションを払ってその役割をやってもらっていました。ホイットニー美術館(Whitney Museum of American Art)やニューヨーク近代美術館(MoMA)で展覧会があったら、ともかく 10冊は買って送ってもらう。
だから、向こうで 100ドルだったら、 200ドル近くの販売価格はなるんだけど。無いよりはいい、と。
水野 美術館に洋書を置くという発想が普通はなかったからね。置くとしてもイエナや丸善に販売をやらせるよね。
高橋 最初は芦野も、イエナさんにはお声をかけたようです。ただし、イエナさんもとても無理、という気分だった、ということでしたからね。
水野 そんなことを、入社2−3年の僕に社内ベンチャーとして出資してやらせてくれた。今でこそあるだろうけれど、 1975年の話だからね。 僕はあの時、本当に西武っていうめちゃくちゃな会社に入って良かったなと思いましたよ。
撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph
構成:森綾 http://moriaya.jp/