【ソトコト×日本ワーケーション協会連載】ソトコトと日本ワーケーション協会がコラボして、各分野、各地域で活躍するワーケーション推進者をゲストに迎えて、毎回対談。ワーケーションにおける現在地や未来の展望を語ります。
第3回目のゲストは、各企業にワーケーションを推奨している社労士の岩田佑介さん。社労士としてクライアントにワーケーションを提案しながら、岩田さん自身も月に2〜3回ワーケーションしている実践者です。日本ワーケーション協会のメンバーはじめ、周囲からも「ワーケーション社労士」と呼ばれている伝道者。前編、中編、後編の3編に渡って、岩田さんご自身の「ワーケーション社労士」のお仕事について深堀っていきます。(前編)
「働き方の専門家」として、ワーケーションを前のめりに推進中!
ソトコト 今回は、「ワーケーション社労士」として活動されている、社労士としてたくさんの著書も出されている岩田さんが登場です。早速ですが、端的に「ワーケーション社労士」って、何ですか?
岩田 そうですね、まずは社労士の説明からしていきましょう。社労士の正式名称は「社会保険労務士」で、社会保険と労務の専門家です。しかし、それではわかりづらいので、「働き方の専門家です」と言っています。
私のクライアント企業から「⚪⚪⚪のような働き方を会社に取り入れたい」というニーズを受けて、それを実現するための手助けをさせていただくのが仕事です。具体的には、就業規則を作ったり、労働時間の管理や方法を提案したり……。ワーケーションを提案することも多々あります。社労士としてクライアント企業にワーケーションを推進していますので、単なる社労士だけの肩書きではなくて、「ワーケーション社労士」と肩書きに載せて、®️(登録商標)も取っています。

ワーケーションを推奨する岩田さん。
ソトコト 企業にワーケーションという新しい働き方を提案して、理解してもらうのは、なかなかハードルが高そうですね…。
岩田 企業…特に管理系の部署は、まだまだワーケーションに否定的なところも多いのが現状です。実は私自身も、社労士として独立する前はワーケーション否定派でした。当時、保険会社で人事の責任者をしていたのですが、部署内のメンバーからワーケーション制度導入の提案を受けた時は、反対しました。「ワーケーション? なぜバケーションに企業がお金をかけないといけないのか? まだお金をかけるべき制度は他にあるでしょ! 労務リスクやコンプライアンスは、どうするの?」と、頭ごなしに却下しました。
ソトコト 今とのギャップがすごいですね!
岩田 当時保険会社に勤めていた時の人事メンバーからも、未だに「信じられない」と言われています(笑)。当時はテレワークすら否定的だったので、ワーケーションなんてなおさら賛同できませんでした。そんな自分が、今では月に2〜3回ワーケーションしないと落ち着かない身体になっているんですから…。
最初に副業解禁でテレワークをしてみたら、「これは、すごくいいぞ!」
ソトコト 何がきっかけで、肯定派に考え方が変わったのでしょうか?
岩田 それが、何かきっかけがあったわけではないんです。最初の一歩は、2018年頃に実践したテレワークでした。当時、副業解禁の波があり、会社に副業を導入するにあたり、自分自身でも副業をやってみようと、社労士としての個人の仕事を始めました。副業ですから、オフィスは当然自宅です。つまり、テレワークをやらざるを得ない状況になったわけです。で、やってみたら「これは仕事に集中できるし、すごくいいぞ!!」となりまして(笑)。そんなタイミングでコロナ禍に突入。ワーケーションが注目され始めました。テレワークのように自分自身が実践しないまま、ワーケーションを否定してはダメだと…。タイミングよくワーケーション企画の提案があり、自分自身もトライしてみることにしました。で、やってみたら「これは気分も変わるし、すごくいいぞ‼」となりまして(笑)。

宮崎県日向市のコワーキングにあるテラスにて。
波の音が心地良い。
ソトコト 実際ご自身でも実践していくうちに、変わっていったのですね。そこからなぜワーケーションをクライアント企業にもお勧めするようになったのですか?
岩田 今まで自分が抱いていた人事領域の課題が解決できるのが、実はワーケーションだと気づいたからです。企業の人事部に勤めていた時も、独立して社労士になってからも、大企業、中小企業問わず、組織に横たわる共通の課題が「停滞感」でした。それなりに事業が安定してくると、どうしても仕事ってルーチン化していってしまいます。それを打破するための施策を、人事部や社労士に求められるわけですが、どれも打ち手としては弱く、ずっとモヤモヤしていました。その突破口がワーケーションだ!とピンと来ました。ワーケーションという施策にワクワクしました!
ソトコト 確かに、毎日毎日ずっと同じ場所に同じ時間に来て、同じ仲間と毎日ルーチンに過ごしていたら、マンネリ化して、活気は薄れて停滞化してしまいますよね!
岩田 そうなんです! 変化がなければ停滞します。当たり前の毎日になるんです。だから「場所、時間、人」の変化が必要で、その3つを全部一緒に変えられるのが、ワーケーションだと気づきました。停滞化から活性化に変わる…大きな可能性を感じました。
戦略的に「ワーケーション社労士」と名乗るように…
ソトコト そこからなぜ「ワーケーション社労士」と名乗るようになったのですか?
岩田 実は「ワーケーション社労士」と自分から言い出したわけではないんです。ワーケーションを推進している社労士として、トークイベントに出演させていただいた時に、ワーケーション社労士とプロフィールに勝手に掲載されていました(笑)。とてもわかりやすいし、覚えてもらえやすいので、そこから「意図的」に肩書きに使っています。
ソトコト 意図的というのは?
岩田 一番の狙いは社労士仲間に、ワーケーションを認知してもらいたいから。ワーケーションが広がり始めた初期の頃にワーケーションを実践したのは、大手企業の社員が大部分でした。でも、日本にある企業の99%が中小企業なんです。つまり、ワーケーションが普及していくには、中小企業へのアプローチは必要不可欠です。社労士の主なクライアントは中小企業なので、社労士こそワーケーションの推進者になるべきだと!…こうした意味合いからも、意図的にワーケーション社労士と名乗っています。
ソトコト アツいですね! 社会全体、未来を見ている視野の広さを感じます! ワーケーションを広げるために登録商標まで取られたと、先程お話しされていたしたよね!
岩田 登録商標の取得は、攻めの戦略というよりも、「守り」のためです。ワーケーションの価値を理解しないままにワーケーションを推進したり、変に流行りモノのように広められたりしないように、その防御策として商標を取りました。
ソトコト なるほど。つまりキチンとワーケーションがブランディングされるための戦略だったのですね。さすが戦略家ですね! 去年「経営戦略としてのワーケーション入門」という本を出版されたそうですが、それも、ワーケーションをブランディングして、広げるための施策ですか?
岩田 もちろん広げるためというのは大前提としてありますが、企業でワーケーションを推進していくために、上司を説得する道具として、この本を使って欲しいという思いがあります。かつてワーケーション否定派だった自分を説得するための本です(笑)。否定派だったから、痒いところにも手が届くような「説得材料」を盛り込めていると思います!
ソトコト 書籍があったり、メディアに取り上げられると、説得力が増しますよね!ソトコトでも記事化して大きくワーケーションを取り上げて、ワーケーションを広げる材料として記事を使っていただければと思います。(中編に続く)
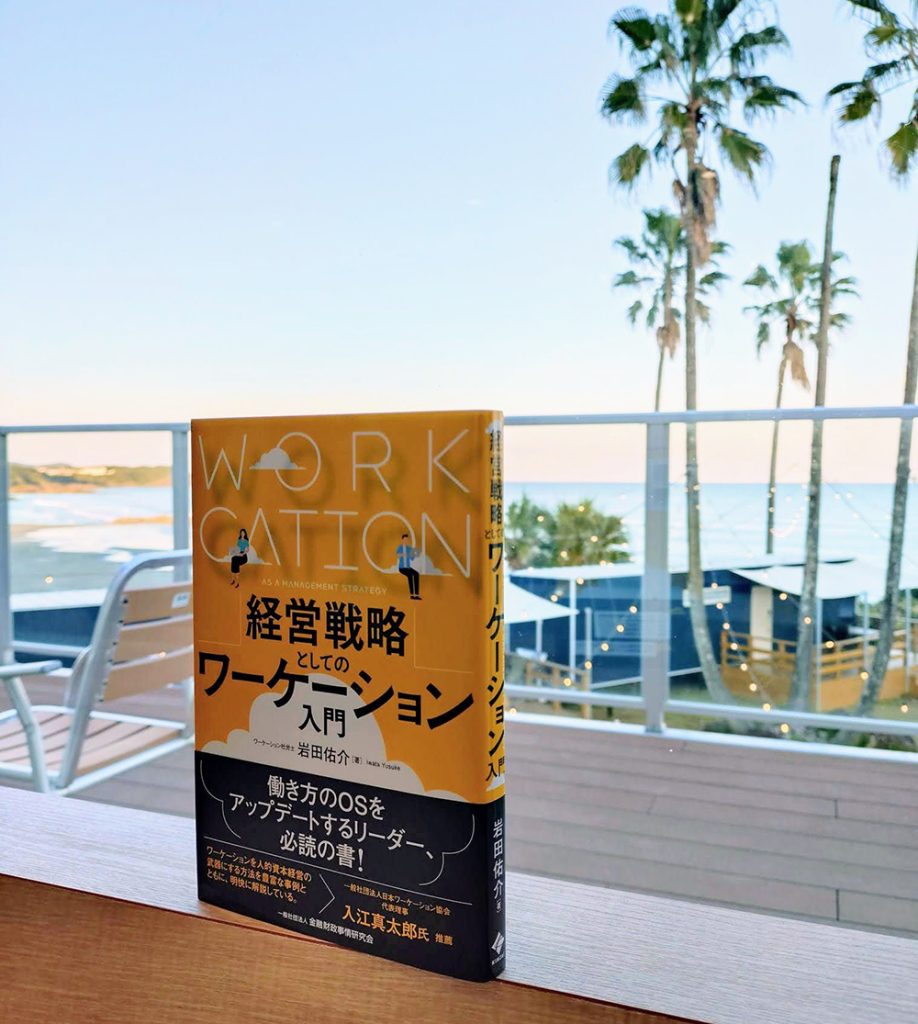
「企業でワーケーションを推進するための、
説得材料として使って欲しい」と岩田さん。
【岩田佑介プロフィール】
岩田社会保険労務士事務所。ワーケーション社労士 ®。パソナにて官公庁の地方創生プロジェクトの立ち上げに従事。 2016年よりライフネット生命保険に参画し、人事部長としてテレワークや兼業・副業など働き方改革を統括したのち、独立。2021年より観光庁の「新たな旅のスタイル促進事業」「ワーケーション推進事業」のアドバイザーに就任。著書に「図解労務入門」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)、「ベンチャー・スタートアップ企業の労務 50のポイント」(セルバ出版)、「経営戦略としてのワーケーション入門」(金融財事情研究会)など。
【一般社団法人日本ワーケーション協会プロフィール】
ワーケーションを通した「多様性が許容される社会実現」を目指し、2020年7月に発足。300を超える会員(自治体・企業・個人)とともに、様々な取り組みを行っています。
















