仲村健太郎さんは京都市左京区に拠点を構え、活動するグラフィックデザイナーだ。
福井県・永平寺町出身。デザインが好きだった仲村さんの、中学・高校時代の愛読書は『広告批評』。周りにデザインについて話の合う友人は少なかったという。京都造形芸術大学情報デザイン学科に進学し、そこでコミュニケーションデザインを学んだ仲村さんは、2013年春に卒業後、そのままフリーランスのデザイナーとして仕事をするようになる。
「文字を機能的に、美学的にどう組むか。それは『技芸』、つまりエンジニアリングとアートの領域であり、4年やっても学びきれなかったという感触が卒業証書をもらったときに自分の中にあって。どこかの会社や事務所に入って“お弟子さん”になると、その師匠のやり方は学べるけど、自分一人でもっと“探索”したいという思いがあって、どこにも入らず自分で始めたような気がします」
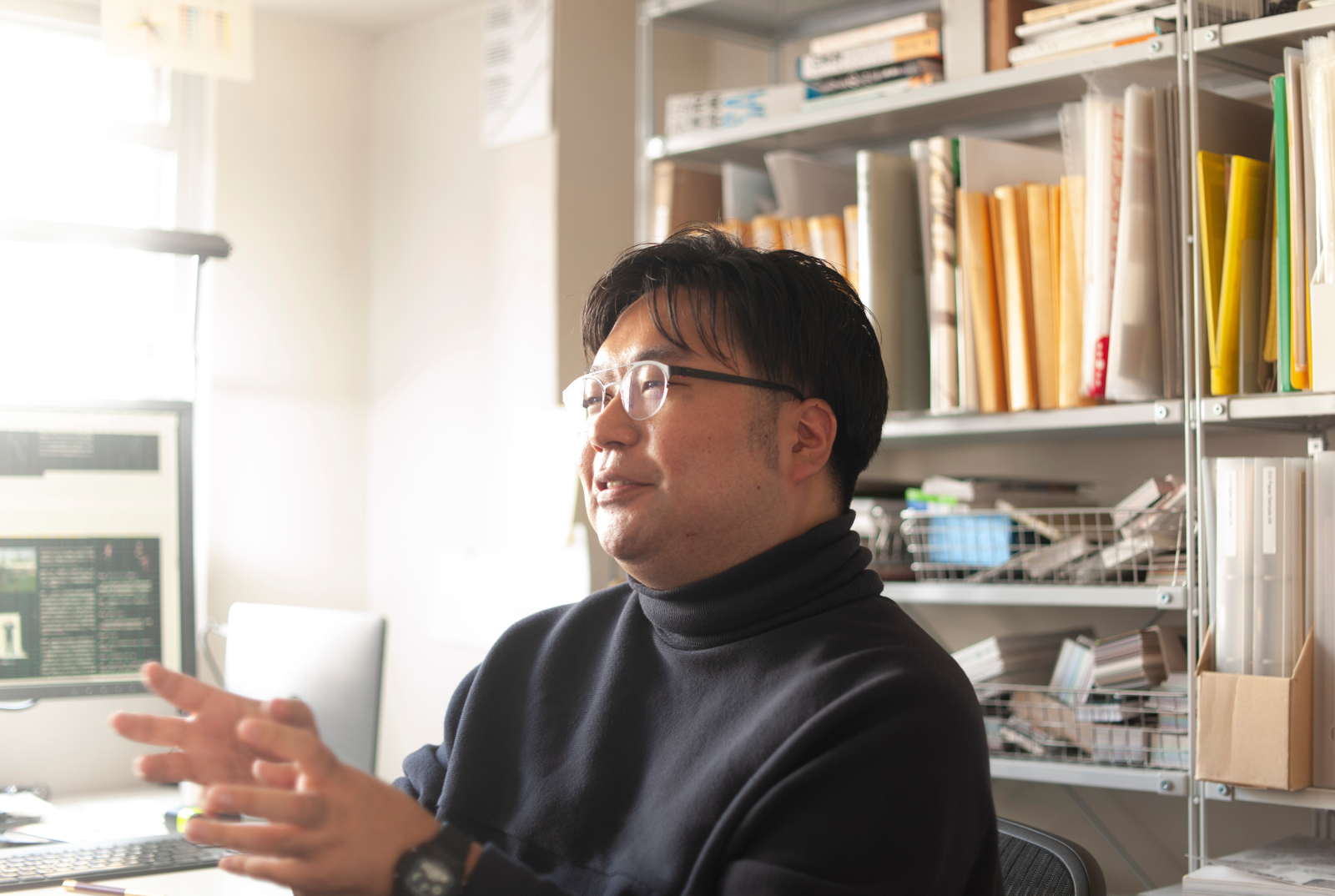
共通解釈をつくること。主観と客観の間で物事を捉えること。
自身、「イエス、ノーがはっきりしていない美術の仕事がおもしろい」と話すように、アート系のデザインを数多く手がけてきた仲村さん。代表的なものの一つに舞台『プラータナー:憑依のポートレート』の公式ガイドブックのデザインがある。一般的な作品のガイドブックに型があるとすれば、そこには物語のあらすじや登場人物についての解説、場面カットなど、つまりは「作品の補足情報」が詰まったものだろう。が、仲村さんのそれはまったく違う。必要な情報を連ねつつも、作品に漂う複雑な文脈や、世界観そのものが誌上を使って再現されている。グラフィックの表現も秀逸だ。ここまでできるのか、と感嘆する。例えばページを重ねるごとに印刷の色数が減り、色自体も薄くなり、最後は印刷も粗く、紙の厚さまでも薄く。「喪失感のある物語なので、色が無くなっていくというか、ちょっと茫漠とするつくりにしようって。最後は透けちゃうような紙になって、おしまいに」。

デザインは、舞台の映像を何度も見返し、関係者らとの対話を重ね、提案したものだという。「自分の勝手な解釈だけでなくて、共通解釈をつくらないと、独りよがりのものになってしまう。対話をして、ヒントをもらう部分と、ヒントのバトンを受け取った後に、デザインでどこまでおもしろくできるか、って考えることから始まります」。
それは仲村さんがよく用いる「間主観」という考えにも通じるのだろう。「客観的な好みと主観的な好みってありますよね。例えば自分では着ないけど、いいなあと思う服。それに近くて。デザインも、全部主観でやっているわけではなく、ご依頼していただいたものを、主観と客観の間で物事を捉えたいと思っています」。
対話を大切に、「明るく話しかけるように」デザインする。
さまざまなデザイナーのスタイルがある。仲村さん曰く、「もらった素材で『どう美しく組むか』を考えるのは、レイアウトがうまい人がやること。自分も、そうできたらしたかもしれないけど、ただ待っていることはあんまりないですかね。能動的に解釈したほうがおもしろくなるし、『これってこういうことなんだ!』って発見を自分で見つけたほうが仕事も楽しいですよね」。

いわゆる「提案型」のデザイナーだが、その塩梅も、仲村さんは絶妙だ。デザインと“会話”できる感じと言えようか。強めのグラフィックデザインを見たことはないだろうか。それ以外の解釈を認めないような、いや解釈を求めないような、メッセージが個性的で濃いもの。「そういう“かっこいいデザイン”に憧れた時期もあります。それはそれで一つの在り方ではありますが、僕のは『明るく話しかけるように』デザインしている感じですかね。自分のキャラクターがそんなにソリッドじゃないからもある(笑)。でも、自分と自分の“デザインの話し方”をズラしてしまうと、あんまりよくないってどこかで気づいて。地域性もあるかもしれませんね。福井の人ってすごくゆったりしていて、なんか、そういう自分のメンテリティ、バイオリズムみたいなものが、コミュニケーションの根本にある。デザインで会話したり、コミュニケーションできたらいいなって思っています」。
“視覚的な言葉”の可能性を信じ、仲村さんの『技芸』の探索は続く。
「デザインで会話する」とはどういうことだろう。「答えをそのまま手渡す、というとことではもちろんなく、その人の中で『あ、わかった!』っていうような、捉え方を変えるきっかけになるような、解釈したくなるようなモノをつくりたいと思っています」。
右から左に“渡す”だけじゃなくて、なにかに喩えてみたりする。そんなメタファーも仲村さんの真骨頂だ。「まず『自分の中で解釈した言葉を持つ』というか。その言葉を、デザインという、言葉ではない『視覚的な言葉』に翻訳して、いろんな人に伝えていく。見た人がそれを受け取って、新しい解釈にまで至ればいいなあって思っています」。

仲村さんはグラフィックデザイナーを、「不特定多数の人と視覚的な言葉を通してコミュニケーションする仕事」だと説明する。「視覚的な言葉」こそがデザイン。発信する人との対話によって得た言葉を、デザインを使って、どう受け取り手へ渡すか。さらに一歩進んで、彼は”探索“を続けている。
「人に伝わるときに、言いたいことと変わっていてもいいと思っていて。言葉ってその意味どおりに伝わらないこともあると思うんです。しょんぼりした感じで『元気です』って言われたら心配しちゃいますよね。話し言葉では、身振りや手振り、口調が加わることで別の意味で伝わったりする。でも、ズレるからこそ話すことに意味があると感じています。デザインという”言葉“で会話するときには、意味の伝わり方をちょっとだけ豊かにしたいなっていうのが、やりたいことかもしれないですね」。 仲村さんのデザインはシンプルでいて複雑。意図的であり実験的。かつ言語的。グラフィックデザインの可能性を見せてくれました。























