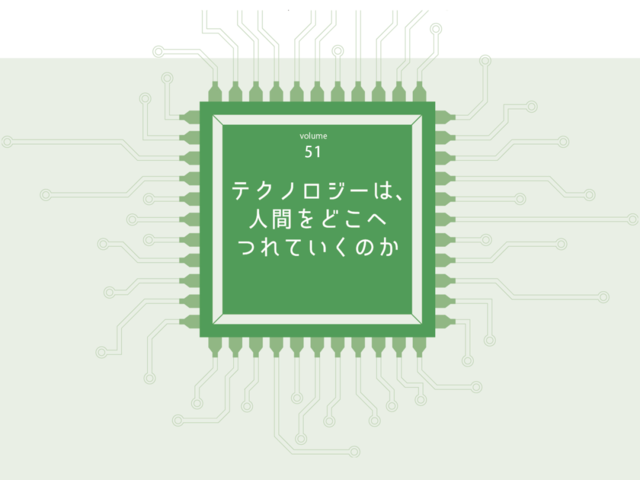生きる日々に、デジタルが染み込む。いまのところは、「デジタル社会」と称したりする。しかし、わざわざ“デジタル”なんとかと冠をつけていたことはやがて滑稽になる。染み込み切ってしまえば、空気同様、そこに意識すら及ばない。
2017年4月に『国立社会保障・人口問題研究所』が公表した「日本の将来推計人口」における「出生中位・死亡中位推計」結果によると、2042年以降は65歳以上の人口が減少に転じても高齢化率は上昇を続ける。2065年には38.4パーセントに達して、国民の約2.6人に1人が65歳以上の者となる社会が到来すると推計されている。未来を正確に予測することはできないが、淀みない流れが反映されたこの統計は、動かしがたい未来を形づくる。
デジタルが浸透した社会においては、高齢者がデジタルの蚊帳の外に置かれるという思い込みは過去のものとなっていて、むしろ高齢者ほど重宝し、生活のあらゆる場面でデジタルの恩恵を受ける。デジタル・ネイティブ世代も高齢者層にスライドするので、世代間のデジタル・デバイド(情報格差)も自動消滅していく。
デジタルと高齢化が同時に進む社会。「デジタル高齢社会」で顕著になるのはデジタル遺品の問題だ。故人が残したスマートフォンやPC、クラウドサービスやハードディスクの中のデータ、SNSのアカウント。ネットバンクや株式などの口座情報、毎月課金されているオンラインサービス。放置されたままだと遺族に被害をもたらすものも残されているかもしれないが、故人のデータは見られたくない、知りたくない。故人にとっても遺族にとってもプライバシーの壁が立ち塞がる。放置はできずに対処が必要な場合も、パスワードがかかっているため、専門業者に依頼をして解決できるか否かということになる。
日本の個人情報保護法の現状においては、生存する個人の情報が個人情報であり、死者の個人情報は保護の対象にならない。プライバシーの権利も一身専属で、譲渡も相続されることもない。「デジタル高齢社会」に突入するにもかかわらず、死後のデータの取り扱いを定めたルールは未整備だ。
フェイスブックでは、生前の本人の意志で追悼アカウントとして保存や削除を選択できる。グーグルも、本人が指定した相手に通知してデータの保存や消去ができるサービスを提供している。各種IDやパスワードを遺言書とセットで家族や弁護士などの専門家に管理を委託しておく手段もある。「デジタル遺品」とどのように遺族が向き合うかというよりも、生きる者が「デジタル終活」を行うことが「デジタル高齢社会」の慣習になるだろう。残すべきか残さぬべきかは、遺族よりも当の本人のほうが判断と対応がしやすい。
と言われても、生きているうちから「デジタル終活」に入るのは実に切ない。理解はできても、行動に移せない。なるべく避けて通りたい。それが包み隠さぬ心情というものだ。
ただ、そこは考え方ひとつである。未来を考えることはいまを生きることだ。未来はいまが連なるその先にあり、いまとつながっている。「人生の店じまい」ではなく、未来をポジティブに考え、その結果としていまを整理する。未来を感じさせない“終活”という言葉が諸悪の根源だとすれば、「デジタル終活」というコンセプトもやめにしよう。生きる中でデジタル・データを整理することは、未来のためのいまの活動であり、未来のためにいまを生きている証しである。
デジタルは、日常生活や社会だけではなく、死生観にまで染み込み始めている。その善し悪しを問うよりも、それぞれが死生観を熟考し直す好機だと捉えたい。