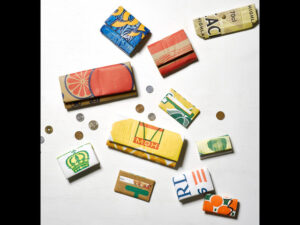江戸時代は宿場町として栄えた面影が残る、島根県仁多郡奥出雲町の三沢地区。その一角に昭和2年(1927年)建築の民家を改修した、『古民家オフィスみらいと奥出雲』(以下、『みらいと』)があります。高齢化が進み、人口が減少している同町に若者の関心を引く産業を興すことができたら、と誕生しました。時代に合わせてアップデートされた、古民家のあり方とは──。
交流拠点も兼ね備えた古民家シェアオフィス。
奥出雲町で、起業・創業活動を支援するためのレンタル・シェアオフィス『みらいと』。空き家などの活用提案を行う不動産業や農業IoTサービスの研究機関など多様な企業が入居し、東京のIT企業のサテライトオフィスとしても利用されている。広々としたコワーキングスペースや会議室もあり、立派な日本庭園を眺めながら仕事ができる、地域ならではの特色を生かした環境だ。

そして、最初に人目を引くのが、施設の中と外をつなぐ土間スペースだ。古民家を改修する前、住民対象のワークショップが開かれた。その時、地域の人が集まってお茶を飲んだり、交流したりする場が欲しいという声が上がったことから、地域の交流拠点も備えることになった。

この土間スペースでは、毎週木曜日の10時から15時まで、「おしゃべり笑店『みらいと』」を開催。日用品・食料品が土間に並び、大きなテーブルにはお茶が用意される。これを主催するのは、『みざわ小さな拠点づくりの会』、そして『みらいと』の入居者で、NPO法人『ともに』代表の吉川英夫さんだ。三沢地区の出身の吉川さんは、高齢者の生活支援や地域でよい関係性を築きながら過ごしていく仕組みづくりを行っている。「プライバシーを気にする時代の風潮もあり、子どもの頃に比べて地域の人との関係性が稀薄になってきたように感じます。これからの時代、お互いに助け合っていけるように、新しい居場所が必要だと思っていました」と吉川さんは話す。

“買い物”という動機が、明日を運ぶきっかけに。
『みらいと』の土間スペースは交流拠点として造られたものの、すぐに利活用するには住民の心理的なハードルがあった。「自分たちの知らない企業が入居している状況もあり、仕事に関係のない自分たちは入っていけない場所と誤解が生じていたようでした。入居者と地域の人をつなげたいという気持ちもありました」と吉川さん。
そんなことを考えていた矢先、昨年3月に同地区唯一の小売店が閉店し、ここから約5キロメートル離れた町の中心部まで買い物に行かなければならない状況に。
「週に1度でもここで買えれば、生活支援の一つになる。それに、最初はここをフリースペースにと考えましたが、買い物の目的があるほうが人は立ち寄りやすいと思いました」。同町にあるコンビニエンスストアの協力を得て、毎週木曜日にパン、お菓子、お弁当、調味料、生鮮食品、雑誌とあらゆるものが営業時間内に買えるようになった。さらに、昨年12月の取材時には、この日初出店する鮮魚店のトラックが表に止まり、店を広げていた。

そこへ、地域の人がちらほらと集まり、カゴいっぱいに好きなモノを入れ、レジで会計を終えると、土間にある大きなテーブルに座り、お茶を飲んでひと息ついた。すると、別のお客さんが持参した手づくりのおやつが差し出されて、話が弾み始めた。

この取り組みを始めて10か月、この風景がようやく日常のものになってきた。しかし、ここまでには苦労もあった。「レジや接客などの運営を地域の人にお願いしていますが、協力者を見つけて軌道に乗せるまでが大変でした」と吉川さん。退職した60〜70代の女性や、産休中のお母さんなどに協力を求め、都合のよい時間帯に来てもらうことに。協力者もだんだんと自分の役割が分かってくると、今度は自分たちで考えて行動するようになってきた。「今まで干物などは売っていたのですが、やっぱり生の魚が欲しいという声をお客さんから聞いて、スタッフの誰かが魚屋さんを見つけて、交渉し、連れてきました」。

さらには、月に1度食事会も開催。産休中にスタッフをしていた栄養士の女性が始め、職場に復帰してからも月に1度休みを取って活動を継続しているという。「高齢者向けのサロンやデイサービスなどもありますが、決まった日時に行くことでだんだんと利用者の気持ちに義務感が生じてしまう。ですが、この取り組みなら、都合のつく時、来たい時に足を運び、さっと用事を済ませることも、お茶を飲んでいくこともその人の自由。そんな場が、その人の生活の一部になればと思います」。ふらりと立ち寄れる場所があることは、暮らしを豊かにする。

INTERVIEW 設計士の宇田川孝浩さんに聞きました。
まちとつながる、職場と住居を兼ねた古民家とその活かし方。
これからの暮らしに合う、古民家が持つ機能。
「住宅」や「家族」について調べていくと、私たちが当然と思っている独立した“家族”は明治時代以降に意識されるようになった形態であり、それ以前は住む場所と働く場所が分離されておらず、地域の人と協力して農業やものづくりをしていたことが明らかになりました。つまり、その頃に建てられた古民家には、人が働き、人が集まる機能が備わっているということです。『みらいと』の改修は、元々古民家が持っている性質を発見していくプロセスでした。

奥出雲町三沢地区も時代とともに変化し、若者が少なくなり、高齢者の独り暮らしが多くなってきました。“家族”を前提にした住まいや町の在り方が難しくなっている今、昔の人たちが助け合って生きてきたように、ここでは家族を超えた関係がないと生活するのが難しい状況にあります。以前の暮らしの構造が残っている古民家からは学ぶことがたくさんあり、それを生かした設計を試みました。
やはり、最初に素晴らしいと思ったのは、町につながっている土間でした。土間に人が集まる様子は人の気配が少ない通りに対しても魅力的で、ここでやっていることがこの建物の表情になります。入り口近くに仕切った小さなスペースがあったのですが、それは取り払い、曇りガラスを透明なものに替えました。

また、土間には大きなテーブルを置きました。茶の間でテレビを見て家族で団欒を楽しむ時代もありましたが、今の家族が共有する時間はご飯を食べる時です。そういった暮らしの中心は大きなテーブルにあると考えています。ここ『みらいと』では、地域の人がお茶を飲んだり、入居者が打ち合わせをしたりするのにテーブルが使われています。やっていることは異なっても、場所を共有することで、入居者同士が、また、入居者と地域の人が知り合うことにもつながることを意識しました。

コワーキングスペース部分については3間続きにして、外の景色を見ながら仕事ができるよう障子をすべて透明な素材に。また、この裏にあるシェアオフィスについても1間を特製の衝立で仕切ったり、部屋と部屋の間の欄間をそのまま生かしたりして、隣の気配が感じられる造りにしています。古民家は壁で構造を支える現代の住宅とは異なり、柱と梁で屋根を支えていて、内部の可変性が非常に高くなっています。布団を片付ければ、そこでご飯を食べたり作業をしたりと、部屋ごとの機能は固定されていませんでした。
集まった人が自由に利用できるという点は、古民家ならではのよさだと思います。ここは、顔が見えたからちょっと寄っていけるような、自由に人が集まり、それぞれが好きなことができるような場であったらいいなと思います。

『宇田川孝浩建築設計事務所』代表・宇田川孝浩さんの人が集まる場づくり3つのポイント
大きなテーブルを建物の中心に。
人が場所と時間を共有できる食事は、暮らしの軸。大きなテーブルなら、食事以外にもそれぞれが好きな時間を過ごせる。
日常の延長線上にある場所。
商店のような日常の延長線上にある場所であると入りやすくなる。その場に、それぞれの居場所があることも大切。
区画や部屋からはみ出ること。
現代は、建物も部屋も機能や用途で区画されてしまう。そこをはみ出せば、人と人、人とまちが関われるようになる。
人が集まって生まれたこと、変わったこと。
茶飲み話ができるように。
買い物後、自然に集まり、互いに元気でいることが確認できる場になった。