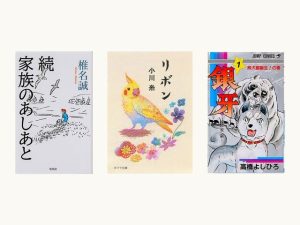誰ひとり取り残されず、しなやかに強く、幸せに暮らせる持続可能なまちへ。
SDGsに取り組む自治体が増えてきているが、
その好事例として紹介したいのが、北海道上川郡下川町。
SDGsをまちづくりにどう活用しているか、訪ねました。
SDGsの17項目は、いわば「チェックリスト」。
下川町のありたい姿と照らし合わせています。
住民と一緒に考えた、
下川町の7つのゴール。
北海道・下川町。林業や木質バイオマスエネルギーの取り組みで知られるまちだが、2030年、人口は3300人から2400人へ減少し、高齢化率は43パーセントに、小・中学校は1学年平均13人にという、目を閉じたくなる予測数値が挙がっている。将来の課題に今から手を打つ必要があると考えていたとき、国連がSDGsを採択した。「下川町もまちづくりにSDGsを取り入れて、レベルアップを図ろうと決めました」と話すのは、下川町政策推進課SDGs推進戦略室室長の蓑島豪さん。「SDGs17の目標が、下川町のどの取り組みに当てはまるかを検証し、下川版SDGs『2030年における下川町のありたい姿』を、7つのゴールとして設定していきました」。

設定する際にポイントとなったのは、地域住民が中心となってゼロからつくったこと。「下川町総合計画審議会という自治体の最上位にある総合計画を審議する場に『SDGs未来都市部会』を設け、住民10人と行政職員約10人が13回、侃々諤々話し合って決めていったのです」。
「SDGsって、何?」という段階からスタートした部会で、17の目標と下川町の現状を照らし合わせた。例えば、SDGsの「5/ジェンダー平等を実現しよう」。ジェンダー課題は国同様、下川町も弱かった。そこで、女性住民から、女性が活躍できる社会をどうつくったらいいかを考えるための女子会(後に「下川りくらしネット」に)が発案され、持続可能で幸せな暮らしを目指し、この町でできることに取り組んでいる。

また、下川町には海がないので、「『14/海の豊かさを守ろう』の目標はパスかな?」という声が上がったが、「待てよ。海はなくても、川がある。サクラマスが遡上して上流で産卵する、その産卵地は下川町だ。川の環境を守ることは、海の豊かさを守ることにつながる。それが目標14に対して私たちができること」と議論を深めた。そんなふうに、下川町を見つめ直すための「チェックリスト」としてSDGsを活用することで、見えなかった課題や優位性が発見でき、未来の「ありたい姿」を考える大きなヒントになったのだ。
そうして決まった下川版SDGs「2030年における下川町のありたい姿」の7つのゴール。30年までの町の総合計画に記され、今後はゴールに向かってアクションを起こす段階に入る。「どんなプロジェクトが立ち上がるのか楽しみです」と、蓑島さんも期待を寄せる。

『ソトコト』編集部が見た、下川町の未来づくり。
森を駆け回るうちに、
SDGsのゴールを達成。
国連が定めたSDGsの目標を「チェックリスト」として活用し、独自の7ゴールをつくった下川町。2018年には国から「SDGs未来都市」に選ばれた「意識高い系」の自治体と言えそうだが、一朝一夕で環境や社会課題への意識が高まったわけではない。

さかのぼれば、1953年に国有林野整備臨時措置法が制定され、下川町でも町民の財産をつくろうと、1221ヘクタールの国有林を取得したことに始まる。ところが翌年、洞爺丸台風に襲われ、取得した森林が一晩で風倒木の森に。町はその災害を機に、60年間で1サイクルさせる森林経営に取り組むことを決定。毎年約50ヘクタールの人工林の取得を続け、60年以上が経った今、約3000ヘクタールを確保。1年間に50ヘクタールの人工林を伐採すると同時に、そこに新たな苗木を植え、60年間で1サイクルする循環型森林経営を確立し、2003年にはFSC認証も取得した。建材に使えない木や林地残材は木質バイオマスボイラーの燃料に。町内には11基の木質バイオマスボイラーが設置され、30の施設に熱供給を行い、地域熱自給率は49パーセント。化石燃料を使った場合より、年間1900万円ほどの燃料費が浮くため、それを積み立てて子育て支援、例えば、幼児センターの利用料の軽減、給食費の負担軽減、中学まで無料の医療費財源に充てるなど、森の恩恵を地域に循環させている。

そんな「環境未来都市」としての取り組みに惹かれ、『フプの森』の田邊さんや、『SORRY KOUBOU』の山田さんや小松さんが下川町で起業した。彼女たちも「意識高い系」かもしれないが、環境保全や安心・安全をけっして上から目線で唱えない。むしろ、FSCやSDGsを気にせず、感覚的に森を楽しみ、森の恵みに癒やされてほしいと笑顔で話す。そんな彼女たちのように、森の中を駆け回ってほしい。森にふれる中で未来の暮らし方を見つけ、知らない間にSDGsのゴールテープを切っているかもしれないから。