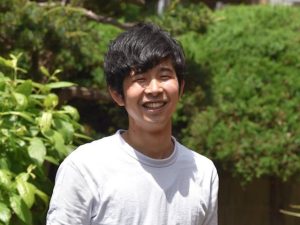東北のことを知り、東北ファンを増やすための取り組み「Fw:東北 Fan Meeting」(フォワード東北ファンミーティング)。その一環で、東北への移住をテーマにした「東北暮らし発見塾」というオンラインイベントが行われています。第3回は「⾷・農×移住で拓く村の魅⼒づくり」と題して、2023年11月下旬に開催されました。
移住者や関係人口が、村に新しい風を吹き込んでいる。
今回の「東北暮らし発見塾」の舞台は、岩手県北東部に位置する野田村。北には野田漁港に突き出した約50mの断崖「大唐の倉」がそびえ、南には清流・安家川が流れ、西には和佐羅比山、そして東にはゆるやかな弧を描くように海岸線が続く十府ヶ浦など、海・山・川に囲まれた自然豊かなところです。

最初に小田祐士・野田村長から、野田村の魅力について紹介がありました。「野田村は中山間地域にある普通の田舎ですが、ワカメ、アワビ、ウニなど豊かな海の幸や、山葡萄や山菜といった山の幸など、自然に恵まれています。特に野田特産の『荒海ホタテ』は、日本一おいしいと自負しています」と話します。また、海水を窯で炊いて結晶化させる、伝統的な直煮製法でつくられた天然塩「のだ塩」も、特産品として知られています。
野田村にはかつて、日本有数のマンガン鉱山として知られていた野田玉川鉱山がありましたが、閉山後は人口が減り、現在の人口は約4000人。「しかし、人口は減っても元気はなくなっていません。小さな村ですが、特に東日本大震災以降、関西や首都圏の大学生と交流するなど、関係人口づくりに挑戦しています」と小田村長は力を込めます。その取り組みのひとつに『心はいつも野田村民』というバーチャル村民登録制度があり、1300人近い登録者がいて、関係人口となっています。また、一次産業を中心に地域おこし協力隊も活躍中です。「協力隊員は、村の人たちにとっては若い孫のような存在ですね。若い人のパワーはすごい。村の活力になっています」と小田村長。震災前は外からやって来る人に対して構える村民が多かったとのことですが、震災後にボランティアなどでさまざまな人が村に入ってきたことで、次第に心を開くようになったそうです。

続いて、登壇者3人が自己紹介を行いました。ひとりめは、野田村出身の安藤智子さん。高校卒業後に上京して調理師免許を取得し、上場企業の有名レストランに勤務していましたが、震災を機にUターンして地産地消レストラン 『Osteria Vai-getsu』を開業しました。3人の子育てをしながら、家業である荒海ホタテの養殖も手がけています。

ふたりめ、山葡萄農園『Lu.cultiver』を営む山口光司さんは、栃木県宇都宮市の出身。大学卒業後に地域おこし協力隊として野田村に移住し、野田村の特産品である山葡萄の生産に携わってきました。「野田村では、震災復興の取り組みとして山葡萄ワインづくりが始まりましたが、その原料となる山葡萄の生産者が高齢化によって減っていたので、何か力になれたらと思ったのです。村の人たちに助けてもらいながら、大変な中でもやりがいを感じる日々を過ごしています」と山口さんは話します。

3人めは、現在地域おこし協力隊として活動している外舘崚さん。東京生まれですが、両親が野田村出身で、小さい頃からお盆やお正月に村を訪れる機会があったそうです。福祉の仕事、アウトドアメーカー勤務を経て野田村に移住し、障がいのあるスタッフが働く『カフェrokka』の運営などに携わっています。「野田村に来て、東京に住んでいたときよりも“質のよい”生活ができていると感じています」と、外舘さんは野田村暮らしを満喫している様子です。

のだ塩に山葡萄。食が地域のアイデンティティに。
トークセッションの後半は、小田村長と3人の登壇者、そして弊誌編集長の指出一正も加わって、クロストークが行われました。まずは「のだ塩」の話題に。「のだ塩はうま味たっぷりで、えぐみがなく、甘みを感じるまろやかな味わいです。とても評判がよく、全国展開しているパン屋さんや、食肉加工などでも使ってくれています。『道の駅のだ』で食べられる、のだ塩ソフト、のだ塩ラーメンは自慢の逸品で、観光客からも大人気です。のだ塩を使ったおにぎりもおいしいですよ!」と小田村長は熱く語ります。安藤さんも「のだ塩はレストランや家でも使っています。新米にのだ塩があれば、それだけでごちそうに。ごはんよりも塩を食べていると言ってもいいほどですね」と、のだ塩を絶賛しました。

野田村で古くから行われていた製塩は、明治時代に塩が専売制となったことで廃止されました。しかし平成に入ってから、村の青年たちが製塩を再開。製品化を望む声を受けて、野田港に『のだ塩工房』が建設され、のだ塩の商品化が実現しました。軌道に乗ってきた矢先、東日本大震災の大津波で『のだ塩工房』は流失。製塩も中止となりましたが、2012年2月に新しい工房が完成し、製塩が再び始まりました。野田村の特産品として、地域内外の多くの人から愛されています。
のだ塩の話を受けて、指出は次のようにコメントしました。「塩はシンプルなものですが、それが極上であるというのは、今年秋冬ファッションのトレンドである『クワイエット・ラグジュアリー』に通じますね。これは“華美ではなく、控えめで本質をついたおしゃれ”のことですが、ローカルの文脈では、本質的な豊かさのある地域を『クワイエット・ローカル』と呼べるかもしれません。塩が地域のアイデンティティになっていて、塩がファンや関係人口を増やしている野田村は、まさにクワイエット・ローカルだと思います」。
そして、野田村のもうひとつの特産品は山葡萄。太平洋から吹き込む冷涼な風・やませによって、じっくり熟成されて育ちます。「山葡萄は、効率化された野菜などの生産とは違って、時間をかけて育てていきます。つるが絡まないように切るなど、手間がかかるのですが、その分創造的でおもしろいですね。野田村の山葡萄は糖度が高い段階で収穫するので、山葡萄ワインも糖度が高く、甘く濃い味わいが特徴です」と山口さんは話します。しかし、現役の山葡萄農家は4軒だけとのこと。山葡萄の圃場はたくさんありますが、使われていないところも多く、小田村長は山葡萄生産者が増えることを願っています。

安藤さんも、野田村の食材・農産物に魅せられたひとり。「帰省時、バーベキューで振舞うメニューを考えていたときに、野田村の食材のすばらしさに気づきました。田舎だから野田村を出て行ったのに、その魅力を再発見したのです。野田村の食材でフルコースをつくろうと決意し、その3日後には店舗工事の発注をしました」と安藤さんは振り返ります。そんな安藤さんに向けて小田村長は、「野田村に帰ってきてくれてありがたい。安藤さんは畑もやっておられて、食材も自家製にこだわっているのがすごいと思います」と伝えました。
このように野田村では、食・農が地域の特徴・魅力となっており、移住やUターンにもつながっています。
“帰省”したくなる、野田村は“みんなのふるさと”。
野田村では、移住やUターンの促進に加え、冒頭で小田村長が触れたように、関係人口づくりにも力を入れています。「震災後、各地の大学生が野田村に出入りするようになりました。大学生たちが来るたびに一緒に飲んでいますが、彼らの視点や考え方は私たちにはない新鮮なもので、非常に参考になります。若い人たちが来るだけで新しい風が吹くので、移住でなくても、気軽に遊びに来てもらえたらうれしいですね」と小田村長は話します。
それに対して指出は、「学生さんたちは小田村長を慕って、“帰省”の感覚で野田村に来ているのではないでしょうか。実は今、“帰省先”を探している都会の若者が多いんですよ。帰省は、有名な観光地に遊びに行くというようなイベントではなく、日常の延長にあるものなので、リピーターが生まれます。関係人口づくりにおいて、大事なポイントですね」とコメントしました。
外舘さんも、両親の故郷への帰省が野田村との接点でした。外舘さんは、障がいのある人たちが地域で活躍するためのサポートを行う中で、さまざまな人々と関わりながら、自身と地域との“関わりしろ”をつくっています。地域おこし協力隊として奮闘する外舘さんに対して小田村長は、「外舘さんが運営に携わっているカフェは、障がいのある方々の居場所になっています。多様な人たちがそれぞれ活躍でき、みんなが協力し合って村をつくっていけるように、引き続きがんばっていただきたい」とエールを送りました。

トークセッションの後は、山口さん・安藤さん・外舘さんの3ルームに分かれてブレイクアウトセッションが行われました。参加者たちは、野田村の印象や、自身の移住に対する関心などについて話をしたり、登壇した3人に野田村での生活や仕事について尋ねたりしました。ブレイクアウトセッション後、参加者からは「いろいろな人にとっての“ふるさと”になるというコンセプトがよいですね」「野田村に“帰省”したくなりました」といったコメントが寄せられ、野田村への興味関心や親近感が伝わってきました。
最後は、復興庁復興知見班参事官の後藤隆昭さんが次のように挨拶して、締めくくりました。「野田村は素朴なところですが、東京から見ると非常に贅沢な場所です。その魅力を再発見する形で、“帰省”や移住・Uターンの方々がうまく発信されているなと思いました。震災復興において、単に元に戻すだけではない『よりよい復興』を意味する『Build Back Better(ビルド・バック・ベター)』という考え方がありますが、これはハード面だけでなくソフト面でもいえることで、野田村では震災を機によりよいものが生まれてきていると感じました。一方で、一次産業をはじめ、さまざまなところで担い手が不足している現状がありますが、裏を返せば、野田村ではだれもが担い手になれるわけです。移住はもちろんですが、まずは関係人口やバーチャル村民としてでも、野田村と関わりをもっていただけたらと思います」。

———
photographs by H-tus Co., Ltd.
text by Makiko Kojima