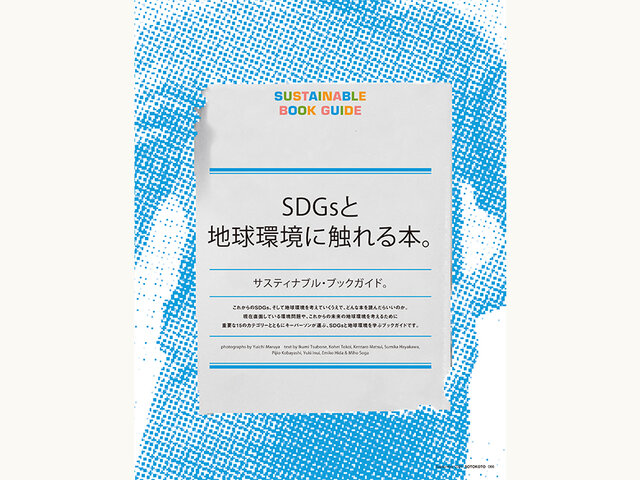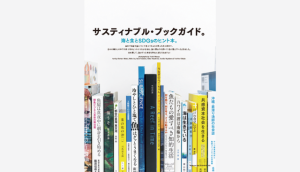葭内ありささんが選ぶ、SDGsと地球環境に触れる本5冊
森本さんは真に良い布を作ることに心血を注ぎましたが、単に伝統の絹絣をよみがえらせたかったわけではなく、森を再生し、絹絣づくりを復興させることで、それに携わる人々が食べていけること、生活できることが非常に重要だとおっしゃっています。そんな森本さんの高い芸術性を携えたものづくりへの哲学、持続可能で循環型の森づくりや仕事づくりを実践されている姿に感動し、私は森本さんに会いにカンボジアへ向かいました。「伝統とは古いものを守ることではなく、未来へ向かって新しいものをクリエイトすることであり、先人もそうしてきた」と、若い頃に京都で手描き友禅の工房を主宰されていた森本さんならではの言葉が胸に残っています。2017年に亡くなられた後も、森本さんが代表を務められた『IKTT(クメール伝統織物研究所)』による「伝統の森・再生計画」の活動は現地の方々に受け継がれています。
また、『物には心がある。』は、人々がものに対してどれだけ心を込めてきたかが書かれていて、ものとは何かという根源的なテーマを考えさせられます。著者の田中忠三郎さんは青森県出身の民俗学者で、江戸時代から昭和に至る衣服や生活民具を3万点ほどコレクションされ、特に村人が纏っていた「ぼろ」と呼ばれる衣服や布は「BORO」と海外では称され、完成度の高いハイファッションとしても注目されました。
そんな、ぼろや民具の素晴らしさや、そこに込められた人々の思いをエッセイとしてまとめた良書です。ページをめくれば、ものや布には人のぬくもりがあり、やさしさがあり、物語があることに気づかされます。田中さんが残された、「本物のエコとは『人を愛する気持ち』」という言葉は奥深く、現在のSDGsに掲げられている目標やエシカル消費にもつながる思想だと思います。