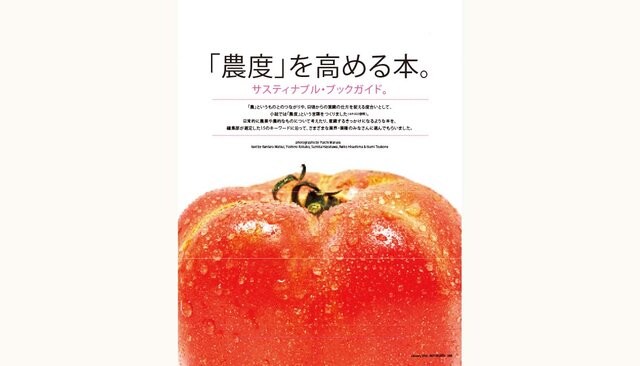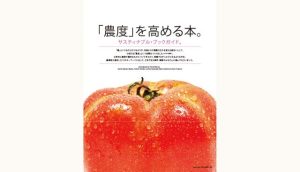『AGRIST』代表/『こゆ財団』代表理事|齋藤潤一さんが選ぶ、「農度」を高める本5冊
僕が代表を務めている『AGRIST』は、農業課題をAIやロボットで解決する事業を行っています。人口約1万6500人の宮崎県・新富町に拠点を置き、農家との勉強会を4年間続けたなかで、収穫の担い手不足という大きな課題があることに気づかされ、その解決のために農業ロボットの開発を始めました。
僕は農業を愛してやまないという人間ではありません。でも、新富町の農家と語り合ううちに、「この人たちの役に立ちたい」という思いが湧き上がり、僕の自己表現として農業ロボットの開発に打ち込んできたのです。ほかのメンバーも多様な背景を持っていますが、みんな「自分のために」というモチベーションで仕事に従事しています。主語は、あくまでも「わたし」。その結果、農業という一つの社会が変わっていけばと考えています。
社会課題が細分化され、農業もスマートフォンの数だけ、あり方や関わり方が存在する時代です。一人ひとりがそれぞれの方法で農業に関わり、その結果、社会を変えることになるという、そんな観点で編集された『これからの「社会の変え方」を、探しにいこう。』は、未来を考える農業者にぜひ読んでほしい本です。
農業のあり方や関わり方を探求することは、自分を知ることにもつながります。今、都市部では農家ではなく、農業ビジネスに携わりたいという若者が増えています。IT分野での能力を生かしてスマート農業に挑戦したり、新しい流通の方法を編み出したり。あるいは、デザイナーとして農業をデザインし直したり。それは、『Be Yourself』の副題にある「自分らしく輝いて人生を変える」ことになるし、そのためには自分がどういう人間か、自分を知ることから始めるのが重要になります。
主語がどんどん「わたし」に戻っていく今、農家としての自分を知り、自分らしく生き、働く。それが自分のウェルビーイングとなり、持続可能な社会の実現にもつながっていくのだと思います。