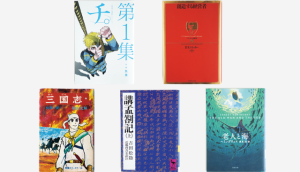海洋や漁業、川や水にまつわる、新しい言葉やマークがここ数年日本でも見聞きされるようになり、スーパーの鮮魚コーナーやファストフードのパッケージでも見かけるようになりました。「ん?このマークは?」と思うものもまだまだあるかもしれませんね。そんな新しいキーワードやマークをご紹介します。これがあると、お買い物の時から、海とSDGsの取り組みに自分ごととして関われる可能性が広がりますよ。
目次
【買い物】
環境に配慮して買い物をするには? 着目すべきポイントや、どんな工夫ができるかを紹介します。
食品ロス
まだ食べられるのに廃棄される食品のこと。日本の「食品ロス」は、推計で年間500万トン以上もあります。解決策としては、買い過ぎないようにする、外食の時に注文し過ぎないようにする、食事は残さずに食べ切る、スーパーや魚屋にある「見切り品」のお刺身や水産加工品から選んで買う、などといった方法があります。
未利用魚
サイズが不揃い、見た目が悪い、加工が大変、漁獲量が少なすぎる、特定の地域でしか獲れない、などといった理由から価値が付かず、市場にあまり出回らない魚のこと。味にはまったく問題なく、おいしく食べられます。近年、未利用魚を活用する動きが広まり、インターネット販売やスーパーで安く買えるようになってきています。
魚のサブスク
月1回や週1回といった形で魚を定期購入(サブスクリプション)する仕組み。サブスクを利用することで、漁業者は獲るべき量があらかじめ分かるので、漁獲量を調整でき、食品ロスを削減できます。未利用魚を使ったサブスクもあり、水産資源を無駄にせず、有効活用することに貢献できます。また、サブスク利用者には魚を日常的に食べる契機になるというメリットもあります。
トレーサビリティ
原材料の調達から生産、消費、廃棄までの追跡可能性。EUでは生態系への負担をかけていないか確認できることも大きな目的とされているように、消費者の安全を守るだけではなく、サスティナビリティの観点からもトレーサビリティは重要になってきています。
ウォーターフットプリント
食料品、衣類、化粧品などの製品やサービスについて、原材料の調達から生産、輸送、消費、廃棄、リサイクルまでのすべての過程で使われた水の総量や、水環境への影響を評価する概念。現在、多くの企業がウォーターフットプリントの算出に取り組んでいます。ウォーターフットプリントを意識することで、水環境への負担が少ない製品やサービスを選ぶことができます。
【ラベル】
スーパーやレストラン、ファストフード店で見るようになった水産物のラベルに込められた意味をお伝えします。
ISO
ISOはスイスのジュネーブに本部を置く非政府機関で、製品やマネジメントの方法について、国際的に通用する規格を制定しています。ISOの認証制度は、第三者が審査及び認証を行っており、規格を取得するにはISO認証機関に認められる必要があります。「ISO」が冒頭についた規格は5万以上ありますが、中でもISO14001(環境マネジメントシステム)は、環境に配慮した経営を行っていることの証明になります。
GSSI
政府やFAO(国際連合食糧農業機関)と民間企業が連携して設立した、持続可能な水産物を普及させるためのパートナーシップ。世界に数多くある水産物のエコラベルの認証制度を審査し、FAOの定める基準を満たしているか確認しています。2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、GSSIが調達方針に組み込まれました。
水産エコラベル認証
生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲・生産された水産物を、消費者が選んで購入できるように、商品にラベルを表示する仕組みのこと。商品にラベルを付けるには、漁業・養殖の事業者から、水産物の取引を行う卸売事業者、その先の加工・流通事業者、小売や外食の事業者まで、すべての関係者が認証を受けなければなりません。
MEL(メル)
2007年12月に日本で発足した、FAOによる水産エコラベルのガイドラインに沿った、持続可能な水産物の認証ラベル。目指しているのは、日本に多い中小規模の漁業者および加工業者も、経済的負担が低い形で認証を取得できる制度です。そのため、日本の水産業の特徴を反映した、日本で取得しやすい仕組みになっています。
MSC
「水産資源や環境に配慮し適切に管理された、サスティナブルな漁業で獲られた」と認められる天然の水産物につけられるラベル。MSC(海洋管理協議会)が管理、推進しています。認証には、第三者審査機関によって28分野に及ぶ89の得点項目に対する規格を満たすか審査を受けなければなりません。世界で広く認知されていて、日本を含む世界約100か国に広まっています。
ASC
第三者機関の厳しい審査で「水産資源や環境に配慮し、適切に管理されサスティナブルである」と認められた養殖場で育てられた水産物に付けられるラベル。複数の利害関係者の関与、透明性の確保、科学ベースのパフォーマンス指標を特色とする、国際社会環境認定表示連合(ISEAL)のガイドラインに従い策定されています。
【食卓】
豊かな海を守りながら、海の恵みをいただく。そのためにできる食事の工夫を紹介します。
サステナブル・シーフード
持続可能な漁業・養殖業で生産された水産物のこと。代表的なものには、持続可能な漁業で獲られた水産物の証であるMSC「海のエコラベル」や、環境や社会への影響を最小限に抑えた養殖場で育てられた水産物を示すASCのラベルが付いたシーフードがあります。買い物をする時にサステナブル・シーフードを選択肢の一つにすることで、海の資源を守ることに貢献できます。
アラスカ・シーフード
持続可能な漁業を進めてきた米国アラスカ州で獲られたシーフードのこと。アラスカ州では、天然資源の持続可能性を重視することが1959年に制定された州憲法にも明記されていて、長く実践されているため、サスティナブルな漁業のパイオニアと呼ばれています。魚では主にサーモンやタラが、日本のスーパーや生協でも販売されています。
シーガニズム
2016年から使われている、sea(海)とveganism(ヴィーガニズム)を組み合わせた新しい言葉で、植物性の食品に加えて、持続可能な方法で獲られた水産物を食べる食生活のことです。食事のバリエーションの広さや栄養バランスは保ちつつ、環境へ配慮した食生活が無理なく送れるため、少しずつ人気が高まりつつあります。
地産地消
「地元で生産されたものを、地元で消費する」という考え方や行動のこと。輸送にともなう環境への負荷を最小限にとどめられます。また、生産者が直接販売することにより、少量のもの、不揃い品や規格外品も販売可能となり、食品ロスが削減されます。さらに、地元の生産者を応援できるので、地域経済の活性化にもつながります。
友産友消
「友達がつくったものを、友達が消費する」という考え方と行動のこと。より身近な人の取り組みに触れることで、食や環境の問題を自分ごととして捉え直すことにつながります。「応援したい」という気持ちで、相手の笑顔を想像しながら買ったり、食べたり、使ったりするので心も満たされ、おいしさやうれしさが何十倍も大きくなります。
【養殖】
養殖には、主に2種類の方法があります。それぞれの具体的な内容と、メリット、デメリットをお伝えします。
海面養殖
海面で魚や海藻などを育て、獲ること。海の中に生簀を造り、その中で魚を養殖するのが一般的です。主なコストは餌代と稚魚代だけなので、ランニングコストを抑えることができます。ただ、自然災害や病気など外部からの影響を受けやすいので安定供給が難しいです。日本ではブリ、ハマチやマダイなどが多く養殖されています。
陸上養殖
陸上で、水槽を使って養殖する方法。海面養殖だと台風や赤潮などの自然災害や、寄生虫、感染症のリスクがありますが、陸上養殖ではそういったリスクを下げられるので、安定した生産量を見込めます。ただ、陸上養殖は水槽などの設備代、飼育する際の水の調達コストやポンプの電気代などのコストがかかるので、販売する時の値段を高めにする必要があります。
【漁業】
漁業のあり方は、海の持続可能性に大きな影響を与えます。どんな方法があるか見ていきましょう。
一本釣り
1本の釣り糸に1個、あるいは数個の釣り針を付けて、釣り竿で魚を釣り上げる漁法のこと。網の漁に比べて特定の魚種だけを取りやすいので、生態系に与える影響が少ないです。日本ではカツオやマグロ、イカなどの一本釣りが行われており、2021年には高知県や宮崎県の伝統漁法「カツオの一本釣り」が、MSC漁業認証を取得しました。
巻き網漁
カツオ、マグロ、サバ、アジやイワシのように大きな群れをつくって海の表面近くを回遊する魚をとる時に用いられる、漁の方法。垂直に垂らしたカーテン状の網で魚の群れを囲み、巾着のひもを締めるように網の底を閉じて、魚を獲ります。数隻の船が役割分担して行うことが多いですが、小さな漁船1隻で行う場合もあります。
底引き網漁
重いネットを海底に沈め、網の中に入ったものをすべてすくう、漁の方法。13世紀に始まったといわれ、18世紀後半から世界中の沿岸地域に広まりました。狙いは、海底付近に生息するタラやメバル、イカやエビなどですが、その他の魚類や海洋生物もすくってしまうので、生態系を傷つけると問題視されています。
違法・無報告・無規制(IUU)漁業
「違法」は、国家や漁業管理機関の許可なく、または国内法や国際法に違反して操業している漁業。「無報告」は、法令や規則に反した時の操業活動や漁獲量を報告しない、または事実と異なる報告をする漁業。「無規制」は、規制または海洋資源保全の国際法に従わずに操業すること。これらを総称してIUU漁業と呼び、国際的に対策が進められています。
乱獲
自然界の動植物を、むやみに大量捕獲すること。自然に増える速度を超えて過剰に獲り続けてしまうと、個体数が増えず、その動植物が絶滅に追い込まれる可能性が高まります。乱獲を加速させる大きな要因として過剰消費が挙げられます。例えば、消費者からの人気が高いマグロは大量に獲られており、世界的に対策が求められています。
漁業生産量
漁獲量と養殖による生産量の合計量のこと。FAOが2年おきに発行する『世界漁業・養殖業白書』の2020年版によると、2018年の時点での総漁業生産量は1億7900万トン。天然と養殖の漁獲量の比率はほぼ半々です。ただ、2030年には世界の総漁業生産量は2億400万トンに増え、養殖が約79パーセントを占めると予測されています。
TAC
TACとはTotal Allowable Catchの頭文字で、一定の海域における特定の水産資源の量を減少させないための、漁獲量の上限のことです。国連海洋法条約により、沿岸国はTACを定めなければなりません。日本では、魚種ごとの漁獲可能量や、都道府県別の漁獲枠などが、漁業者や水産庁などの関係者の議論を経て、決められています。
栽培漁業
卵から稚魚になるまでの時期を人の手で育てた後、自然の海に稚魚を放流し、成長したものを獲る漁業。養殖とは違い、自然界に放流するので、海の中の魚介類の数を減らさず、水産資源の増大・持続的な利用を促す効果があります。魚類では、マダイ、ヒラメ、サワラ、トラフグなどが、ほかにクルマエビやアワビなどが栽培漁業の代表的な対象になっています。
スマート水産業
ICT(情報通信技術)などの先端技術を活用することで、水産資源の持続的な利用と、水産業の持続的な成長の両立を実現することを目指す、次世代の水産業のこと。すでにスマートフォンによる7日先までの漁場予測情報の提供、養殖の際のAIによる最適な自動給餌システムの活用や餌の配合の算出などが行われています。
WCPFC
2004年に発効した条約により設立された地域漁業管理機関で、中西部太平洋の沿岸の国や地域が参加しています。目的は、中西部太平洋における、高度回遊性魚類(マグロ、カツオ、カジキ類)の長期的な保存と、持続可能な利用を確保することです。定期的に会合を開き、資源としてのマグロの管理について議論を行っています。
積立ぷらす
資源管理・漁場改善を促進しながら、漁業者の経営を支援する制度。燃料価格の上昇、漁獲量の低迷、災害などによって加入者の収入が減った際に、漁業共済では補償されない漁獲金額(生産金額)の減収が補填されます。積立ぷらすを利用するには、資源管理計画・漁場改善計画の設定、漁業共済への実質加入が条件になっています。
【廃棄物】
世界経済フォーラムの報告書によると、2050年には、魚より海洋ごみの量が多くなります。その原因とは?
マイクロプラスチック
大きさが5ミリメートル以下の小さなプラスチックごみのこと。まちでポイ捨てされた、ごみ捨て場で風に飛ばされたなどの原因で、プラスチックごみが用水路や川を通って海に流れ込み、日光や波、砂の力で細かくなり、マイクロプラスチックとして海にとどまります。プラスチックは細かくなっても自然分解せず、数百年間以上も自然界に残るため、海や生態系への影響が心配されています。
一次マイクロプラスチック
微小な状態で環境に直接放出されるプラスチックのこと。製品としては、歯磨き粉や洗顔料、化粧品に含まれるスクラブ剤のほか接着剤やインクなどに含まれています。また、洗濯で抜け落ち、下水を通り抜けて海に流れ込む化学繊維や、走行中の車のタイヤの摩耗で出るプラスチックも一次マイクロプラスチックです。
二次マイクロプラスチック
レジ袋やペットボトル、食品トレー、食品の袋やたばこのフィルターなどのプラスチックごみが、川を通って海に漂流したり、風にのって海岸に漂着したりしながら小さくなってできたマイクロプラスチックのこと。長い年月をかけて波の力で砕けたものや、日光(紫外線)による分解で小さくなったものがあります。
生分解性プラマーク
微生物によって水とCO²に分解されて、最終的には自然界へ循環していく性質を持つ「生分解性プラスチック」を使用した製品に表示することができる認証マークです。日本バイオプラスチック協会が認証しています。現在、マルチフィルム、獣害対策忌避ネットなどの農業・土木資材や、生ごみの収集袋、食品容器包装、ストロー、ティーパックなどが認証を受けています。
プラスチック資源循環戦略
廃プラスチック有効利用率の低さを背景に2019年に環境省が策定した、プラスチックの資源循環を総合的に推進するための戦略。「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rと、再生可能な資源への代替を意味するRenewable(リニューアブル)を基本原則にしています。2030年までに再生利用を倍増させるなど、具体的な数値目標も定められています。
プラスチックスマート
2018年に環境省が始めた、海洋プラスチック問題の解決に向け「賢くプラスチックを使おう」と呼びかけるキャンペーン。個人や自治体、NGO、企業、研究機関からプラスチックごみの排出抑制や分別回収の徹底の取り組みを募集し、集まった事例をウェブサイト上で国内外に発信しています。事例数は、2022年6月時点で約3000件もあります。
ビーチクリーン
海岸を清掃すること。行うには、一人から数人で好きなときにするほかに、各地で開催されているビーチクリーンのイベントに参加するといった方法があります。清掃を通して海洋ごみ問題について考えられるうえ、準備をほとんど必要としないので、SDGsに興味を持ち始めた人が、SDGsや海の問題について考える場としての意義も大きくなっています。
ビーチマネー
海に捨てられた瓶などが海岸に打ち上げられ、波によって角が削られ丸みを帯びたガラス片(ビーチグラス)を、地域通貨として使う活動。2007年に神奈川県の湘南で、ビーチクリーンで拾ったビーチグラスを地域通貨の代わりにしたのが始まりで、現在は国内外の200以上の協力店舗でビーチマネーを使えます。海岸でのごみ拾い中に見つけたものなら、世界のどこで拾ったものでもOKです。
【エネルギー】
私たちが生きるうえで必須となるエネルギー。環境に負担をかけない仕組みや技術が生まれてきています。
水産バイオマス
海藻や漁業系廃棄物などの、バイオマスエネルギーとなる海産物のこと。現在、微生物の力でこれらのバイオマスをメタンやエタノールに変換させ、エネルギーに変える研究が盛んに行われています。実用化されると、豊かな海を維持しながらエネルギーが得られます。また、増えすぎた海藻を捨てずに有効活用することができます。
FIP
生可能エネルギーの発電事業者が、卸市場などで売電した時に、その売電価格に対して一定の金額のプレミアム(補助額)が上乗せして支払われるという制度です。すでに欧州ではかなり普及しており、日本では2022年4月から始まりました。この制度により、再生可能エネルギーの導入がさらに進むと期待されています。
OTEC
海水の温度差を利用して発電するシステムのこと。太陽からの熱エネルギーで温められた表層の海水の熱を使って、液体のアンモニアや代替フロンなどを加熱、蒸発させ、その蒸気でタービンを回して発電します。タービンを出た蒸気は深層海水の低温で液化され、その後、再び蒸発させ発電するという循環を繰り返します。まだ実証実験が行われている段階ですが、クリーンで安定したエネルギー源になるので、実用化が待たれています。
【海の生物の問題】
今、海ではどんな問題が起こっているのでしょうか? 考えていくうえで基礎となる知識を解説します。
生物多様性
生物の種間および種内にさまざまな差異が存在していること。「生態系」、「種」、「遺伝子」の3つのレベルで多様性を指しています。生物多様性は地球上の生態系や水循環などの安定性と強く結びついているので、生物多様性が失われていくと、食料や災害抑止力の減少、気候変動の加速、感染症リスクの高まりなどが起きます。
富栄養化
生活排水や工業排水が海や川に流れ込み、水中の栄養素が過剰に増えることで起こる水質汚染のこと。富栄養化が進むとプランクトンが大量発生し、水中の酸素が不足します。これにより生き物に酸素がいきわたらず、大量に死んでしまいます。赤潮、青潮、アオコは富栄養化により起こる現象です。世界中で対策が急がれています。
海洋酸性化
大気中のCO²が増え、それが海にも溶け込み、海水が酸性化すること。カニやエビなどの甲殻類、ホタテやカキなどの貝類やサンゴは、骨や殻が酸性の液体に溶ける性質を持っています。そのため、海洋酸性化が進むと成長や繁殖が難しくなります。食物連鎖でつながっているほかの海洋生物にも影響するので、生態系に広く被害が出ます。
レジームシフト
気温や風、水産資源の分布・生息数などが数十年規模で変動すること。例えば北太平洋では海水温が数十年規模で変化しており、日本では、水温が高い温暖レジームの時はカタクチイワシやスルメイカ、寒冷レジームの時はマイワシやスケトウダラがより多く獲れる傾向にあります。この概念を用いた水産資源の適切な管理を図る動きもあります。
磯焼け
海水温の上昇や海水の汚染、ウニの食害などが原因で海の沿岸の磯の藻類が枯れて、焼け野原のような状態になる現象。磯焼けが起こると、磯を生活の場とするコンブ、ワカメなどの海草や、アワビ、サンマなどの魚介類が獲れなくなります。しかも回復に10年以上かかることも多いので、漁業や水産資源の保護に深刻な影響を及ぼします。
レッドリスト
国際自然保護連合(IUCN)が作成した、絶滅の恐れのある野生生物のリストで、現在4万種以上が登録されています。海の生物では、例えばサメ・エイ類の約4割、造礁サンゴ類の約3割が絶滅危惧種です。なお、日本に生息・生育する野生生物を対象として作られた、国内版の「環境省版レッドリスト」もあります。
【問題解決のアクション】
近年、海の問題が広く知られるようになりました。それに伴い、世界各地でさまざまな解決策が実施されています。
ブルーカーボン
海洋生物の作用によって大気中から海中へ吸収・蓄積された炭素のこと。マングローブ林や海藻、サンゴ礁などはCO²を吸収し、長期にわたり貯留します。こうした働きが温室効果ガス対策として国内外で注目されています。国内では、農林水産省によるブルーカーボンの評価手法や効率的な藻場形成・拡大技術の開発プロジェクトが進められています。
ブルーツーリズム
海の近くにある地域や島に滞在し、そこでの生活体験を介して心身の休養を取る、海辺に特化したエコツーリズムのあり方。例えば、漁業や養殖の体験、海沿いでのトレッキングやサイクリングなどさまざまな体験メニューを自ら選択し、オリジナルのツーリズムをつくり上げていけます。日本では、国土交通省や水産庁などが推進しています。
ブルーフラッグ
海辺がきれいで安全で、誰もが楽しめる場所であることを認める国際認証制度。1985年にフランスで誕生し、日本を含む世界48か国、5000か所以上のビーチやマリーナが取得しています(2022年5月時点)。取得には合計30項目以上の認証基準を達成しなければなりません。また、取得後も毎年審査を受ける必要があるため、サスティナブルな活動の継続が促進されます。
世界海洋デー
2008年に、国連によって制定された国際デーです。毎年6月8日に「私たちの海をきれいに」「ジェンダーと海」といったテーマが定められ、この日の前後には、海に感謝したり、海の問題を考えたり、アクションを起こしたりするためのイベントが世界中で行われます。オンラインやSNSで参加できる取り組みも、たくさんあります。
【海に関する法律・国際機関】
海の豊かさを守るカギとなる法律と、地球規模で海の問題解決に取り組んでいる国際機関を紹介します。
改正漁業法
近年の日本の漁業を巡る変化に対応するために、70年ぶりに改正され、2020年に施行された法律。獲り過ぎや気候変動による漁獲量の低下を止め、持続可能な形で水産資源を利用し、国内漁業の生産力を高めることを目的としています。「持続可能な利用」という言葉が明記され、その実現のために、今まで行われてきた漁具、漁法の規制に代わり、魚種ごとの漁獲量の割り当てや、TAC(漁獲可能量)により、漁獲量そのものを規制する管理法へ移行をうたっています。
水産流通適正化法
日本で獲ったアワビとナマコについて、採捕事業者や取扱事業者が16桁の番号を付けること、取引記録を作成・保存することなどを義務づける法律。近年、全国的にアワビ・ナマコの違法漁法が悪質、巧妙になってきているので、その対策として2022年12月から施行されることになりました。2025年にはシラスウナギも対象になります。
FAO
世界の農林水産業の発展と農村開発に取り組む、国連の専門機関。FAOが2年ごとに発表している『世界漁業・養殖業白書』を読むと、世界の魚の消費状況、漁獲や生産がどのように行われているか、水産資源の現状などがよく分かります。また、FAOはエコラベルや漁業認証の仕組みに関する国際的な技術ガイドラインを策定しています。
UNEP
世界各国の環境問題に関する活動の全般的な調整を行うとともに、新たな環境問題に対する取り組みを推進することを目的とした、国連の専門機関。幅広い問題に対処していますが、海に関しては「ブルーカーボン」を提唱したり、「地域海計画」のもと、140か国以上の海洋・沿岸地域の環境問題への取り組みなどを行っています。
text by Miho Soga illustrations by Yu Tokumaru
記事は雑誌ソトコト2022年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。