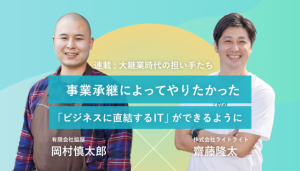経営やマーケティング、デジタル活用など事業の中核を担う人材がほしいと考えている企業と、「地域」に魅力や可能性を感じている都市部の人材をマッチングさせる中小企業庁による事業が、2022年度と23年度、香川県の高松市と琴平町で行われた。
キーワードは「複業」と「地域内の支援ネットワークの形成」。兼業や複業を前提とした求人のスタイルに、地域の企業も応募した人たちも手応えを感じている。
大切なのは信頼と共感。
地方に限らず、人材不足に悩む中小企業は多い。「こんなスキルのある人材がほしい」と明確な企業もあれば、「一緒に新しい仕事を開拓したい」という企業もあるだろう。しかし、正社員の採用は人件費の面でハードルが高く、また地方では人材が見つけにくい現状もある。
そこで、地方に興味関心を寄せていて複業ができる都市部の人材を募集・マッチングして、地域の中小企業のスキルアップや成長につなげようというのが中小企業庁が主導する「地域中小企業人材確保支援等事業(中核人材確保支援能力向上事業)」だ。
この実証機関に2023年度、人材派遣のリーディングカンパニー・『パソナグループ』の一員で、香川県琴平町で地域づくりに関わる『株式会社地方創生』が採択され、人材マッチングのノウハウを持つ『パソナJOB HUB』と協力し実施された。


「20年から22年にかけてはコロナ禍で、観光地の琴平町は大きな打撃を受けていました。なんとか外から人を呼び込みたい、そんな気持ちもあり、今回の事業に手を挙げました」と『地方創生』代表取締役社長の近江淳さんは語る。
事業に協力した『琴平町商工会』経営指導員の住谷健治さんは、当時、琴平町の企業が置かれていた状況をこう語る。
「人口減、高齢化、コロナ禍などで、会員企業の多くが人手不足でした。特に新規事業を起こしたい、デジタル化に対応したいと思っても人材が少ないので、ノウハウを持つ人が来てほしいという企業は多いと感じました。ただ、当時は本当にいい人が来てくれるのかという不安と、でもチャンレンジしなければ変わらないという両方の思いがありました」
そこで住谷さんと『地方創生』のメンバーらは企業に足を運んで経営課題をヒアリングし、「複業」での取り組みを前向きに捉え、関わることができそうな企業に声をかけた。また高松市でも参加企業を募集。人材を募集した企業は延べ20社(2022年度、23年度の合算)となった。

次に『パソナJOB HUB』を通じて本事業を周知し、応募があった人たちに向けてオンラインによる企業の説明会「顔合わせイベント」を実施。その後、琴平町と高松市に来てもらい、企業の経営者と交流できるフィールドワークを実施した。
「この事業を進める中でもっとも重視したのは共感と信頼です。応募者のスキルだけでなく、経営者のミッションや思いに共感してくれた人と仕事をしたいと考える企業は多いですし、私たちもその部分を大切にしてマッチングしたいと考えました。なので“顔が見える”コミュニケーションを大切にしました」と、事業の運営に携わった『地方創生』の山川宰さんは語る。
さらにフィールドワークの後、応募者は企業でどんなことをやりたいのか、提案書を提出。それを元に面談を行ったうえで、採用するかどうかが決まる。
「時間も手間もかかりますが、フィールドワークや面談でお互いの考えや求めていることがわかってきます。また複業という働き方についてのイメージもすり合わせることができるので、これは欠かせないステップだと思います」と山川さん。

今回の事業に参加した企業のいくつかを紹介。参加企業の一つ『株式会社森と山』が金刀比羅宮の参道で運営する犬の一時預かり所『ゲンのいえ』、ドッグフードやドッググッズを販売する『ゲンのみせ』、『cafe森と山』。左上/1Fにカフェ・ギャラリー『Sando Sand. Stand』が入る『HAKOBUNEビル』を運営している『株式会社栞や』も琴平町からの参加企業の一つ。左下/高松市内の参加企業『ペダル株式会社』の拠点であり、1Fにライフスタイルも提案するサイクルショップが入る『田町クラウズ』。
SNSの運用にスペシャリストの力を借りて、サービスを浸透。〜『琴平バス』の場合〜
琴平町に本社がある『琴平バス株式会社』は、バスやタクシー、観光、宿泊業などに携わり、客層は国内外に広がっている。同社は22年度の事業に参加した。代表取締役の楠木泰二朗さんは、募集をかけた理由をこう語る。
「琴平町は古くから観光業が盛んだったが故に、なかなか新しいことに取り組めていません。観光客が少しずつ戻ってきていますが、さらに発展するためには外からの視点が必要だと思います。こうした応募をきっかけに、都市部の人が琴平町に目を向けてくれることに意味があると思いました」
コロナ禍を経て、会社としてもさまざまな働き方に対応しなければと思っていが、ではどうやるのか、そのノウハウはなかった。この事業は新しい働き方を試す機会にもなったという。

『琴平バス』で採用されたのは、フリーランスとして広報やマーケティングのスキルを活かし、いろいろな地域で仕事をしている内山学さん。会社全体のSNS運用の見直しや、SNSを活用した相乗り型の新しい移動サービス『琴平mobi(モビ)』への加入促進に6か月間取り組んだ。
この6か月間で、それまで担当者ごとに感覚で行っていたSNSの運用方法を整理し、より効果的に情報を発信できるようになった。楠木さんは「mobiのユーザーを広げることもできました」と新しい人と一緒に仕事をする効果を実感している。
内山さんは今回、『琴平バス』以外にも2社と契約し、それぞれにオンラインで仕事を行った。
「元々旅行が好きなのですが、旅行よりももう一歩踏み込んで地域で何かできたらと思っていました。いろいろ経験してきましたが地域での仕事の魅力は『人』にあると思います。斬新な発想で事業を行う地域の経営者と出会えることは、都市部ではなかなかありません。そんな企業に自分のノウハウやスキルが役にたつところにやりがいを感じます」

今回の事業をきっかけに正社員として勤務。〜『瀬戸内サニー』の場合〜
2年続けて人材を募集したのは、高松市の教育系スタートアップ企業『瀬戸内サニー株式会社』だ。「瀬戸内からおもしろくしたい」と、Youtubeの発信や発信者の育成、地域発のコンテンツ作成、企業や学校などで研修なども行っている。
そもそも『瀬戸内サニー』は、フルフレックスでコアタイムもなし。組織もフラットで、全スタッフが集まるのは週に1回という会社。複業人材を活用することへの抵抗感は少なかったが、こんな人がほしいと具体的イメージがあったわけではなかった、とCEO兼YouTuberの大崎龍史さんは語る。
「最初は、『琴平バス』の楠木さんから誘われて参加した、というのが正直なところです。オンライン説明会では、『何をしてほしい』ではなく弊社の理念やこれから教育分野に事業を全振りしていきたいという話をしました。そこに共感できる人に応募してほしかったので」


そんな大崎さんの言葉に動かされたのが、岡山市で広報・マーケティングをフリーランスで行っていた小池香苗さんだ。小池さんの提案書には、『瀬戸内サニー』に魅力を感じ、一緒に働きたいという熱い思いが綴られていて、それが大崎さんに響いた。
「話をするうちに小池さんがとてもコミュニケーション能力が高いことがわかり、提案型の営業の仕事を任せられるのではと思いました」
小池さんも「一緒に考えて私に合う仕事を考えてもらいました。そういうスタイルの方が、確実に仕事のパフォーマンスが上がる」と感じている。実際、小池さんの提案で企業に動画作成のノウハウを教えるという新しいビジネスが立ち上がった。現在、小池さんはフリーランスの仕事を続けながら、『瀬戸内サニー』で正社員として週4日勤務している。

複業マッチングで『瀬戸内サニー』で働き、今は正社員として関わっている小池香苗さん。「今回の募集が、副業ではなく『複業』だったところがいいなと思いました。また、教育系の仕事は私も興味がある分野でしたので、これから教育系の事業を展開したいという『瀬戸内サニー』の思いを聞いて、ぜひ私も一緒に加われたらと思いました」。

地域が必要とする複業人材のマッチングの仕組みの構築を目指す。
2年間の事業で、複業人材と企業のマッチング件数は延べ46件。参加した地域側のプレイヤーには、こうした人材マッチングで、地域に新しい風が吹くのではないかという手応えも生まれた。
『琴平町商工会』の住谷さんは「最初はどんな成果が生まれるかイメージが湧かなかったのですが、2年を経ていい成功事例が生まれ、複業人材の必要性を企業に説明しやすくなりました。企業側も、こんな人材が応募してくれるのか、と具体的なイメージが掴めたと思います」
『地方創生』で事業の運営に携わった岩田愛菜さんは、複業人材の活用は地域の企業の武器になると感じたと話す。
「今回の事業で企業の意識も変わったと思います。自社の弱いところに力を貸してくれる人材を採用することで、企業が次に進むステップアップにつながると思います」
23年度を終え、一旦本事業は終了となるが、同社の近江さんもこの仕組みの必要性を実感している。
「地方の企業の経営課題解決に向けて人材とのマッチングを促し、企業が成長を続けることをサポートする仕組みは、地域が活性化するために必要なものだと思っています。中小企業庁の最終的な目的は、事業終了後も人材マッチングを自走させ、支援体制を継続させること。その目標に向かって、よりよい仕組みをつくっていきたいと考えています。目指すのは『地域の人事部』です」
———-
photographs by You Sakana
text by Reiko Hisashima