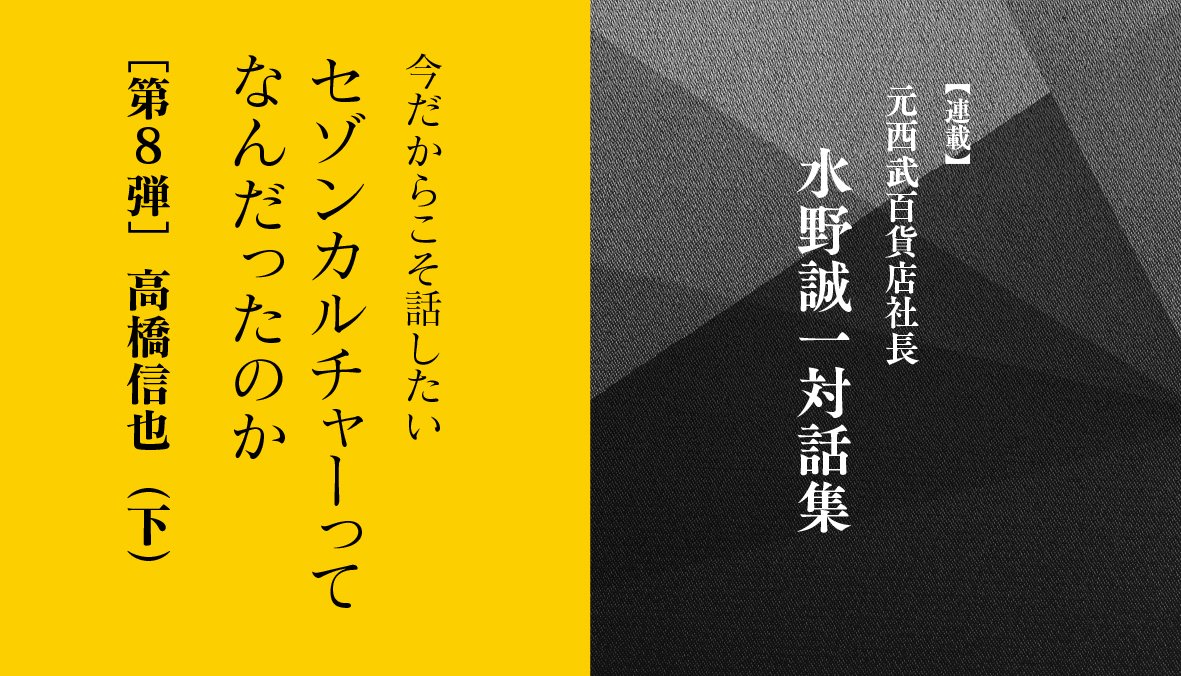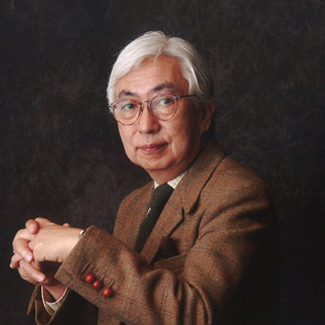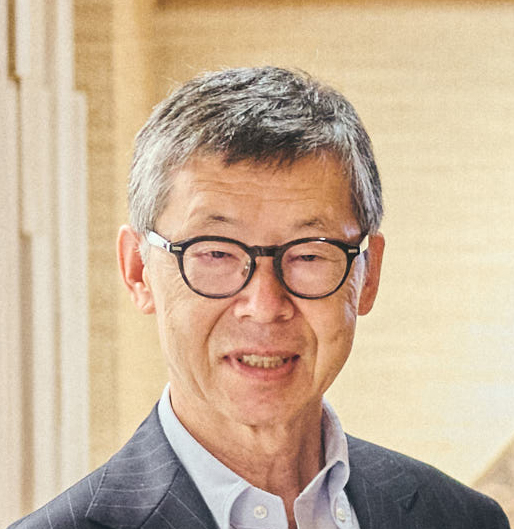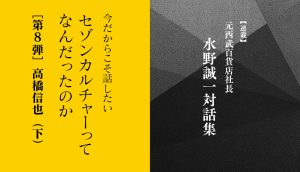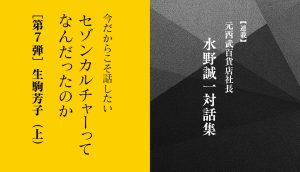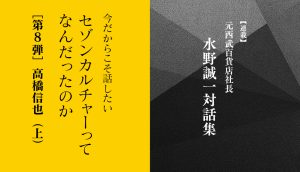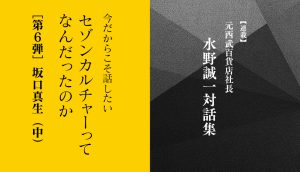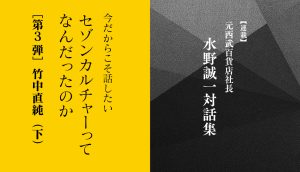西武美術館の洋書店・アールヴィヴァンがなくなっても、そのままアートの世界に生き続けた高橋信也は、その後、森ビル・森美術館にも関わり、90年代に村上隆、奈良美智をグローバルに紹介することになる。西武百貨店の社長を退任後、森ビルの特別顧問になった水野誠一との対談は、より深いアートの世界的背景と、アートを体現したとも言える堤清二の想いへと迫る。

村上隆、奈良美智。日本人が世界で認められた背景
水野 高橋さんは村上隆や奈良美智を世界に打ち出していった。
そのなかで、セゾンが元気だったときのようなやり方や思いというものは多少ありましたか?。
高橋 もちろん、僕はセゾンにいましたので、身についたものはあります。
ただ、村上隆、奈良美智、杉本博司といった日本人が海外で受け入れられるために何が必要だったかというと、彼らの力もさりながら、海外のアートの状況がぐちゃぐちゃになっていたということが功を奏した気がします。
日本ではバブルの崩壊が文化にとって大きな打撃でしたが、海外では東西崩壊だったわけです。湾岸戦争のあと、ベルリンの壁が崩壊し、ソ連が解体した。もう国境・言語・宗教・人種がぐちゃぐちゃになって、ヨーロッパ全土に入り混じっていった。
そこで、アートの拠点としてのパリやニューヨークがもう維持できなくなった。ポンピドゥー・センター(Centre Pompidou)みたいな西洋美術の牙城が「大地の魔術師」というアートじゃないもの、アートの概念から外れる民族的な表現の展示をやったりするようになった。
じゃあ西洋がどう再生するのか、躍起になり始めていたとき、日本では横浜トリエンナーレが有名ですが「いろんな国のいろんな文化の人間が集まってこれからどうするかを考える展覧会」というのが、 90年代の後半に流行ったんですよ。
それだって英語、中国語、フランス語、アフリカ語の人がいたらもう美意識が 一本化できっこないじゃないですか?言葉を乗り越え、感性を乗りこえることからしか始まれない。
だからそこへ、日本も参画できたんですよ。その時、それが村上さんだったり、奈良さんだったり、杉本さんだったりした。
つまりそれまでは、なかなかガードが固かった。そのガードが壊れ,考え方が変わったことで、むしろ前向きに参入できた。それが 90年代だったと思います。
水野 なるほど、なんとなく体感として分かりますね。
高橋 90年代は、マルチ・カルチュラリズムとか、カルチュラル・スタディーズという哲学の流れがあって、どこの国の文化も等しく大事ですね、という観点があった。
その考えをもとになんとなくまとまって、 20世紀を越したという感じです。
それで21世紀になってからは、ある枠組みがもうできていたり、コンテクストができているから、なかなか入れてもらいにくいんですね。
そういう点では、やっぱり村上や奈良は幸運なタイミングだったと思います。
水野 思えば、三宅さんや山本さんがパリへ出て行ったあの時も、ファッション界でもある意味、パリの限界が来ていた時期かもしれませんね。変化が欲しかった。そこに受け入れられたっていうのがあったわけです。
だけど、やっぱりそういうタイミングを見出す力というのは、まあセゾンがロシア・アバンギャルドをやってみたというようなことにつながりますよ。
高橋 しかし、こういう言い方は失礼かもしれないけど、セゾンがというより、やっぱりその堤清二氏の見極めによって立つところだったと思いますね。
その点では、私の周りにも、その堤さんについて行きたいがために、セゾンに入社したと言ってる人もたくさんいました。そのセゾン文化の中で、それに従事させてもらってることは、ハッピーだと思っている社員もたくさんいたように思いますね。

堤清二は経営者であり詩人だった
水野 今はまた難しい時代ですね。20世紀的な価値観が、21世紀に入って大きく変容しています。その最たるものは、土地とか金といった物質的な資産の価値が薄れてきているということです。西洋占星術ではこれから200年は「風の時代」に入ると言われているらしくて、これは地球の歴史的に見ると縄文時代ぐらいまで遡るぐらいの、価値観の転換が出てくるらしい。
つまり、金を持ってるとか不動産を持ってるというより、アートという一番不確かなものが重要な意味を持っていくんじゃないかと。
だからこういうときに、セゾンがやろうとしていた文化体験というものも求められているんじゃないかと思ったりします。時代がそういうものを求め始めてるんじゃないかという感じがするんですよ。
非常に難しい時代だけど、日本人は昔から花鳥風月を愛でるとか、もう既に富や物質ではない概念が存在していたじゃないですか。
高橋 今、水野さんがおっしゃったことに近いことを、堤さんも書かれています。
堤さんご自身の言葉で。
「70年代に私達は、成熟することによって同時に大きな変革を内包せざるを得なかった、いくつもの流れを看取しています。そうであるから、多様なままにそれを受け容れることが、そのまま拠点としての資格になるのだと思います。その意味では明確な主張や、古典的な特定の主義に立たないことが美術館にとって必要であるに違いありません。
言いかえれば、美術館それ自体が、たとえば砂丘を覆う砂や、極地の荒野の上に拡がる雲海のように、たえまなく変化し、形を変え、吹き抜けた強い風の紋を残し、たなびき、足跡を打ち消していく新しい歩行者によって、再び新しい足跡がしるされるような場所であって欲しいと考えています。」
水野 わかっていたんですね。
高橋 しかしこれ、詩人が言っているならわかりますけど、経営者の言葉ですよ。
水野 世の中の堤清二の評価として「彼は、辻井喬だったのか。堤清二だったのか」というっていうのがある。ある意味においては、都合よく彼は使い分けたと言われているんだけど。そうじゃなくて、彼は2つのキャラクターを同時に持っていたという気がするんです。世の中の理解を超えた存在であったということだったと思うんですよ。「堤清二ってって面白いね」という人のなかでも、その本質を理解して面白いと言っている人は、ほとんどいなかった。
だから「水野さん、ああいう人と付き合うって大変ですね」と言われたけど、そんなことはなかった。
僕は非常に彼と同質的なところがあったから、彼が何を考えてるのかよく分かりました。
つまり人間の幸福や平和を求めていったときに、右からのアプローチもあれば、左からのアプローチもある。でもそこにこだわらないことが重要なんです。
例えば共産主義というのは”はしか”のようなもので、一度は学んでみる必要があるけれども、いつまでも”はしか”じゃ困る。人間は成長していくんだから、そんなの当たり前だ。いい加減だと言われちゃ困るんだと。
僕は理解できますけど、そういう自己矛盾の中に彼の発想原点がある。
高橋 僕は今の時代、少なくも 90年代以降を堤さんはどう考えられるだろうと、本当に聞きたいですね。
水野 聞きたいと思うのは、実は想像がつくからなんだよ。
確かに、強欲資本主義の崩壊後をどう捕えているんだろうと、本当に聞きたいですね。

森ビルの森さんは堤さんを気にしていた
水野 高橋さんは、その後、森美術館にも関わりましたね。
高橋 はい。僕は森美術館の時に二度、堤さんに講演をお聞きしました。1回は美術館でお願いして、講演をしていただいた。その後、堤さんの方から「中国の近代化について講演をするから聞きに来ないか」とお声掛けをいただき、その後、森ビルの森稔会長が一緒に食事をしたいと言った時に、お声を掛けさせていただきました。
秘書と車で来られるんだろうと思っていたら、おひとりで歩いてこられて、びっくり仰天したことがありましたけど。なんとなく糸口を作って、これからのことを聞くところまで持ち込みたかったんですけど、残念ながら、そこまでいかなかった。
水野 森さんというのも、なかなかユニークな人でしたからね。とても単純な人なんですけど。堤清二の複雑性からいくと、 10分の 1ぐらいシンプル。でも純粋な心の持ち主でしたね。
高橋 すごく純粋な方なんですよ。
水野 やっぱり人間の幸せとは何なんだろうと、深く考えてしまう人で。
高橋 講演の後に「お前、すぐメシをセットしろ」って言われて。社内で、なんでもっと早く持ってこないんだと、怒られたぐらいでしたね。
水野 僕は森さんにもね、ずいぶん「堤さんってどういう人だったか」と聞かれました。そもそも森さんとの付き合いは、戌年会という宴会からでした。
森さんは僕よりひと回り上の戌年なんですよ。僕は昭和21年(1946年)だから、森さんは昭和 9年(1934年)か。それに昭和33年(1958年)の人たちと 三世代の戌年の財界人が集まる会でした。
新橋の料亭で、これほど盛り上がらないカラオケ大会というのもないんだけどね(笑)。
1人だけ出て順番に歌っていくわけ。そして、森さんの番になった。森さん、どうするんだろうなと思っていたら、案の定「僕は歌は苦手なんでお話をします」と言って。
「これからの街というのは、垂直の森を作るべきです」と。つまり高層ビルがあって、そこ自体にも草木を生やすっていう発想があってもいい。余った土地に緑を作ればいいという発想で、これがこれからの都心づくりだということを、延々と話されるんだけど、、誰も聞いちゃいない。
僕は森さんの真正面にいたので、じっと聞いていたわけです。ずっと。
この人は相当空気を読まないけど、でも素晴らしい人だな、と。
すると、その翌週ぐらいに、森さんが僕の事務所にいらして「六本木ヒルズを作ります。その前にアークヒルズをもう 一度建て直したいので、西武にいる役員、あるいはOBでどなたか、森ビルに来てくれる人はいませんか」と、相談に来られたんです。
「残念ながら、僕がもう辞めたぐらいですから、西武にはいないです」と答えて、他社の友人を推薦したんですが。
そういう話のときにも「堤さんって、どんな人ですか」と、盛んに聞かれましたね。
高橋 学びたいことがいっぱいあったのでしょうね。
水野 森さんは志半ばで亡くなってしまいましたね。僕は彼には長生きしてほしかったな。
高橋 本当です。まだ70代でしたからね。
水野 堤清二と25年間付き合って、森さんとも 11、 2年付き合って。堤清二の次は森さんに文化的な経営者として成功していただくことが大事だなと思ってた。
性格も文化的な背景も違うけれど、絶対面白い化学反応が起こりうると思いました。
森美術館を作ったことは、偉業だったなと思いますね。
高橋 そうですね。その時も「堤さんだったらどうするか」と、彼は相当意識していましたね。
水野 残念なことでした。
日本の美術館の悲しい現状
高橋 今、僕は文化行政の立場も半分あるんですが。
美術とか表現の業界の側から見ると、実は日本の文化行政が貧しい為に、時代時代にその時代のパトロネージュをしてくれる人がいるんですね。
例えば、 50年代 60年代は草月流の勅使河原蒼風さんや宏さんのように。
音楽ではサントリーの佐治敬三さんがおられたり、資生堂の福原さんおられたり。
70年代ぐらい入って堤さんがおられて、 90年代に入って森さんがいてというふうに。
本来、文化行政が担うべきことを、パトロンとして経済文化人が担ってきました。
日本の文化状況は、こうしてできてきたんだと思うんですよ
水野 世界的にそうでしょう。
高橋 ご承知のようにニューヨークのニューヨーク近代美術館(MoMA)は私立の美術館です。ロックフェラーの奥様たちが進められた美術館だし、英米の美術館は、実はお金を集めるのが得意なプライベート・ミュージアムです。ヨーロッパの大きな美術館は、どちらかというと国家から資金が出ているから、国営が多いんです。
そう考えると、日本は欧米の美術館を真似したとも言えるんだけど、真似せざるを得なかったとも言える。
しかし、結局はお金持ちに取りすがって、なんとなく経営を、成立させてきたんですかね。
水野 でもね、日本の寄付というのは税制が悪いんで、寄付する人が少ないんです。
だから、それこそ日本の美術館に寄付として入ってくる収入は、欧米の美術館の10分の 1ぐらいじゃないかな。
高橋 国立美術館なんかでも、結局は今、国がどんどん面倒を見なくなっていきそうで。大学もそうですが、自立しろと。
それでもう、お金がなくて大変です。本当に展覧会ができなくなってしまう。
水野 高橋さんは、今、具体的にはどんな仕事をしているの?。
高橋 私は今、企業としてはNADiffの専務っていう立場ですが、京都市京セラ美術館リニューアルのゼネラル・マネージャーをしていました。4月から京都市の文化担当参事で、エクゼクティブ・アドバイザーです。
個人的には、1980年代以降の東京のアートシーンをクロニクルとしてまとめた書籍を執筆中です。
水野 それは楽しみだね。同じころに僕の本も出せるかな。
丁度僕が西武百貨店を退職してから30年が経ったんですよ。西武に在籍していたのが26年間だったから、最早それを超えた。そこで人生を振り返ってみたくなった。
しかしどんな本にしようか悩んでます。主だったテーマは、今振り返って見てセゾン文化とはなんだったのか?なんだけど、このテーマでは既に色々と書籍が出版されている。
西武を辞めた後、参議院議員をしていた時代に、朝日新聞から声が掛かって、渡辺守章(東大名誉教授)さんと対談をしたことがあり、そこでは、企業文化を作るのには数十年かかるけど、壊すのは一瞬という話が出ました。セゾン文化も一旦幕引きになったけど、その種が残ってさえいれば、数十年後かもしれないが、必ず新たな芽吹きが始まると話したんだけど、残念ながらその部分は掲載されなかった。
でも今、セゾン外の様々な所で次第に現実化し始めているじゃない?西洋占星術で言うところの、19世紀から20世紀にかけての「土の時代」の経済主義的巨額の富の上ではなくて、21世紀から始まる「風の時代」の小さな精神的豊かさの上にではあるけれど・・僕はそれに賭けたいと思っているんですよね。
残念なことに、堤さんも芦野くんも他界してしまったけど、セゾン文化の原点とは言わないまでも、せめてアールヴィヴァンの原点に立ち戻って、われわれ二人で何か面白いことをやりましょう。
撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph
構成:森綾 http://moriaya.jp/