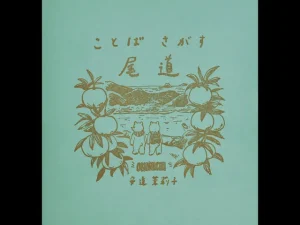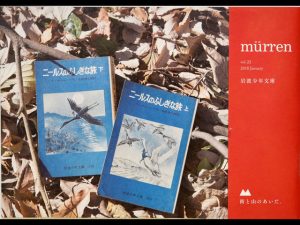鍾乳洞で雫が鉄琴を打つ音。意外なことかもしれないが水そのものに音はない。雨音も川のせせらぎも水の粒が何かにぶつかって音をたてているのだ。
打楽器奏者・松本一哉はさまざまな「音」を音楽に仕立ててゆく、ある意味、音楽の本質に迫るアーティストだ。十和田湖など厳冬期の凍結した湖や知床半島でオホーツク海の流氷に録音機材を立ててレコーディングしつつ、全国56か所を巡回し、どんな小さな会場でも渾身の演奏を聴かせている。
昨年末にはそのドキュメンタリーを『鐵冴ゆる』としてリリースした。水滴の落ちる音、銅鑼をなぞる倍音、シンギングボウル、波紋音など「音具」を取り巻く音すべてを魔法のようなリズムに組み替えていく。このスタイルでの演奏は、原理的に考えて同じ演奏は二度と存在しない。
彼の作品からは、音楽を通してその土地の繊細な何かにつながろうとしていることがよくわかる。そこから想起するのはブライアン・イーノやクリス・ワトソンといったアンビエントやフィールドレコーディングの先駆者たちの系譜よりも、宗祇、心敬といった連歌師たちのような、連綿と続く土地の繊細な何かと、自然の生命力のつながりをつかみ取ろうとしていた先人たちの姿だ。21世紀の日本にまだ現れていない何かを目指す姿に見えて仕方がないのだ。そしてそれは、おそらく古い時代から伝わるさまざまな「藝能」にひそむ秘密と関係している。
彼の演奏がほかと違うのは「楽器」たちが舞台を飛び出して、水のように散らばってゆくことだ。その姿が、彼の音楽の広がりそのものであり、音楽シーンを取り巻くさまざまな限界やさらに音楽そのものを超えていこうとすることにつながっている気がしてならない。