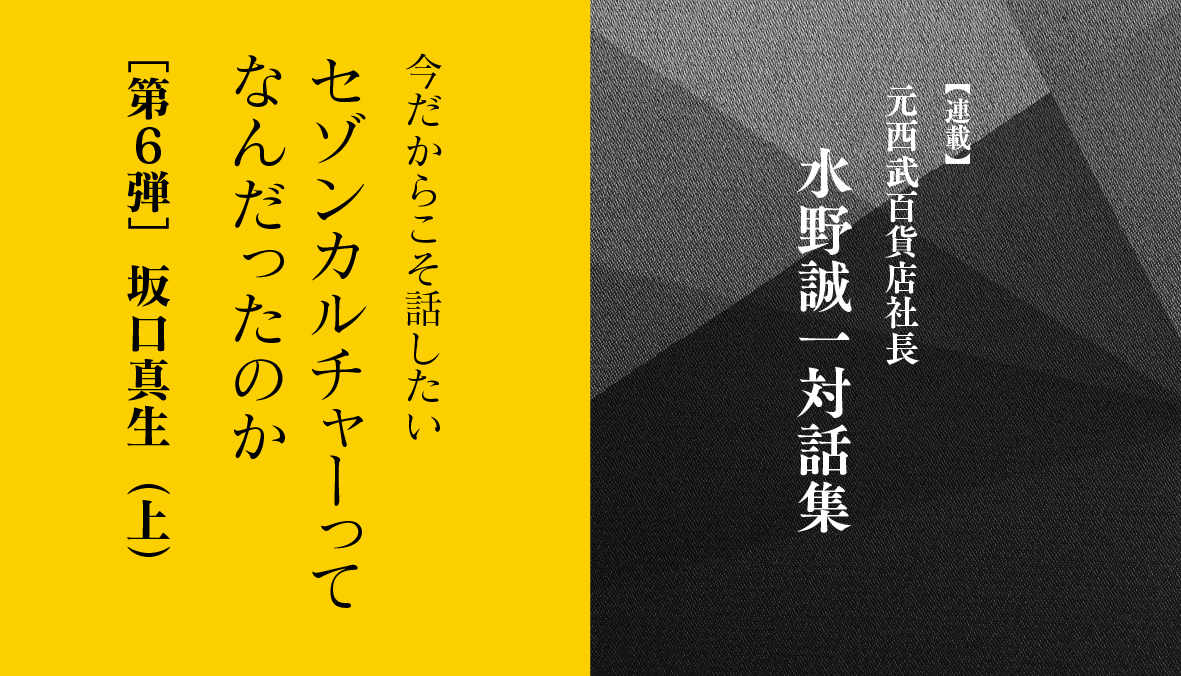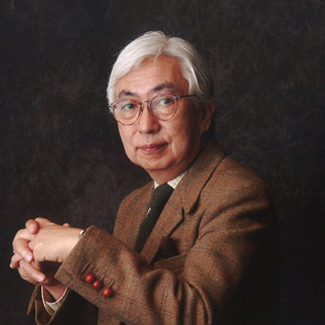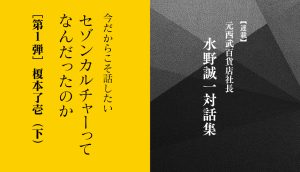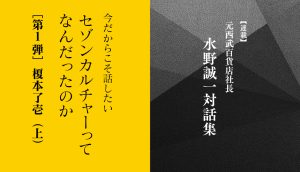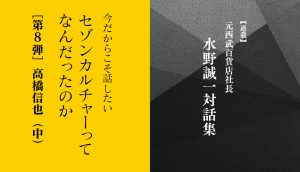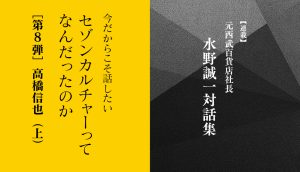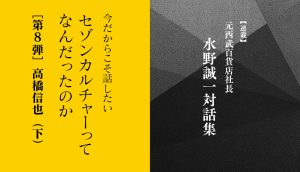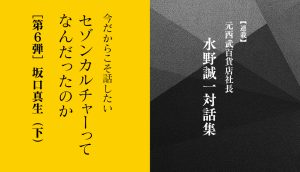「ethical」=エシカル。その言葉は倫理的な、という語意から人や社会、環境に配慮した考え方、行動を意味する。
水野誠一対話集、今回のゲストは、日本初のエシカル・ディレクターとして、物販や旅までさまざまな方面でその概念を説きつつクリエイティブに活動する坂口真生。
前編では、水野誠一との出会い、初めて組んだ仕事でぶつかった壁についてなど忌憚のないエピソードが飛び出す。

出会いはアッシュ・ペー・フランスの展示会「rooms(ルームス)」
水野 今日の対話場所は坂口さんがオフィスとしている、EAT PLAY WORKSです。この場所自体がシェアリング・エコノミーのシンボル的な、シェア・オフィス・スポットなんですね。ここは出来てから何年ですか。
坂口 もう 4年目ですね。7月で丸 5年になります。名前の順番が、食べて、遊んで、仕事が最後に来ています(笑)。一応、仕事をする場所なんですが。
水野 ソルトグループCEOの井上盛夫さんに賛同してメンバーになられたのでしたね。僕もそのうち参加しようかなと思っている場所なので、楽しみにやってきました。
坂口さんとの出会いは、アッシュ・ペー・フランスがやっていた「rooms」という展示会でしたね。
あれは結局、何回やったんですか。
坂口 トータルで 44回くらいやってますね。20年以上をかけて。
実際 1年に 2回 のペースでやっていたので。
水野 僕は西武百貨店を辞めてから、ああいう展示会というものに一切行かなくなっていたのですが。唯一「rooms」だけは面白いので、行っていたんです。
ところがある時プロデューサーの佐藤ミカさんから、「今回は坂口さんに案内してもらってください」と、ご紹介をいただきました。
坂口 それは、僕がアッシュ・ぺー・フランスでエシカル事業部を始める直前だったので、2010年か2011年、森ビルでやったときだったと思います。代々木体育館が使えない時期があって、六本木ヒルズでやったときですね。
水野 そうですね。最初の頃は入り口の辺りに小さくエシカルコーナーがあって。それで真生さんはエシカルということをやっているのだと初めて知ったんです。
ところがそれから毎年、行くたびにエシカル・エリアとして大きくなっていて、最後の頃は 全体の3分の 1ぐらいになっていましたね。
坂口 一番大きくなったのは 2019年の記念すべき 40回目「rooms vol.40」でした。
合計 115ブランドぐらいですかね。
水野 最初はエシカルって何なんだろうって僕自身もよくわからなかったところからスタートして。 でもエシカルという定義が、これからすごく重要な意味をもつと思い始めたのが、その最後のあたりでした。 残念なことに、 アッシュ・ぺー・フランス自体が経営的に難しくなって、展示会は途絶えることになってしまった。だけど、その後 「NEW ENERGY」という形になった。そこに変わるまでにブランクは何年かあったんでしたっけ?。
坂口 ブランクはほぼなかったです。roomsのチームが丸ごと会社を出て、場所も住友三角ビルに移して、「NEW ENERGY」という展示会イベントに変わったんです。
商社、テレビ局とのコラボで分かった、エシカル意識の未到達
水野 その後、某商社から「テレビ局とコラボで事業をしたいんだけど何か良いテーマはありませんか」との相談が僕の所にありました。迷わず「エシカル」を提案し、坂口さんを思い浮かべました。
坂口 ありがとうございます。一緒にプロジェクトができそうだと思いました。
水野 「テレビ局とのコラボ」という条件がありました。最初は興味深いと思ったものの、その条件が少し難しい点となってしまったようです。
業界では「ELEMINIST」など数社が先行していました。我々もそれを超えるためにいろいろ試みました。あの話が来た時、どう感じましたか。
坂口 いや、もう僕としては俄然前向きでした。ライフワーク自体がエシカル消費市場を作り活性化させる、ということなので。エシカル消費を拡大させていくための刺激材になることなら、何でもポジティブにやりたいと思っていましたから。
まずは 一つは、商社が絡んでいるということ。 そしてメディアのなかでも、マスメディアとしてのテレビ局が、絡んでいるというのは、非常にチャレンジしがいがあるものだと思いました。
もう一つは、水野さんに声をかけていただいたということも、嬉しかったし大きかったです。
水野 始めて1年間、PoC(Proof of Concept/実証実験)で始まったんだけど、そこでの問題点の一つは、テレビ局が専用の番組を作ってくれるのかと思っていたら、 そうではなくて、番組の空き枠があるところに少しずつ突っ込むというやり方だったんですよね。 そもそも僕はこのエシカルの商品というのは、物語を語っていかないとなかなか消費者に届かないと考えていました。
その物語をもっと丁寧に番組として作ってくれるのかなと思ってたんだけど。
結局、 PoC(Proof of Concept/実証実験)の域を出なかったのは非常に残念なことでした。
商品の買い取りもできないし、バイヤーもいない。ビジネスとしての構造もできていなかった。
坂口 僕が本当にディレクションしたい方向に持っていけなかったのは残念でした。マスメディアというものは凝り固まってる部分があって、それを我々が粘土のように柔らかくすることができなかった。
同じような売り方をしちゃダメなんだなって、今でもあのときの学びが続いている感じはあります。マスを相手にしているテレビ局の方々のマインドも、感触として分かった部分があるので、切り取り方、あとは他との差別化みたいなところを変えていかなきゃいけないと、突きつけられた部分もすごくあります。でも、逆にそれはまだ可能性があるということでもあると前向きに捉えています。
水野 もう一つはエシカルという言葉自体の、世の中の理解が充分に足りていないということもありました。エシカルというと、なんか安いものだという消費者サイドの思い込みも間違っているし。
坂口 安い、難しい、堅苦しい、みたいな(笑)。
水野 この商社がやっている、テレビ通販にサステナブルなコーナーがあったんですが、ほとんど何にも学ぶ要素がない。なんか、中途半端にエシカルをかじっている風潮があちらこちらに見受けられますね。

うめだ阪急はエシカルを最上の形にした
水野 そんななかで、 僕が非常に勉強になったのは、坂口さんから、阪急うめだ本店に「GREEN AGE」というのができたという話を聞いたことです。
あれは坂口さんはどういうふうに関わっているんですか。
坂口 「GREEN AGE」に具体的に関わってることはないんですが、それができる少し前に、数年間にわたって、阪急阪神のエシカル・コンサルタントのようなことを社員向けにやっていたんです。さまざまな立場のマネジメント・クラスの方を相手に。
売り場も衣類、食品、それに広報や人事などのマネージャー・クラスの方々に対して「エシカルとは」というところから始めて、実際の事例を検証したり、みんなで環境系のドキュメンタリー映画を見たりとか。
あとはキャンペーンをするときに、その人たちと15分ずつぐらい 、1日かけて面談をして「皆さんどういうことやるんですか」とかそれに対して事例を紹介したりとか。 つまり、意識づけをして行くようなことをやりました。
その流れで、あの阪急百貨店の大改装をやるという話は聞いてはいたんですよ。
まさにニューエイジのエリアなので、社員がすごく大胆なチャレンジをやってたじゃないですか。
水野 女性の担当者の方がいましたね。僕が本当に驚いたのは、ラグジュアリー・ブランドが数多く並んでいるということでした。
坂口 はい。広く展開、出店していますね。
水野 ラグジュアリー・ブランドこそがエシカルの最たるものであるべきだと。
今の世の中では、毎年大量の衣料品が新たに生産され、実際に使用されることなく廃棄されているケースが多く、大量生産・大量消費・大量廃棄のサイクルが深刻な問題を引き起こしていますよね。
昔、百貨店にいた身としては、なんとも心が痛む思いなんですが。
その中で最も問題なのは、低価格で大量生産される商品ですよ。対照的に、最も救いがあるのは、ラグジュアリー・ブランドです。なぜなら、高級ブランドの商品は購入後、大切に扱われ、流行に左右されることが少ないから。
坂口 このシリーズの石川次郎さんとの対談でも、60年ぐらいもっているセーターがあるとおっしゃっていましたね。
水野 そうですね。初期のVANの話でね。
坂口 そのとき、高くてどきどきしながら買ったものは、捨てられない、と。
水野 捨てたくないんですね。 そういうふうに長くもってもらうために、そのフロア(GREEN AGE)で中心になっていたロエベの「LOEWE ReCraft(ロエベ リクラフト)」は修理をするセクションを作っていますね。直すだけではなく、リモデルしてお客様の欲しいバッグに作り替えるとかね。そういう話を見聞きして「エシカルは安いという誤解は、こういうことで解いていくのが一番早いのかな」と、思いましたよ。
ラグジュアリー・ブランドにはサステナブル・セクションがある
水野 阪急うめだ本店の「GREEN AGE」は、なかなかたいした売り場だと思いました。
坂口 僕があそこの担当者に聞いて、すごく印象に残ったのは 、この売り場のコンセプトに、ラグジュアリーブランドの方が乗り気だったということでした。
プラダ、ミュウミュウ、ロエベなど大きいスペースで入っていますが「よくこんな営業の交渉ができましたね」と言ったら「逆に、ラグジュアリー・ブランドの方が乗り気だった」と言われたんです。
実際「無理だろう」と思って交渉してみたら、逆に「阪急さんみたいな大きなデパートが、がっちりサステナブルなテーマでフロアを作るっていう 、その明確なコンセプトはむしろ超ウェルカムです」と。
つまり、今やラグジュアリー・ブランドにはサステナブル・セクションが当たり前のようにあって、 10年以上、サステナブルなシリーズを出していたりする取り組みもあったり。プラダに関しては什器までがサステナブルな素材であったりとかする。逆にもう、今オファーしてくれたスペースよりもっと広いスペースが必要だ、みたいな反応だったそうです。
本当に日本の企業よりも前向きに話ができたそうです。
一方で今、その百貨店がラグジュアリー・ブランドを1階に出店させることがすごく難しくなってきている現状があって苦しんでいるというのを聞きますが。
明確なテーマさえしっかりもって落とし込めば、そういうことになるんだという事実は、なんだか勇気づけられました。

ステラ・マッカートニーというエシカル・アイコンの物語性
水野 しかもあの「GREEN AGE」の規模は半端じゃないですよね。 8階だけど 約700坪くらいあって。売り場作りもほとんど廃材であるとか。なかなか素敵な売り場ですよ。
このエシカルの世界では、シンボリックな存在でもありますね。
僕は最初、ステラ・マッカートニーが全部コンセプトをやるというように聞いたんですよ。看板みたいになっていましたが、ステラ・マッカートニーの活動というのは、坂口さんは、昔から注目されていましたか。
坂口 そうですね。サステナブルなブランドとしては、ラグジュアリーという、別次元で、こだわり抜いているし。
デザイナー自身がかなり、 貫き通してアイコンにもなっているし。
阪急うめだ本店さんではいろいろやられていて、大きな展示とか、その過去の写真展みたいなのもありました。その過去の写真展は面白くて、お父さんの ポール・マッカートニーやお母さんの実家に行って引っ張り出してきた昔の写真とかも結構並んでいました。
それらを見ると、いかに両親がステラにサステナブルな教育をさせたかということが伝わってくるんです。小さい頃から牧場へ連れて行って生活をさせ、それが動物愛護につながっていたり、菜食主義になったり。
そういう幼児教育の前に、父親のポールはあの時代のヒッピー・カルチャーのなかにいた文脈にもすごく興味がありますね。それでいて、彼女はラグジュアリー・ブランドというものを選んだ。そこに飛び込む形で入った彼女のこだわりと貫き通し方は、一線を画していると思います。
水野 彼女のショップで、レコードプレイヤーとか、スピーカーとか、非常にシンボリックなディスプレイもありました。
それから、やっぱりステラ・マッカートニー自身が、そういうサステナブル・ライフをしているという感じが、なるほどな、と。シンポリックに彼女を起用しているとことが素晴らしいなと思います。
けれども、正直、僕は心の片隅で、このチャレンジングな売り場がどれくらい持つかなという心配もあったんです。百貨店というのは、売り場での効率が悪くなるとすぐ撤去しますから。でもすでにあそこは 2年以上ありますね。 大阪へ行ったら、僕は必ずあそこに立ち寄るんですよ。全館がエシカルな百貨店、できないかなあ。
ところが最近になってシンボルゾーンだったステラ・マッカートニーの売り場が撤退したと聞いてショックを受けています。売り上げよりもシンボルゾーンだっただけに、何か残して欲しかったと痛感しています。
撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph
構成:森綾 http://moriaya.jp/