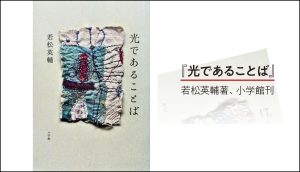2024年12月20日(金)に発売した、ソトコト編集長・指出一正8年ぶりの新刊『オン・ザ・ロード 二拠点思考』が、おかげさまで好評です。そこで今回、「まだ買ってないよ」「買うかどうか迷っている」という方のために、ソトコトオンライン編集部オススメの、読者の興味関心を掻き立てるパートを一部抜粋して、“ソトコトオンライン限定”で無料公開しちゃいます!
\書籍レイアウト版で読みたい方はこちら!/

『オン・ザ・ロード 二拠点思考』
「はじめに」より
12号車、8番C席。iPhoneのアプリ「EXアプリ」を立ち上げ、東海道新幹線ののぞみの席を予約する。指定席の12号車はお気に入りで、だいたい真ん中あたりの8列目、3人掛けシートの通路側のC席を取る。品川、あるいは新横浜から乗り、新大阪、または新神戸で降りる。その逆の日もある。
「崎陽軒のシウマイ、買っていこうか?」
「りくろーおじさんのチーズケーキは?」
移動の途中で妻や息子にショートメッセージを送る。これが今の、日常のペース。
2022年4月、東京で暮らしていた僕たち家族は、息子の進学で縁があり、兵庫県神戸市に移住しました。妻と息子(と保護犬のフレンチブルドッグの朔)は関西に住み、僕は東京と神戸を行き来する。自分にとっての二拠点生活が始まったのです。引っ越した直後は漠とした気持ちも抱え、取材や事業のスケジュールの調整に頓知を働かせ、些細な忘れ物が増え(笑)、そんな心を住まいの近くを流れる住吉川を泳ぐ天然のアユたちに解きほぐしてもらいました。その頃は新大阪から神戸線の快速や新快速への乗り換えも、車内での立ち方もぎこちなくて、関西ライフの初心者として迷惑にならないようにと、きっと緊張していたのでしょう。
社会や環境を主題にしたメディア『ソトコト』の編集長を務める僕にとって、二拠点生活は重要かつ話題のトピックです。日本の各地で拠点を複数持っている方々にもお会いして、いくつもの満ち足りた表情を拝見してきました。今、自分が二拠点生活を行うようになって2年半が経ち、おもしろさを実感しています。二拠点生活は僕の視点にもふくよかな広がりを与えてくれて、その経験から「二拠点思考」という新たな言葉と考えに至りました。実際に「住む」といった生活の拠点を持っていなくても、ふたつの好きな拠点を意識して複眼的に地域や社会を見つめることで、関係人口の裾野が広がっていく。二拠点思考にはこのような思いが込められています。
2016年12月8日に出版した単著『ぼくらは地方で幸せを見つける ソトコト流ローカル再生論』(ポプラ新書)は、地方創生やローカルの暮らしに興味のあるほんとうに大勢のみなさまに手に取っていただくことができました(心より感謝申し上げます)。この一冊から関係人口の議論や政策が生まれていくという機会に恵まれ、著者としては想像していなかった日本社会全体での動きが起こり、現在の新たな地域づくりにつながっていることを思うと感慨深いものがあります。僕にとって、自分をまだ見ぬ世界に出会わせてくれた恩人のような本です。
以来、8年ぶりに刊行する自著が本書『オン・ザ・ロード 二拠点思考』となります。「オン・ザ・ロード」は日本語に訳すと路上の意味です。生き方や思想で影響を受けたビート・ジェネレーションを代表する作家であるジャック・ケルアックの代表作『路上』になぞらえたところもありますし、東海道新幹線や東北自動車道、国道6号や350号、さらに明石海峡大橋、山陰本線、猿払村道エサヌカ線など、各地を移動するその一瞬一瞬を過ごし、思考した場所やルートもすべて路上であると考え、このタイトルに決定いたしました。ビーティフィックなビートニクたちとは比べるべくもありませんが、ローカルの路上に立ち、つむいだ言葉の集合体です。地域を歩き、人に出会い、山と川と生き物の美しさに惚れ惚れとし、人の息づかいの聞こえるまちなみでの浮き足立った記憶のお土産とも言えるかもしれません。
本書の読みどころをご紹介しましょう。まず、全編を通して2016年以降、特に2022年から2024年の約3年の間に『ソトコト』編集長が注目して訪れたり、関与したりした日本の地域の現状や取り組みについての事実や解説が読みやすい語り口調で述べられています。ニッチかつミクロの視点も取り込んでありますので、地域づくりやローカルプロジェクトがどのように生まれ、経過していったかなど知りたい方、その背景や機微にご興味がある方も広く楽しめると思います。
次に、地域や社会の現在から未来を満たしている空気感、「社会気分」と呼んでいますが、オンゴーイングの社会気分を主にふたつの言葉で表し、説明しています。ひとつは「二拠点思考」、そしてもうひとつは「リジェネラティブ」です。二拠点思考は僕自身が二拠点生活を実践する中で体感していった価値や創造です。人の暮らし方がこのように拡張されていっているということを説明しています。
リジェネラティブは英語で「再生させる」の意味です。サスティナビリティの価値観が環境政策だけではなく、まちや社会や福祉の分野までも飲み込んで広がりを見せたように、リジェネラティブも、土壌の再生にとどまらず、社会と未来を豊かにリジェネレーションしていく思考とムーブメントになってきています。このリジェネラティブという感覚をわかりやすく紐解いています。
そして、前作に続く「関係人口の現在」を、実例と各地の講座での実践によって積み重ねたフィールドワークを基に論じています。論じる、というと論文のようなので、「おしゃべりしています」のほうがしっくりくるかもしれません。関係人口がどのように深みをつくり、分化を見せたのか、関係人口として地域に関わる人や地域で関係人口を迎え入れる人たちの思いなど、たっぷりおしゃべりするように書いています。関係人口の現在地、そして行く先を知りたい方にもおすすめです。
さらに。フレッシュなローカル事情をお話ししているのにもかかわらず、個人的な好みで随所に1980年代や90年代の街角と中山間地域の風景やカルチャーが投げ込まれています。趣味の魚釣りの挿話も少々。過去と現在、何事も「掛け合わせる」ことで理解が進むというのが編集の信条にあり、ご寛容をいただけたら幸いです。
それでは、旅支度をしてページの中の「路上」へ。光と匂いあふれる風景を軽やかにお楽しみください!——
続きは『オン・ザ・ロード 二拠点思考』で! >>>>>>>>>>
『オン・ザ・ロード 二拠点思考』
第4章「 二拠点生活とリジェネレーション」より/
リジェネラティブなサスティナビリティとは?
サスティナビリティは皆さんご存知のように、日本語では「持続可能な」と訳され、SDGs(サスティナブル・ディベロップメント・ゴールズ)、持続可能な開発目標の1文字目の「S」がそれに当たります。じゃあ、「リジェネラティブ」って何なのか? 最近、僕はこの言葉をよく口にしているのですが、ひとことで言うと「再生させる」という意味です。「リジェネラティブ・アグリカルチャー」なら、「再生させる農業」、再生型農業と訳されますが、元々、「リジェネラティブ」という言葉のコンセプトは農業から始まったものだと考えてもらっていいと思います。1960年代頃から広まった環境再生型の農業もそう。1970年代にオーストラリアのビル・モリソンとデイヴィッド・ホルムグレンによって提唱されたパーマカルチャーも「リジェネラティブ」のマインドに当てはまっています。
最近になって、「リジェネラティブ」という言葉が注目され始めている大きな理由は、「サスティナビリティ」の盛り上がりから来ていると思います。よりよい未来をつくるためにどういう手法を考えたらいいのかと、農業や第一次産業にとどまらず、福祉や教育でもみんながそれぞれの専門分野で考えを凝らして、工夫しています。一直線型ではなく、スパイラルでもいいし、右肩上がりのイメージがあってもいいと思うのですが、今よりももっと楽しく、もっと豊かに、もっと幸せに、と考える人たちが現れ出しているのが2020年代だと感じています。そこに「リジェネラティブ」という言葉が、農業や土の分野を飛び越えて現れたというのが注目されている理由だと考えるといいかなと思います。
「サスティナビリティ」のメタファーというのか、シンボリックな存在として挙げられるのは海です。海洋プラスチックの問題は深刻で、ウミガメがクラゲと間違えてビニール袋を食べたり、ペットボトルの小さな破片を飲み込んだり。川から海へ流れ出たプラスチックごみが年月を経てマイクロプラスチックとなり、ウミガメに限らず魚たちの体内から検出されています。そんな映像を見て、子どもたちが胸を痛めています。これ以上、海の環境が悪化しないようにするために、マイクロプラスチックを含む海洋プラスチックごみの問題を防ぎ止めなければいけません。「サスティナビリティ」は、ビジュアル的にも海と結びつきやすいのです。
「サスティナブル・シーフード」という考え方もあります。海の食料資源が減っていく中で持続させなければいけないという議論が1990年代から2000年代にかけて起きました。経済として養殖産業をしっかりと組み込んでいかないと、海の食料資源が足りなくなることはわかっているので、サスティナブルな視点で海の食料資源を確保できるよう考えなければいけないことからも、「サスティナブル=海」というメタファーは成り立ちそうです。
一方、「リジェネラティブ」の言葉のコンセプトは土、すなわち陸です。それぞれのルーツが海から、陸から来ているのです。「リジェネラティブ」は、僕たちが踏みしめて歩いている大地から来ているというのも、ちょっと特徴的な気がします。たとえばここ10年間くらい、「アーバン・パーマカルチャー」が注目されたり、都市型農業が人気になったりしているのも、「リジェネラティブ」に紐づいているんじゃないでしょうか。「リジェネラティブ」のルーツは、土壌を修復し、自然環境を回復するという環境再生型農業にありますが、今では社会やまちづくりの分野でも広く使われる言葉になっています。僕の言う「リジェネラティブ」は、どちらかというと広義の意味の「リジェネラティブ」だと考えてください。「サスティナビリティ」は、防ぎ、持続させること、「リジェネラティブ」は防ぎ、再生させることだと僕は意味づけていますが、「リジェネラティブ」は従来の場所や仕組みを改善し、人がより幸せになるように取り組んでいく行為なのではないだろうかと思っています。
なぜ、こんなことを2024年になって言い出したかというと、僕が大好きな地域づくりやまちづくり、未来のビジョンをつくっている若い人たちは、「リジェネラティブ」という言葉を数年前から自由に使っておられるから。トークセッションやワークショップでも、「リジェネラティブ」な話を熱心にしてくださる方々が大勢いらっしゃるのです。社会の空気として、「リジェネラティブ」が広がっていることを感じて、僕も使うようになったのです。
2024年の新春、久しぶりにサンフランシスコに行ったことも「リジェネラティブ」をより意識するようになった理由です。何か新しい風を感じようとか、何かの仕組みを見てこようというより、自分のマックブック・エアをアップルセンターに里帰りさせてみようというくらいの小さな幸せを感じられればと、パロアルトやスタンフォード大学を見てきて、西海岸の気持ちいい風を浴びてきました。イノベーションという言葉が生まれた本丸のようなまちを清々しい気分で歩いてきたのですが、その時、はたと気づいたのです。東京みたいに、SDGsの17のパネルをあまり見かけないなと。教育機関や、イノベーションを起こす場所に、日本だと必ずあるSDGsの色とりどりのユニバーサルデザインのパネルが見当たらなかったのです。もしかすると、17のパネルが目に入らないほどほかのグラフィックが格好よかっただけかもしれませんが、少なくともアメリカがSDGsを一生懸命やっているという印象は、2週間ほどの滞在中、感じることはありませんでした。
その代わり、言葉としての「リジェネラティブ」が、たとえば「ハワイをリジェネレーションしよう」というように、それがアメリカでキーワードになっているのか、英語を追いかけると「リジェネラティブ」という言葉がずいぶん使われていると感じました。西海岸、とくにサンフランシスコだったからでしょうか。「サスティナビリティ」よりも「リジェネラティブ」の空気感の方が広がっている印象を受けました。バイアスがかかった目で見ていたからかもしれませんが。
調べてみると、SDGsはどちらかというとヨーロッパ型、EU型の環境への取り組みで、SDGsを実践している国のランキングも、だいたい北欧やEU関連の国が上の方にあって、アメリカは40位くらいです。でも、頑張っていないのかというとそうではありません。社会や環境をよくするためのテクニックは違うけれども、環境問題に取り組んでいるのは事実です。SAFなどのサスティナブルな燃料にも力を入れています。おそらく、アメリカが選択肢として取ったのが「サスティナビリティ」よりも「リジェネラティブ」だったのでしょう。そんな空気感を感じて、僕も「リジェネラティブ」を言い始めているのです。ちなみに、SDGsは「リジェネラティブ」と言えそうです。SDGsは前に発展させる目標がほとんどで、食い止めるためのものではありません。SDGsは「リジェネラティブ・サスティナビリティ」みたいな言い方ができそうです。「再生させる持続可能性」とか、「再生型持続可能性」とか。直訳ですが、「リジェネラティブ・サスティナビリティ」みたいな考え方が今、日本が目指しているところじゃないかなと感じています。
日本でも、「サスティナビリティ」と「リジェネラティブ」を考える上で参考になるいい本が発行されています。ベーシックなものでは、ポール・ホーケンが書いた『リジェネレーション[再生]気候危機を今の世代で終わらせる』(山と溪谷社)。環境再生という大きなテーマで書かれている本です。もう1冊は、東京大学連携研究機構不動産イノベーション研究センター(CREI)が出している『Regenerative Commons – 場所と地球がつづくための関係づくり』という冊子です。コモンズという言葉がついているように、場所に関しての「リジェネラティブ」を研究する方々の論考が掲載されていて、僕も大変参考にさせてもらいました。「リジェネラティブ」で検索していただくと他にも出てくると思いますが、特に建築や都市デザインの世界で「リジェネラティブ」がよく語られているのが2024年っぽいです。
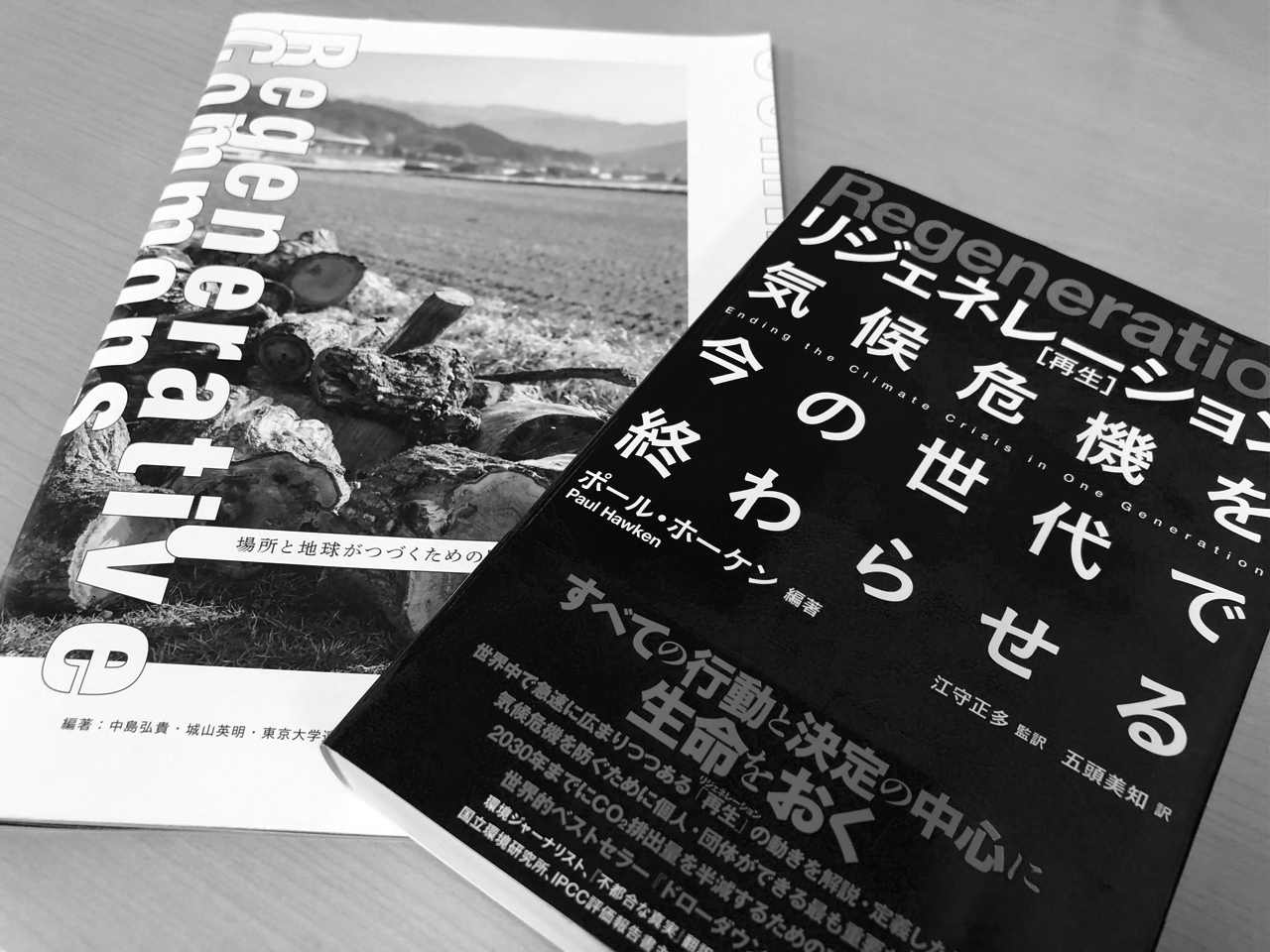
勉強みたいな話はこのくらいにして、僕の中で「リジェネラティブ」ってどういうことなのか話していこうと思います。今、僕が夢中になって読んでいる漫画の話をしましょう。久々に読み始めました。これで3回目。『夏子の酒』です。1988年に初版が出ました ―――
続きは『オン・ザ・ロード 二拠点思考』で! >>>>>>>>>>
『オン・ザ・ロード 二拠点思考』
第5章「地域PRの好例に見え隠れする二拠点思考」より/
岡谷といえば、シルク、うなぎ、釣りの餌
その軽井沢へ、神戸から車で訪れる途中、諏訪湖に隣接する岡谷市に立ち寄りました。岡谷は僕のなかでとてもおもしろいまちなのです。岡谷の市議会議員に今井浩一さんという方がおられ、その方に2024年の春に招かれ、まちづくりの勉強会の講師をさせてもらいました。今井さんは地域のカルチャー活動にも力を入れられて、『ソトコト』にも共感していただいているのですが、元は演劇情報誌『シアターガイド』の編集長をされていたという経歴の持ち主です。その岡谷は、実は僕にとってルーツの場所で、子どもの頃によく来ていた地域なのです。
何をしに来ていたかというと、僕の父はボイラーをつくる小さな会社を高崎で経営していたのですが、僕が小学校の頃に、「これから岡谷に行くけど一緒に行くか」と声をかけられて、「うん、行く」ってよく連れて来てもらっていたのです。別に岡谷に興味があったわけではなく、ただお父さんと一緒に出かけるのが楽しみで、途中でゲームセンターでクレイジークライマーをさせてもらえるかもしれないとか、ほかほか弁当で唐揚げ弁当と海苔弁当を2つ買ってもらえるかもしれないとか、その程度の楽しみでついていっていたのです。父は仕事に来ていました。岡谷の製糸工場をはじめ、現場のボイラーの見回りをしていました。つまり、お得意先の営業ですね。そんな思い出もあったので、家族と一緒に岡谷に立ち寄ることにしたのです。
岡谷は、隣の諏訪市にある諏訪大社の文化が色濃い地域です。諏訪大社は縄文がルーツで、掘り下げると非常におもしろい。諏訪湖のエリアって縄文文化なんですよね。縄文時代の遺跡もたくさんあります。それほど古くから人が暮らし、独自の文化を築いている地域なのです。また、製糸やシルク産業が盛んで、経済もそれで潤った地域なのですが、僕にとっては見逃せない日本を代表する企業がここをルーツとして操業しているんです。それは『マルキユー』っていう会社です。今は埼玉県に本社があり、さいたま新都心に「マルキユー」って書かれた大きなビルが立っていて、この前、仕事で近くに行ったときに、そびえ立つマルキユービルを見て、拝みたくなるくらいの神々しさを感じたのですが、そのマルキユーが創業したルーツの場所が岡谷。そしてマルキユーがなんの会社かというと、釣りの餌をつくっている会社なんです。
岡谷は明治時代から製糸産業が盛んです。映画にもなった有名な小説『あゝ野麦峠〜ある製糸工女哀史〜』の野麦峠はもう少し西の方ですが、岡谷にはこの野麦峠を越えてやって来た工女さんがたくさん働いていたようです。工場では蚕の繭からシルクの糸を取るのですが、繭の中にいるサナギは必要ありません。その廃棄されるサナギを仕入れて釣りの餌に活用したのが『マルキユー』でした。僕にとっては、まさにローカルベンチャーの元祖と言える会社。
そういうことも含めて、岡谷は親しみを持っている地域なのですが、先ほどの勉強会に来られていた『やなのうなぎ 観光荘』といううなぎ料理店の3代目の宮澤健さんがお土産をくださったのです。それが、JAXAに認証された宇宙食の「スペースうなぎ」。僕はとてもうれしくて、お店にも食べに行きたかったのですが、そのときは時間がなく、残念ながら行けませんでした。宮澤さんは「シルクうなぎ」というメニューも開発していて、『マルキユー』と同様、シルク工場から出る蚕のサナギをブレンドした餌をうなぎに与えていて、やわらかで、ふっくらとした食感のおいしいうなぎに育つそうです。
そんな観光荘のうなぎを家族で食べることができました。ものすごい人気で、1時間以上待ってようやく席につけたのですが、宮澤さんが僕のことを覚えてくださっていて、連絡もしていなかったのに見つけて、すぐに声をかけてくださいました。スタッフの皆さんも優しく声をかけてくださり、愛される老舗なんだなと実感しました。そんなうなぎ料理店が岡谷には何軒もあり、岡谷はうなぎのまちとして売り出しているのです。「うなぎ音頭」もありますよ。おもしろいのは、うなぎの焼き方。関東は背開きで白焼きにした後、蒸してから再び焼き、関西は腹開きで蒸さずに焼きますが、岡谷はそのハイブリッド、背開きで蒸さずに焼く。東と西の交通や文化が交わる地域ならではの食文化を体感しました。甘めのタレで、とってもおいしかったです。
諏訪湖に近い岡谷では、元々、諏訪湖でうなぎが水揚げされていた時代が長かったのでうなぎの文化が息づいているのです。うなぎをはじめ、川魚文化があったわけですが、今は日本全体、世界全体として天然うなぎの資源が減少していますから、諏訪湖でのうなぎの水揚げが岡谷のうなぎ料理店を存続させるだけの規模を維持することができなくなってしまっています。うなぎは豊橋など、良質なうなぎの産地で育てているそうです。でも、週末になると、そこここのうなぎ料理店には開店と同時にお客さんが並んで予約を取り、おそらく1時間以内に「今日のうなぎは終わりました」みたいな紙が貼られるくらいに大盛況でした。若い人も、先輩世代も、遠くは関西からもお客さんが来ています。その場所ではとれなくなったけれど、地産地消でなくてもその地域らしい食文化として名物を残し続けることができるということを岡谷のうなぎから学びました。
お腹がいっぱいになったところで、『岡谷蚕糸博物館 シルクファクトおかや』に足を運びました。現在もシルクを紡いでいる工場そのものがミュージアムになっていて、働いている方々の後ろを通ったり、その方に質問したりすることもでき、臨場感がありました。シルクについて学び、しかもシルク製品がアウトレット価格で買えるとあって、機織りをやっている妻は満面の笑顔で機織りのための生糸を買っていました。岡谷、とてもいいまちです ―――
続きは『オン・ザ・ロード 二拠点思考』で! >>>>>>>>>>