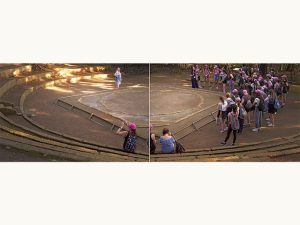数十人の“棚主”が本を持ち寄り、場をシェアしながら、販売。店番を交代で行うことで運営さえもシェアするという新しい本屋が、東京都武蔵野市に誕生しました。
名前は『ブックマンション』です。
みんなでシェアして運営する、『ブックマンション』。
東京都武蔵野市に無人の古本屋『BOOK ROAD』を弟で建築家の中西健さんとつくったのが7年前。以後、運営を続けてきた中西功さんが、2019年7月に同じく武蔵野市に新たな本屋を開店した。JR中央線の吉祥寺駅北口から歩いて5分ほどのところに立つ小さなビルの地下1階にある『ブックマンション』だ。名前が示すとおり、フロアに設置された本棚はマンションのよう。縦横31センチのサイズに区切られた棚を、中西さんが月額3850円で”棚主“に貸し出している。今、70組ほどの棚主が借り、各々のスペースで好きな本を販売している。

「棚主さんたちが本を持ち寄り、このビルの地下1階の場をシェアし、一緒に運営しているのです」と管理者である中西さんは『ブックマンション』の仕組みを教えてくれる。毎月、70組×3850円=約27万円のレンタル料が『ブックマンション』に支払われ、さらに棚主の本が1冊売れると100円が『ブックマンション』に納められる。中西さんが書籍の在庫を持つ必要はない。2つの本屋を経営しながらも、運営に時間がかからないため、それ以外の仕事に取り組むこともできているようだ。

開店以来、半年間ほど中西さんが店番として『ブックマンション』に常駐し、管理してきたが、2020年1月頃から棚主がシフトを組んで順番に店番を担当する運営スタイルを導入。みんなで店番を行い、場を維持するので、特に人件費は発生しない。「本屋としての場も、運営も、棚主みんなでシェアするのです。月に20日間ほど営業すれば、3か月間に1回ほど棚主さんに店番が回ってきます。新型コロナウィルスの感染拡大の影響で、緊急事態宣言が出された4月から6月末までのうちの1か月半は休業しました。その後、1周年を迎えたタイミングで、お店のルールを変えました。営業時間は4時間です」と中西さんは言う。コロナ前は、カナダや香港からインスタグラムを見て訪れる外国人客も多かったが、そんな旅行者の姿も見られなくなったのは寂しいと嘆く。とは言うものの、『ブックマンション』は本の売り上げだけに依存をせず、また、人を雇ってもいないので、コロナのせいで店を畳むという深刻な状況には陥っていない。もちろん、営業は続けている。「棚に並べた本が売れるというプチビジネス以上に、本に対する愛着が誰かに共感されたうれしさや、好きだった本が誰かの手元へ旅立ったという喜びを感じられることが何よりの魅力だと棚主さんはおっしゃいます」と中西さんは、『ブックマンション』の価値をそう位置づける。

地域のコミュニティの形成や継続にも展開。
『ブックマンション』が大切にしているのは、人と人とのコミュニケーションだ。棚主同士、棚主とお客、お客同士など、店内でさまざまな出会いが生まれている。その橋渡しを担うのが中西さんだ。
例えば、棚の一つに『本屋』という本屋があり、棚主は小学5年生の山内蒼大くんだ。当時、父親の山内佑輔さんは公立小学校の先生をしていたが、蒼大くんと本の補充に来た際に中西さんから、「ユニークな棚主さんが今、ビルの上階で哲学対話のイベントをされていますよ」と紹介。その棚主は、『問いが見つかる本棚。』を運営するタガイさんだった。タガイさんは山内さんと話すなかで、「山内さんは学校での図工の授業は『自分で答えをつくるもの』とおっしゃっていて、考えに共通するものを感じました。3月の山内さんの図工の時間に『哲学対話』のワークショップを行うことに決まったのですが、新型コロナウィルスが広がってしまって」と中止になったことを残念がった。
山内さんはまた、吉祥寺の魅力を描いた「吉祥寺かるた」を制作したデザイン会社『クラウドボックス』の徳永健さんと園田理明さんとも知り合った。『クラウドボックス』は『クラウドブックス』という本屋の棚主で、新たに「コロナかるた」もつくったと聞いた山内さんは、4月から赴任した『文化小学校』の授業とコラボレーションしたワークショップの実施を依頼。児童たちも「コロナかるた」をつくるそうだ。


棚主がみんなで場をシェアしているからこそ、人と人とのつながりも生まれる本屋が全国に広まることを中西さんは願っている。「実店舗の本屋の運営は、今のご時世では二の足を踏む方が多いと思いますが、『ブックマンション』の仕組みなら始めやすいはず。地方の商店街の空き店舗を月10万円で借りられたとして、20人の棚主が集まれば1人5000円の負担で本屋を運営できます。20日間営業するなら月に1日、順番に店番をすればいい。管理者は本屋だけの収入では生計は立てられませんが、みんなで取り組むのでマイナスになることはなく、場は維持され、特に時間を割く必要がないため、今までの職を継続させることも可能です」とアドバイスを送る。
本屋でありつつ、コミュニティの場でもあると捉えれば価値は広がる。『ブックマンション』では棚主が店番をする間、その場で有料のワークショップを主宰してもいいし、本以外のものを販売してもいい。展示会やトークイベントなど、棚で販売している本とリンクするテーマのイベントを開くのもおもしろそうだ。

中西さんは言う。「モスキート音のように、年を取ると知覚できない事象もあると思います。僕はもうすぐ42歳になりますが、僕が『いい』と思ってもそれは42歳の男の視点から見た『いい』でしかないのです。自分と異なる世界を生きている人に関わってもらうことで、多様な視点の『いい』がその場に確保され、可視化され、具現化されていくと思います」。そんな、棚主たちの多様な視点を横目で見ているのが楽しいと中西さんは微笑む。「棚主さんたちの表現をなるべく制限しないようにしつつ、場が荒れることがないようにちょこんと座って、話に耳を傾けるのが僕の役割です」。
最近、中西さんは本のある場を増やすためのコミュニティ『ブックカルチャークラブ』を立ち上げた。環境変化に対応しやすい『ブックマンション』の仕組みを使い、地域のコミュニティづくりやその継続のための活動に賛同してくれる人を募っている。2025年までに本のある場を1000か所増やしたいと考えているそうだ。