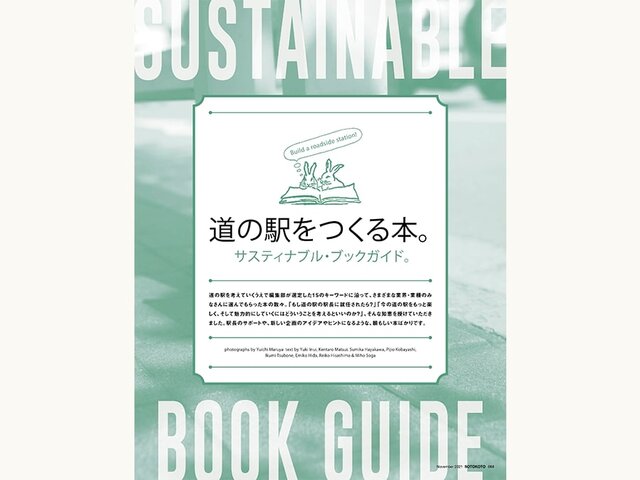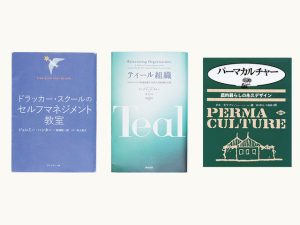石井宏子さんが選ぶ、道の駅をつくる本5冊
道の駅がその土地の直産品を販売する場所なら、温泉も同じように捉えることができるのではないかと思っています。そこで選んだ一冊が、『日本の温泉─170温泉のサイエンス』です。温泉を日々研究している『日本温泉科学会』が監修してつくった本で、その温泉がどういう地質から出ていて、どういう化学組成をしていて、どういう成分を含んでいるのかということが書かれています。温泉を野菜だとすると、栽培方法や生産者がわかるようなイメージです。道の駅の温泉を見つけたときに、こうした情報もわかるとおもしろいかもしれません。また、温泉のある道の駅や、温泉地の近くの道の駅で働く人にとっても、環境情報としての温泉とは異なる情報をお客さんに提供できるのでおすすめです。
『農業大国アメリカで広がる「小さな農業」─進化する産直スタイル「CSA」』は、道の駅の新たな展開のヒントになる本として選んだ一冊です。CSAはアメリカでもともと始まった考え方で、農家が作物をつくる前にコミュニティの住民が種や重機など農作業にかかる費用を事前に出資し、出資者はその額に応じて収穫期にできた作物を受け取ることができるというものです。農家は天候や疫病などさまざまなリスクを抱えていますが、原資を得られるため安心して農業に専念できるのです。このコミュニティサポートの形は、道の駅や温泉地といった場にも使えるのではないかと期待しています。お気に入りの道の駅や温泉地に先払いをしておき、あとからサービスを受けることができるようにする。そんなふうに都会や遠隔地にいる消費者も地域の活性化に直接関わっていけるのではないかと考えています。
道の駅と温泉を掛け合わせてできることは、まだまだたくさんあると感じています。私が道の駅で温泉をつくるなら、やっぱりその地域の特色を生かしたものにしたいですね。