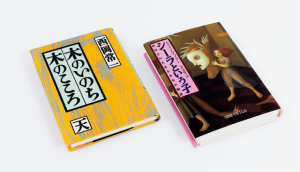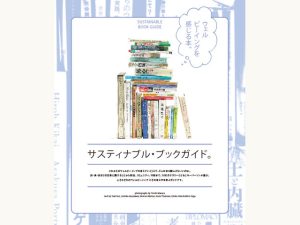瀬川 翠さんが選ぶ、道の駅をつくる本5冊
小嶋さんの建築は、人も車も自転車も電車もすべてをフラットに扱っていて、何気ない日常のワンシーンをドラマチックに見せてくれる。そういうところが素敵で大好きな建築家です。道の駅のようなモビリティと密接に関わる建築なら絶対に「小嶋さんでしょ!」と思いました。
研究室では人や車の移動をグラフィックで表現する研究や実証実験もしていました。情報を記号化、図式化する表記法を「ノーテーション」と言いますが、本のなかでは、都市のアクティビティを小さな矢印の群れに置き換え、そこから空間を考えていく設計メソッドが書かれています。人の動きはもちろん、光や空気といった環境の動きも小さな矢印と捉えて、その積み重ねによってボトムアップ的に空間をつくる手法です。
道の駅にはいろいろな人が来て、滞在時間も過ごし方もさまざまだと思うので、そういった多種多様さの捉え方が重要になると思います。多様な情報を矢印に置き換えて整理していく考え方を教えてくれるこの本は、いろいろな矢印が存在する道の駅の設計にぴったりだと思います。
『ビジネス・フォー・パンクス』は、スコットランド発祥の『BrewDog』というクラフトビール会社の話で、
タイトル通りとてもパンキッシュな内容です(笑)。著者の自伝を通して、事業計画が学べます。普通のビジネス書と違うのは、数字だけでは計れない想いを重視した内容であること。印象的だったのは「顧客ではなくファンをつくれ」という言葉です。
道の駅をつくるとき、「何のために」、「誰のために」というようなブランディングが必要になると思いますが、道の駅に限らず、公共性を優先して「老若男女のために」を目指すと、誰にも刺さらない魅力のぼやけたものになってしまいがちです。
この本は、事業を始めるときに自分が幸せにしたい人の顔が浮かんでいるのか、自分が本当にやりたいことを研ぎ澄ませているのかを、問いかけてくれます。私は、みんなのためのものとして設計されがちな道の駅や公園、公民館のような公共性のある場所も、もっと独自性を追求していくべきだと思います。個性的な道の駅ならわざわざ行ってみたいですし、紋切り型の道の駅だったら注目はしないですよね。これからの道の駅は、もっとつくり手のメッセージを込めてほしいと思っています。