地域課題の解決を通じて企業人が学びを深める、『日本能率協会マネジメントセンター』の企業向け「越境学習(ラーニングワーケーション)」。先行き不透明のこの時代、新しい学びの一つとして注目されています。その重要性や、地域の人々との対話に必要な心構えなどを知ることができる本を選んでいただきました。
選者 category:ワーケーション
『越境学習入門』は、考え方から実践のノウハウ、企業側と地域側それぞれの効果など「越境学習」をしっかりと理解できる一冊です。日本企業はこれまで現存するものを深化させることを得意としていましたが、先の見えない時代に探策的な発想をするのはとても苦手です。すでに前提を共有している者同士で新たな発想を誘発するのは限界があるため、前提を共有しないコミュニティの中で学ぶことの重要性をこの本から知ることができます。企業で人材教育をしている担当者や、これからワーケーションを取り入れてみたいと考えている人にぜひ読んでほしいと思います。
『問いのデザイン』は、問題の本質をどう見抜くか、固定観念をいかに壊すかにつながる「問い」と「対話」を戦略的にデザインすることについて書かれています。組織の中で働く人の多くが抱える問題は、自分たちの置かれた制約状況に気づかず、枠からはみ出す発想を持っていないこと。ここを打ち破ることで、一気に課題が見えてきます。ファシリテーターでなくても、問題を捉える思考法や課題設定の際に陥りやすい罠について知るだけでも十分。地域と都市圏をつなぐ人にとって勉強になると思います。
ただ休暇先として地域を楽しむのではなく、地域と企業の人が出会い、互いに学びや成長をもたらすことでつながり続けていく。このような機会は、関係人口の創出ももたらすと思っています。
宇田川元一著、NewsPicksパブリッシング刊
松下慶太著、学芸出版社刊
東大社研編、中村尚史編、玄田有史編、東京大学出版会刊






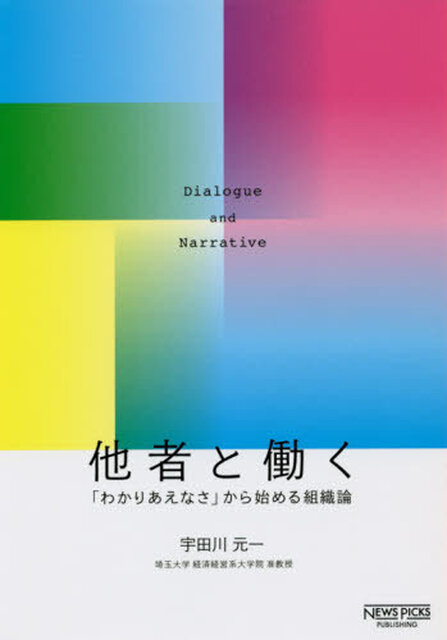


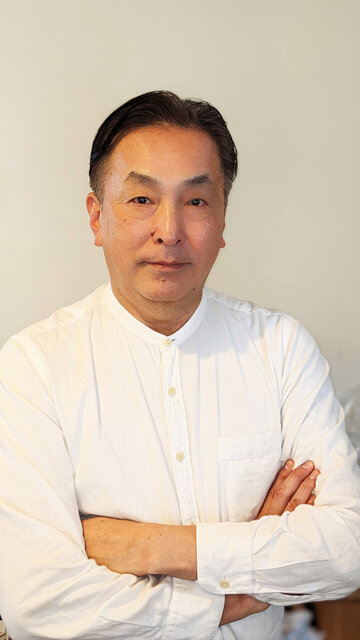





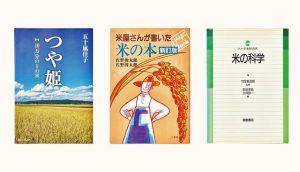












異なる共同体のメンバーと共に、専門領域を超えて行われる活動を「越境」と呼びます。この越境に焦点を当てた本で、組織の中で働く人が境界を越えた活動を通して、何をどのように学んでいるかを知ることができます。
問いのデザイン ─ 創造的対話のファシリテーション/安斎勇樹著、塩瀬隆之著、学芸出版社刊
問題の本質を見抜き、解くべき課題を正しく設定し、関係者を巻き込むという課題解決のプロセスをデザインする。その考えや方法を紹介しています。地域の課題や思いをしっかりと捉えるためにも、読んでもらいたい本です。