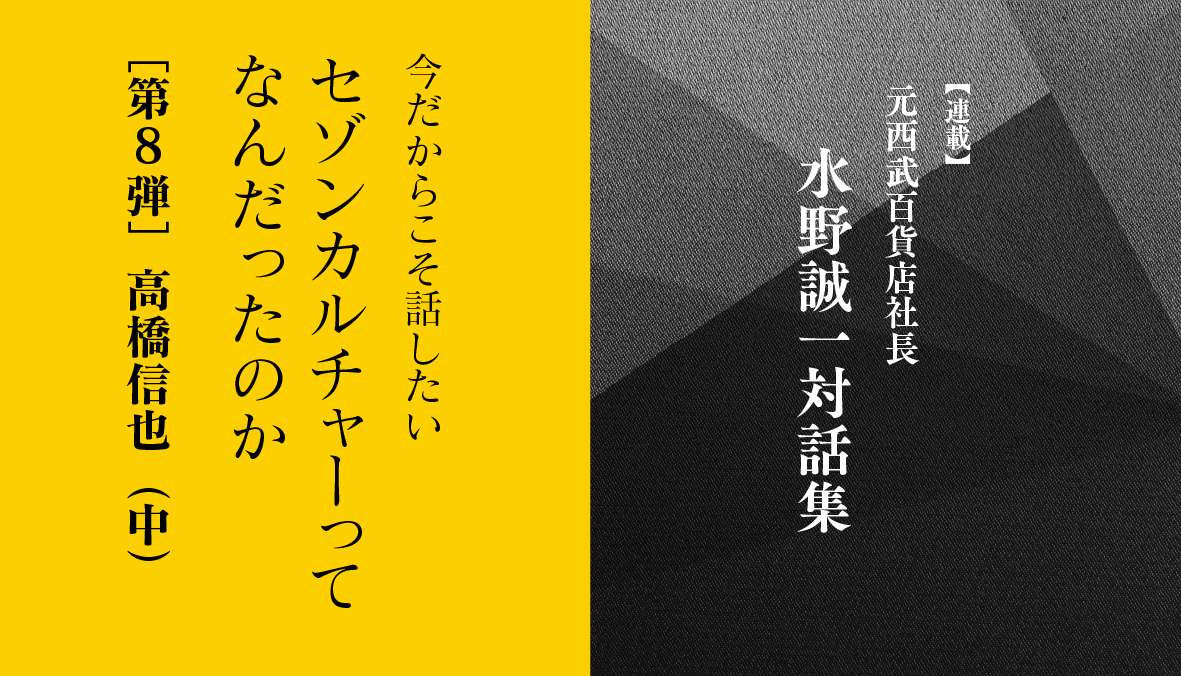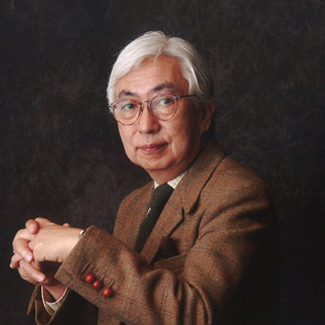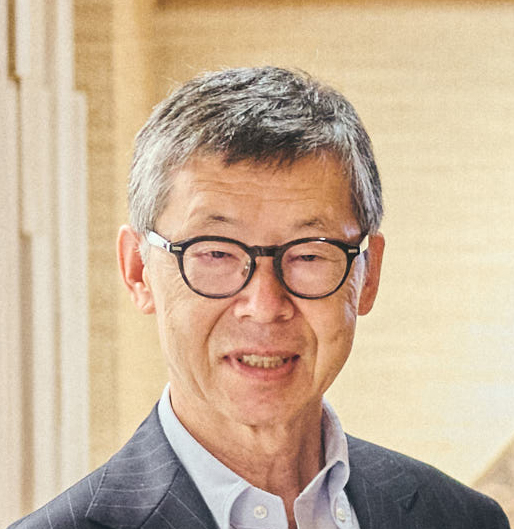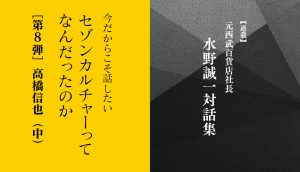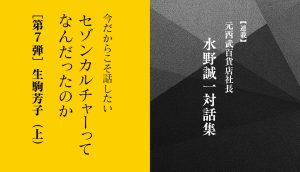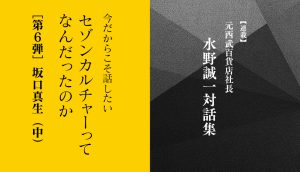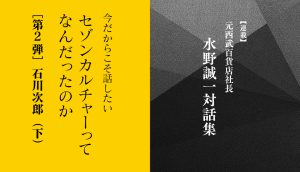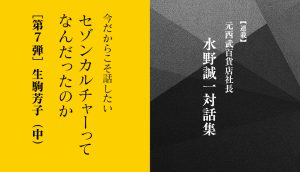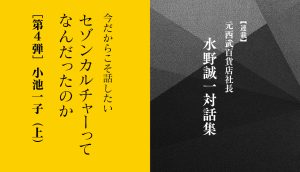堤清二が精魂込めた西武美術館が開館したのは、1975年。西武百貨店の社員として携わった水野誠一と、その美術館の洋書店・アールヴィヴァンにいた高橋信也。今や日本の美術界を牽引する一人である高橋も、やがて社長となる水野も、堤清二とアートの関わりを見つめ続けていた。対談の中編は、西武美術館の全盛とその終焉までが語られる。

音楽、ダンス、美術をすべて取り込むアーティストの招聘
水野 アールヴィヴァンとともに、西武美術館がスタートしました。そこに日本の美術史に残る素晴らしいコレクションが世界から集まるわけですが。
高橋 開館に寄せた堤さんの文章がそれは素晴らしいものでした。
要約すると、これまでの日本人は美術を勉強するものとして捉えていた。そうではなく、今感じていることを今表現するという人たちが、次々に塗り換えていく美術館であってほしい、と。そのためには、美術館というものは一般的に主張があるかもしれないけど、そのことを顧慮する必要はないと。
そういう意味で、あの時代、アートの精神の拠点になればいいというのが堤さんの想いだったんでしょうね。
水野 彼は文化というものを、ある意味において、生活のなかのひとつの側面として捉えているんです。何か金科玉条として飾ったようなものがアートだとか文化だとかは彼は思っていない。
高橋 そうですね。堤さんが最初に宣言されたのは「ルーブルとか大英博物館などの大美術館は、大航海時代に収奪してきたものでできている。でも、アートとはそういうものではないんだ」ということでした。「では現在、日本という成熟した社会でどういう美術があり得るのか」と。
しかもそんなことを書いておられる割には、当初の西武美術館のコンテンツ内容というのは、オーソドックスなんですよ。非常に正統派だった。
水野 でもマルセル・デュシャンやジャスパー・ジョーンズは普通の美術館ではできなかったでしょう。感性として考えられなかったと思いますよ。
高橋 マルセル・デュシャンは当時、世界的にブームになっていました。そのきっかけはポンピドゥー・センター(Centre Pompidou)が開館のときに大回顧展を実施していたことです。
ところが、これには大きな意味があって、マース・カニングハムとジャスパー・ジョーンズと、ジョン・ケージは、自称デュシャンの弟子なんです。
つまり、音楽もダンスも美術も当時の前衛は、ある意味でマルセル・デュシャンが根源なんです。ジャンルを横断した文化が、マルセル・デュシャンというハブによって成り立っていた状況だったんですね。
水野 それだけのことが出来たアーティストというのは、いないよね。
高橋 はい。結局、デュシャンが死んで、ケージが死んで、カニングハムが死んで、結局またそれぞれの分野に分断されてしまった。そういう意味では、デュシャンがいたから、パリからニューヨークへとアートの拠点も移った。
水野 デュシャンはいわゆる総合プロデューサー的なアーティストの始まりだったんですね。だから、それは昔ながらのパリを中心としたアートの世界とは、もう次元が違う。
それを堤清二は理解していたということだね。
高橋 そうなんです。デュシャンがキーパーソンになっていたということと、その後、堤さんが美術はもとより、出版も映画も音楽もおやりになっていくこととはリンクするんですよ、確実に。
80年代に広げていくプログラムの淵源がデュシャンで、その後も革新的なことがいくつかあるんですね。

5ヵ年計画でロシア・アバンギャルドを引っ張り出す
水野 当時は革新的なアーティストを次々と呼んできましたね。
高橋 そのひとりがまず 、ヨーゼフ・ボイスです。当時”パフォーマンス”という言葉が世の中に成立したのはボイスがいたからです。ボイスは、日本の文化庁が呼ぼうとしたりもしたんだけれど、 二度すっぽかされた経緯があり、大方は日本には来てくれないだろうと。
ところが、セゾンには来たんですよね!セゾンに来て、オープニングでパフォーマンスをやったんです。
水野 憶えてますよ。それと僕がびっくりしたのは、ジャスパー・ジョーンズがコレクションになっている「ターゲット」の1枚を堤清二のために書いてくれたことですね。
もうひとつ、それ以上にすごいと思ったのは、ロシア・アバンギャルドですよ。
最初はロシア・アバンギャルドって何なんだ?と、僕もさすがに一瞬目が点になりました。
高橋 ロシア・アバンギャルドって、当時、ロシア本国では不名誉なものとして隠蔽されている美術分野だったんですよ。
西側に出ているのは、コスタキス・コレクション。それから西海岸のロサンゼルス・カウンティ美術館(LACMA)で中規模な展覧会があった。その程度なんです。
ロシア革命前後の美術ですね。ともかく抽象表現が美術史上、最初に現れたと言われているんだけれど、運動の奥行きや所在もわからないし、国に隠蔽されて見ることもできないものだったわけです。
僕は、堤さんがこれをどういうふうに追っかけられていたのか、今までわからなかったんだけど、堤さんの著書の中に秘密が書かれていました。
水野 それは興味深い話ですね。
高橋 「文化 5ヵ年計画」としてソ連に働きかけて、と考えておられたようです。それはまず端緒として「呼び水」的に「草原の美人展」などをやって、最後に「ロシア・アバンギャルド」を引っ張り出すという戦略でした。
ソ連に行かれた折、「その後、僕はモスクワの学芸員と話をしていて、ロシア・アバンギャルドのアーティストについてどうかと尋ねると『あれは美術じゃないんだ』と、言下に言った。けれども『好きでしょうがない』という表情もありありと現れた。」
つまり、表面は否定しているけれど、本当はとても大事だというのが、ありありと汲み取れたというわけです。
水野 国家的には、否定されているものだから、学芸員としては非常に辛い立場ですね。
ロシアというのは、かつてヨーロッパの中心地だったわけですよ。だから当時の認められない状況にはすごいコンプレックスがある。だけど、だからこそ、そういうアバンキャルドが生まれた。それを個人的に評価した堤清二という人はすごい見識ですよ。
高橋 とんでもないと思います。しかもその「文化 5か年計画」とかいって、呼び水の展覧会を引き受けておいて、「ロシア・アバンギャルド展」をもってきたのですから。
その画集とか写真とかは、当時、わりと流布していて他で見ることが出来たのですが、作品が大きいのか小さいのかがわからないんです。ところが、それら代表作の現物がポンと池袋に来ていた。名だたる作品が全部この 2回のロシア・アバンギャルド展に入っていました。
水野 結局、その頃は日本国内でその意味が分かった人っていうのは、非常に限定的だったね。専門家はわかっていただろうけれど、一般のお客さまはわからない。
海外での評価はそれなりにあったでしょうけどね。
高橋 もちろん、海外では評価されていました。
ロシア・アバンギャルド展は西武美術館で 2回やっているんですが、もう 二度と出来ない。本当に堤さんがいた、その時期しか成立していないんですよね。
水野 本当に残念なのは、そういう展覧会を何らかの形で立体的な記録として残せていないじゃない。
高橋 カタログだけですね。
水野 本当に今こそね。そういうのを復元して見せたいですね。

文化は積み上げるのに何十年もかかるが、壊すのは一瞬である
水野 西武美術館というのは、あるところまでは非常に順調にやってきたんだけれど、バブル崩壊の影響を受けて、1999年に閉館してしまいました。それと同時に洋書を販売していたアールヴィヴァンも閉店すると。この間、あなたのインタビューで見たんだけど、西武の幹部に呼ばれて「うちは文化はもうやらないから、アールヴィヴァンはグループから出て行ってほしい」と言われたと。
それを僕はもう本当にとんでもないことだと思っていて。西武のやってきた文化っていうのは、バブルとかそういうものとは関係がない。自ら緻密に積み上げてきた文化じゃないですか。「もう文化やらない」というひと言で終わらせようとしたなんてあまりに横暴ですよ。
文化というのは積み上げなのにね。たとえ現代美術だろうが、現代文化であろうが、積み上げるのに 30年や 40年かかるけど、壊すのは一瞬です。まさに一瞬で壊されました。それは西武にとって本当に悲劇だった。
西武がやろうとしていた文化の芽は、そのとき確かに摘まれてしまったけれど、でも幸いなことは、だからと言って種まで消えてなくなったわけじゃないということ。
今まで撒いてきた種さえ残っていれば、確実にいつかまた発芽するだろうから。
しかしそこはともかくとして、それで芦野が西武から離れて、ナディッフ(NADiff)をやりたいという話が出てきた。そのあたりも高橋さんが苦労したと思うんですよ。
高橋 いえいえ、まあ。…
水野 僕はそのとき、一瞬にして西武の文化の芽を摘んだ幹部は堤清二に対して全面否定だから、西武を離れた後も気をつけろと、芦野にアドバイスしました。彼はちょっとそれでヘソを曲げたかもしなかったけど(笑)。
高橋 いや、実はわかっていたんじゃないでしょうか。結局 1年間、芦野さんは経営に名を連ねませんでしたね。ナディッフは、カンバセーションの芳賀さんに社長を頼んで、私が専務させてもらうことになりました。
水野 僕の忠告は受けてくれたんですね。あの余波はいろいろありました。
その後、高橋さんは村上隆さんや奈良美智さんら、世界に打ち出せるアーティストを育てていった。その話をゆっくり聞きたいですね。
撮影 谷口大輔 Instagram:@tanig_ph
構成:森綾 http://moriaya.jp/