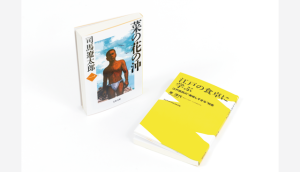海藻はまだまだ手つかず、だけど可能性を秘めた領域。日本全国の陸と海で海藻の養殖を実践する『シーベジタブル』が、「海藻で人も地域も元気にしたい」という思いで邁進し、挑戦をし続けている理由とは?
青のりの全国的不作を背景に、 唯一無二の養殖技術で起業。
「海藻の養殖は、どれだけ光を多く当てさせるかというゲームみたいなもの。うまくいくと1週間で10倍になるほどの速度で成長するんです」というのは、『シーベジタブル』のもうひとりの共同代表・蜂谷潤さん。高知大学大学院で海藻の種苗生産などを研究してきた蜂谷さんは、海藻を陸上で養殖する技術を開発。2016年、友廣さんとともに『シーベジタブル』を設立し、試行錯誤をしてビジネスとしての軌道に乗せた。
とはいえ、当初、蜂谷さんが行っていたのは、トコブシという巻貝を養殖する餌としての青のり養殖だった。かつて高知県の室戸市の名産品だったトコブシをもう一度復活させたいと考えた蜂谷さんは、トコブシと海藻の複合養殖モデルを考え、当時友人であった友廣さんに相談した。友廣さんは、ファーマーズマーケット『すみだ青空市ヤッチャバ』を始めるなど、ビジネスプランのスキルや経験をもっていたからだ。友廣さんを含め多くの人のアドバイスを受け、ブラッシュアップを重ねた結果、10年に開催された学生ビジネスプランコンテストで最優秀賞を受賞。13年には『うみ路』を設立して、海藻やトコブシの陸上養殖の研究開発を行うと同時に水産加工品の販売、高知県の食材を紹介するイベントなどを開催していた。
青のりの生産量が全国的に激減したのはそうした時期だった。これまで主要生産地だった四万十川や吉野川河口付近の海水温上昇にともない、16年から収穫量が減り続け、19年には15年の5分の1まで落ち込んでいた。供給量が足ない状況で、スジアオノリの養殖技術をもっている蜂谷さんたちに、お好み焼きやポテトチップスの生産をする会社から「トコブシの餌をつくっている場合じゃないよ」と熱烈な生産要請の声がかかった。切望されているのを感じたふたりは、融資などの資金調達を行って16年に『シーベジタブル』を設立。最初の陸上養殖施設を室戸市につくった。この時点で、スジアオノリを安定供給できる技術を開発していた『シーベジタブル』は、現在、岩手県陸前高田市、三重県尾鷲市、愛媛県今治市、熊本県天草市などに生産拠点をもち、多くのスタッフが働いている。
日本の海で急激に起きている、 海藻の消失を目の当たりに。
友廣さんは言う。「ここ数年、蜂谷と新井さんと日本中の海を潜ったんです。一年のうち200日以上、海に潜っている新井さんが『海藻がたくさん生えてきれい』と案内してくれた海に行ってみると、海藻が一本も生えていない。そんなところをいくつも目の当たりにしました。今、海ではこうした変化が急激に起きているんです」。原因はアイゴなどの魚やウニによる食害。海水温上昇により、アイゴが年間を通して生息できるようになったことに加え、魚の活性があがる水温の時期が延びたからだと考えられている。
海藻は海の揺籠。海藻を食べる魚はそれほど多くないが、魚の隠れ場所になり、海藻の表面についた微生物を食べに小さいエビなどがやってくる。そして、そのエビを食べに魚が集まる。海藻が増えると魚が増えて、海藻が減ると魚が少なくなる。幼少期に、地元・岡山県内の海で釣りをしたり泳いだりしていた蜂谷さんは、そのことを実感していた。高知大学で栽培漁業学科を選択したのは「海の生き物が増えたらいいな」という思いがあった。
沿岸部海域の海藻が生える区域「藻場」を回復させる対策は、海に潜ってウニを叩いて潰したり、網で覆って魚が入ってこない海域をつくるなどの取り組みが行われている。しかし、人が手を入れ続けるためには、経済としてもまわしていく必要があると蜂谷さんは感じている。
陸上養殖
漁師さんとともに 全国の海で海藻を養殖。
ただし、需要がある海藻はそれほどないから、これまでの海面養殖は、ワカメ、コンブ、ノリ、モズクくらい。これらが育たない海域の海面はがらがらに空いている。そのため『シーベジタブル』では、どの海域でどういう海藻が、どの季節に育つかを1年半ほど前から試験している。「海藻は日本だけでも1500種類以上はあるのに、日常的に食べているのは10種類にも満たない。僕でさえ100種類ほどしか食べてない。もったいないですよね」と蜂谷さん。
天草の海での海面養殖を担当する『シーベジタブル』の富崎凜さんと丸山拓人さんの案内で海上養殖の現場へ行き、さまざまな海藻を食べると、それぞれに甘み、苦み、旨みがあって、食感も全然違う。当たり前のことだが、海藻にも味や個性があることを発見した。しかも、形や色など、目にも楽しい。こうした海藻が流通したら、食卓が賑やかになってさぞかし素敵だろう。
海面養殖は地元の漁師さんの協力なしには成り立たないという。そして、経済的に回していかないと続かないと考えた『シーベジタブル』は、東京にテストキッチンを開設。メニューや商品開発、海藻を原料にした発酵調味料を試作するなど、日々海藻のおいしさを探究し、調理方法とともに海藻の可能性と魅力を発信している。「海藻の養殖と同時に、食文化を広げて”出口“もつくっていきたい。おいしい、楽しいというポジティブさで状況を変えていけたら」と友廣さんは考える。
食文化が変わると、海が変わる。私たちが、海面養殖されたいろいろな種類の海藻を食べることで、漁師さんの新たな仕事をつくれるし、海の生態系も少しずつだがよくなっていく。海藻はまだまだ可能性にあふれている。
海面養殖
『シーベジタブル』の商品例!
そのまま干した すじあおのり
そのまま干した はばのり
塩蔵 とさかのり
記事は雑誌ソトコト2022年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。