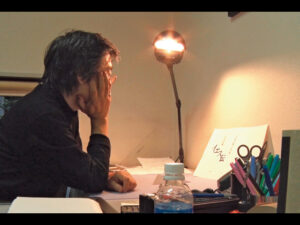アメリカに亡命したユダヤ系ポーランド人作家のイェジー・コシンスキが1965年に発表、故郷・ポーランドでは発禁となったいわくつきの書『ペインティッド・バード』。ヴァーツラフ・マルホウル監督が11年の歳月をかけて製作した映画『異端の鳥』は、ホロコーストを逃れて疎開した少年が、預けられた先の老婆の不慮の死を機に余儀なくされた、帰還のための非情な道行きを、9つの章を通じて描いてゆく。
両親のもとへ帰るため、老婆の家を発った少年は、行く先々で誹謗中傷に晒される。村人が少年を悪魔呼ばわりするのは、彼が、金髪で色白の彼らとは異なる容貌(黒い髪と瞳、オリーブ色の肌)であるからで、暴力の理由はそれ以上でも以下でもない。
村人に袋叩きに遭っていた少年を金で買った呪い師・オルガに始まり、生き延びるために転々とする彼は、立ち現れる大人たちに翻弄され続ける。実際、自分の肉体がいたぶられることはなくても、少年の目の前では、憎悪や欲望、集団ヒステリーによって、正視に耐えない暴力が振るわれる。
自分の妻と作男の関係を疑うあまり、作男の目を刳り貫く被害妄想の夫。その後、身を寄せた鳥売りの男のもとでは、彼の奔放な愛人に自分たちの息子がたぶらかされたと激昂した女たちが、リンチの末に彼女を死へと至らしめ、愛人の死にショックを受けた鳥売りも、みずから死を選ぶ。
ドイツ軍の兵士の射殺を免れ、教会で司祭に救われたのも束の間、少年は自分を引き取った男に凌辱され、その後も、鳥売りの愛人のようなニンフォマニアの女の欲求に”応じられない“ことで蔑まれる。
森の木立、草原、広大な空、河原の葦の茂み、雪原、鳥小屋、家畜小屋……。モノクロームの風景の完璧なまでの美しさと、自分たちとは異なるものへの敵意を露わにする人間の、野生動物のような獰猛さ(などというのは、野生動物に失礼か)。そのコントラストに、言葉を失う。
生き延びたことは、本当に救いだったのだろうか。感情を読みにくい、黒目がちの瞳で大人を凝視する少年の目は、不意にガラス玉のように空ろになる。いくつもの生き地獄をくぐり抜けてきた少年は、恐怖を克服するため、暴力に麻痺しなければ、生き延びることは難しかったのかもしれない。
きっとみんなもそう思っている。だから(何をしても)かまわないだろう。慣習のなかで生きる人々は、そこから外れる者をほとんど無自覚に、異物と見なしている。だが、思考停止状態で発動される、閉鎖環境下での暴力は、誰もが犯しかねない過ちではないか。見る者にそんな自戒を促す作品でもある。
『異端の鳥』
10月9日(金)より、TOHOシネマズシャンテほか、全国順次公開
公式サイトはこちら