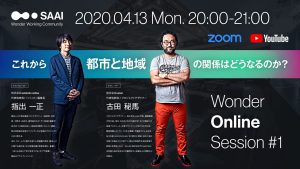ソーシャルでエシカルな関心をもつ人を惹きつける、街の中に広がる学びの場「ソーシャル系大学」。今回は、東京都世田谷区にある本物の大学、東京農業大学が手がける体験型人材教育プログラム「多摩川源流大学」を訪問した。多摩川源流大学は、多摩川の源流域のひとつである山梨県・小菅村を学びの場として、2007年に発足したプロジェクトである。今回は東京農業大学「食と農」の博物館で行われた講座を訪れた。
多摩川を介して、つながる自然を感じた一日。
東京農業大学が研究成果を発信する「食と農」の博物館は、レストランや温室を併設するモダンな建物である。2階のセミナー室で開催された今回の多摩川源流大学のテーマは、「食べ比べ3本勝負」というプログラムのうちのひとつ「ヤマメvsイワナvsニジマス」。山梨県・小菅村からその日の朝に運ばれてきたヤマメ、イワナ、そしてニジマスの実物を前に、清流に棲む川魚としてよく知られる魚種の違いを、見て、触って、食べて理解しよう、という内容である。

プレゼンテーションを担当するのは、山梨県・小菅村にあるNPO法人『多摩源流こすげ』の福本美穂さん、源流大学のスタッフ・矢野加奈子さん、東京農業大学非常勤講師の地主恵亮さんの3名である。小さな虫を上品についばむ清流の女王・ヤマメ、ねずみを丸呑みすることもある意外にワイルドなイワナ、故郷はアメリカの外来種ながら日本各地の渓流に生息するニジマス。

熱のこもった話に何度も笑いが起こる。参加していた小学生たちも、イワナの歯がぎざぎざしていることを発見したり、ヤマメの皮が思ったよりぬるぬるしていると声を上げる。

そしていよいよ実食。3種の塩焼きを、ブラインドテストの要領で噛みしめるが、味の違いを見極めるのは簡単ではない。講座の途中、元・小菅村役場の職員で漁協にも勤めていた加藤源久さんが、川魚の生態を詳細に教えてくださった。小菅村ではヤマメの養殖を昭和42年から始めたこと、それでも人怖じする性格が今でも変わらないということ、イワナの表面がぬるぬるしているのは浅瀬で移動するためで、ときどき蛇に間違える人もいるということ。この頃になると参加者同士もすっかり打ち解け、にぎやかな講座が終わる頃には、誰もが3種の見分け方をすっかりマスターしていた。

参加者には常連も多く、源流大学の講座があると聞くと遠くからでも駆けつける。受講生とスタッフはすっかり顔なじみで、小菅村に移住する若い世代も現れるなど、長い時間をかけて源流大学のまわりにはコミュニティが出来上がっている。水槽の魚たちを観察しながら、多摩川を介して、つながる自然を感じた一日だった。
多摩川源流大学
HP:http://genryudaigaku.com mail:info@genryudaigaku.com