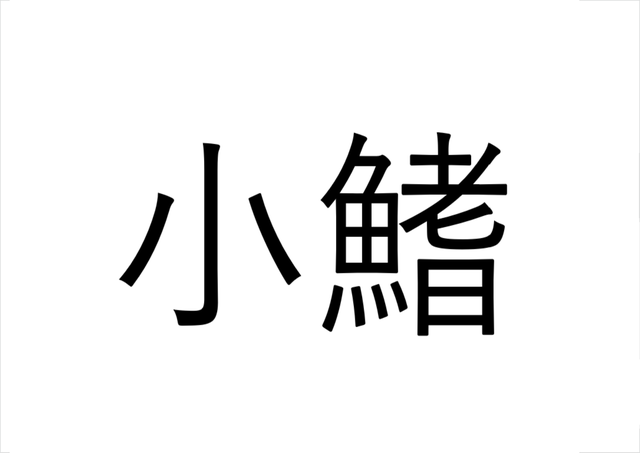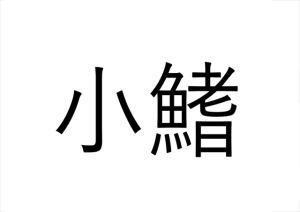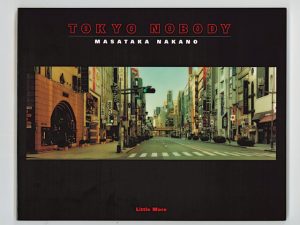読めそうで読めない、魚へんの漢字「小鰭」。見たことはあるものの、読み方がわからない人は少なくありません。そこで今回は「小鰭」の読み方をご紹介します。
「小鰭」なんて読む?
ヒント①:酢締めが定番
ヒント②:出世魚としても知られている
「小鰭」読み方の答え:こはだ
地域によって若魚の名前が異なるのも特徴です。ツナシ(関西地方)・ハビロ(佐賀県)・ドロクイ・ジャコ(高知県)などの呼び方があります。
語源
生態
「小鰭」の食べ方
また小鰭は職人泣かせの寿司種ともいわれています。独特の味があり水っぽさがある小鰭は、塩や酢の加減が難しく仕込みで職人の腕が分かるといわれているほどです。
寿司種以外では、「粟漬け」など酢に漬けてから加工したものが食べられています。「こはだの粟づけ」は、東京都の郷土料理としても有名です。縁起がよく、おせち料理として親しまれています。
また有明海で獲れる小鰭は脂乗りがよく、高く評価されているようです。有明海は九州北西部にある海で、福岡・佐賀・ 長崎・熊本の4県にまたがっています。佐賀県藤津郡太良町竹崎地区では、水揚げされた小鰭の多くが東京豊洲市場へ出荷されています。
小鰭(こはだ)の握り寿司。江戸前の代表的な寿司タネ。よく食べたくなるので、今年も定期的に買ってみる予定。自家製と既製品では味に極端な差がでるので、この魚は生から仕込むのが理想。今回は海塩を振り粕酢で〆たあと、一晩寝かせてから握ってある。本当に美味しい魚。#居酒屋明利 #コハダ pic.twitter.com/5TWTIfuntf
— 明利英司:寿司好き小説家 (@meirieiji) April 8, 2021