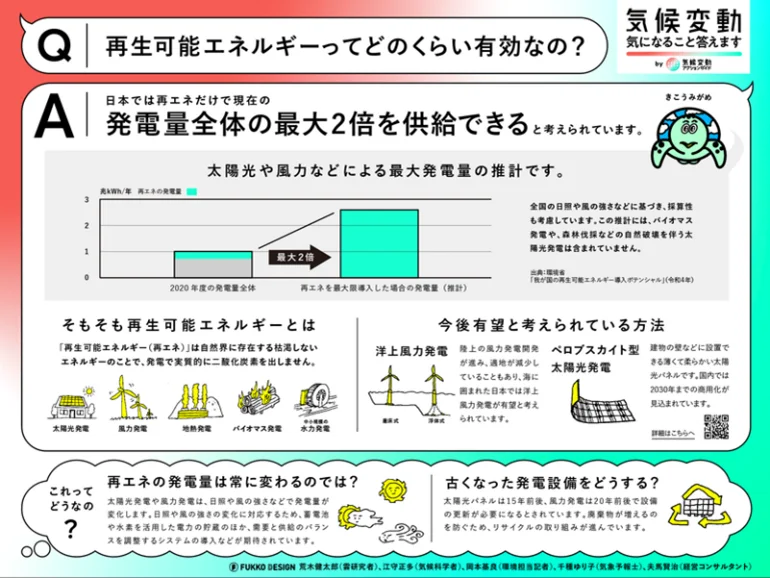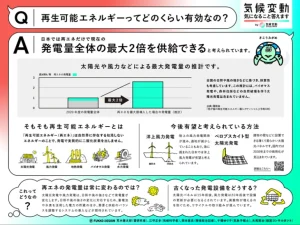国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、人間活動による温室効果ガス排出が主因の地球温暖化によって、極端な天候や異常気象の起こる頻度と深刻さが増していることを発表しています。世界25か国で危機的だと思う問題1位は「気候変動」となり、異常気象への懸念が高まる中、科学的根拠に基づいた新しい防災準備が求められています。
IPCCが警告する気候変動の現実
気候変動に関する科学で最も権威のある包括的な報告書を作成しているIPCCは、人間活動による温室効果ガス排出が主因の地球温暖化によって、極端な天候や異常気象の起こる頻度と深刻さが増していることを改めて発信しています。
異常な熱波、大規模な洪水や森林火災は、世界中の人々や自然、経済システムに悪影響を及ぼしており、気候変動への対策は急務とされています。公益財団法人旭硝子財団の調査でも、25か国全体で1位「気候変動」(37.5%)が危機的な状態にあると考えられており、各国で頻発化・深刻化する異常気象や異常気温を懸念する声が多数寄せられています。
異常気象の科学的メカニズム
近年話題となった「線状降水帯」をはじめ、災害をもたらす様々な気象現象のメカニズムが科学的に解明されています。2021年6月に気象庁が情報発表を開始した線状降水帯は、集中豪雨の原因となる現象で、同じ場所で数時間にわたって雨雲が次々と発生・発達を繰り返すことで発生します。
「ゲリラ豪雨」「台風」「竜巻」なども、気象学の発展により、そのメカニズムと予測可能性が向上。近年の夏の最高温度が毎年更新される現象や、春や秋が短くなる季節変化も、地球温暖化の影響として科学的に説明されています。
デジタルツインで可視化する災害リスク
TOPPANが開発した都市災害リスク可視化サービスは、3Dデジタル空間上に現実の都市を再現し、避難所などの防災関連施設や住人の分布と年齢構成といった地域情報を登録。災害発生時の状況によって変わる被害や避難行動を避難者の属性なども考慮した仮想再現を行い、どのような状況が起きるかを可視化します。
科学計算と地域情報に基づき様々な条件をデジタル空間で検討し、防災・減災活動に反映させることが可能となります。また、デジタルツイン内で起きた災害時の状況を地域防災計画などの行動ルールと組み合わせた訓練シナリオのAI生成も実現しています。
企業の気候変動リスク分析手法
NECが参画する気候変動レジリエンス強化協議会は、企業の気候変動リスク対応に役立つホワイトペーパー「民間企業の自然災害リスク分析・対策のアプローチ」を発行。気候変動の進行に伴い激甚化・頻発化する自然災害や異常気象などの物理的リスクに対し、企業の担当者が評価・対策を進める際の基本的な手順や留意点を整理しています。
物理的リスクには台風、洪水、干ばつ、熱波などが含まれ、企業はこれらのリスクに対応することで財務的損失を防ぎ、持続可能な経営を維持する必要があります。IoTやAIなどのデジタル技術を活用したリスク評価手法も開発されています。
適応ファイナンスと新たな防災投資
適応ファイナンスは気候変動の影響を低減する適応策の導入に際して必要な資金を調達するための手法の一つです。保険や債券、融資などの金融商品の提供により企業や自治体、政府の適応策の導入を推進します。
金融商品の提供においては、気候変動の影響に対するリスクを評価することが重要であり、IoTやAIなどのデジタル技術の活用が期待されています。共通の課題意識を持つ企業との連携により、気候変動への適応に資する新たな市場形成の可能性が模索されています。
科学的根拠に基づく警戒レベルの活用
2021年に気象庁が設定した新しい警戒レベルシステムは、科学的な気象予測技術の向上に基づいて構築されています。線状降水帯の予測精度向上により、従来よりも早い段階での避難判断が可能となりました。
特に「ふだんのそなえ」から「もしものときの対策」まで、段階的な対応が科学的に整理され、気象現象の発生メカニズムに基づいた効果的な防災行動指針が提供されています。
次世代防災教育のデジタル化
スマートフォンを活用した気象現象の観察システムにより、さまざまな気象現象を映像や3DCGで観察できる教育ツールが開発されています。空の高いところで起こる現象や、めったに見られない珍しい現象を間近で見ているかのように体感でき、科学的理解を深めることができます。
「ゲリラ豪雨」「台風」「竜巻」など近年話題の現象の貴重な映像も収録され、気象災害の最新情報を学習できる環境が整備されています。
気候変動時代の総合的防災戦略
気候変動時代の防災準備は、従来の経験則に頼った対策から、科学的データと予測技術に基づく戦略的アプローチへの転換が必要です。IPCCの報告書、気象庁の観測データ、デジタルツイン技術による被害予測、企業のリスク分析手法など、多層的な科学的根拠を活用した総合的な防災戦略が求められています。
個人レベルでは気象アプリやハザードマップの活用、企業レベルでは物理的リスク分析の実施、自治体レベルではデジタル技術を活用した災害対応システムの構築など、それぞれの立場で科学的根拠に基づいた準備を進めることが、気候変動時代を生き抜く鍵となります。