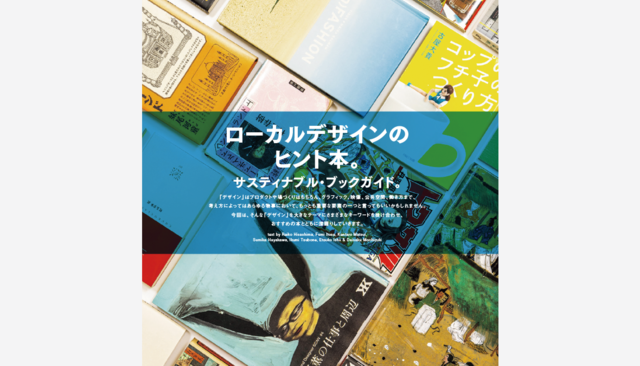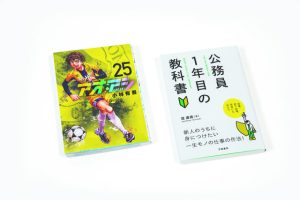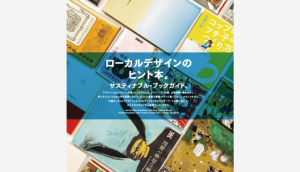『イトーキ』のデザイナーとして、大小問わず、話題になるオフィスデザイン設計で活躍する星幸佑さん。働く場が多様化する今、オフィスに欠かせないポイントや考えは何か?日本各地の“オフィスを考える人たち”とシェアしたい本を、ローカルデザインの視点でセレクトしてもらいました。
星 幸佑さんが選ぶ、オフィス×ローカルデザインのアイデア本5冊
たとえば、東日本大震災のとき、復興活動を円滑に進めるために「ゼッケン」をデザインして利用したケースがありました。ボランティアのメンバーが被災地へ行くと、現地には彼らをさばく人がいない。そうすると現場のみなさんの間で感情のぶつかり合いが起きます。この場を整理し、摩擦をなくすためのデザインとしてゼッケンが採用されたのですが、自分が誰で何ができるのか、胸に付けたゼッケンでアピールすることで、現場で働く人たちの性質が可視化され、作業の〟交通整理〝がスムーズになったというのです。
このような実例をオフィスのデザインに置き換えて考えると「誰でもわかる仕組み」を「誰でも受け入れられるデザイン」で再現するのは、なかなか難しいものです。でも、例に挙げた「ゼッケン」は誰もが知っていて、付ける側の人たちも違和感なく使える。心理的かつ仕組み的なデザインを落とし込んだこの例は、効率性や創造性が求められる現代のオフィスでも、有効な仕掛けのヒントになり得ると思います。
『プロセスエコノミー』で書かれている内容は、時代感として「今のオフィスづくりに求められることは何か?」を示唆しています。これまでのオフィスづくりは、トップダウンで進むことも少なくありませんでしが、最近はオフィスに「つながり」を付与し、愛着を持ってもらうという視点が大切になってきています。要するに「働きたくなるオフィスをつくる」ために、当事者たちにオフィスづくりのプロセスに関わってもらうことが非常に多くなってきているのです。
たとえば、地場産業のなかで生じた間伐材を使ったオフィス・インテリアを導入したり、家具や什器を一緒に選んだり、オフィスの壁を一緒にデザインしたりすると、ヒトとモノ(オフィス全体も含めて)との間にストーリーが生まれ、空間や地域への愛着も生まれると思います。こうした取り組みとプロセスは、会社からそこで働く人たちへ、わかりやすくてポジティブなアピールにもなるはずです。