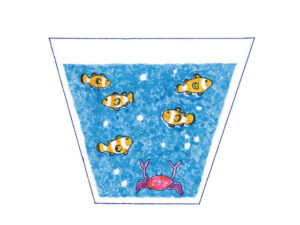もう遅い、ということについて考える。深夜の静けさの中、考える。深夜はいい。正直になれる気がする。まぁ、いつも正直ではあるけれど。
僕にとって今さらもう遅くて叶わないことは、「青い恋」の経験である。2つの未熟な精神と張りのある身体が重なって生まれる切実で甘美な恋。そういった経験を逃して僕は大人になった。同世代の友人たちが飲みの席で「若かった」と、過ぎた恋を語る時、僕はその引き出しに何も入っていなくて苦笑いばかりしている。彼らはどこか自慢げにビールを飲む気がするが、こういうのをひがみと言うのだろうか。
僕の10代はゲイであることを受け入れられないまま終わったし、まだ若いと言えた20代も部活や仕事に精を出しているうちに、もうすぐ終わりを迎えようとしている。今年の8月で僕は30歳になる。こんなにヘラヘラした自分がなっていいんだろうか、なんて思うが、問答無用でなってしまうわけで、なんだかすみません、という気分でいる。誕生日は一人で沖縄に行くことにした。海を見ながら、一人で静かにその時を迎える予定だが、そこに込み入った理由はなくて、たった一人で地球と対峙している間、主人公はどう考えても僕しかいないからいいなと思ったのだ。東京は自然には主人公になれない街だ。
話を戻すが、そんなわけで僕は、「青い恋」に耽溺するのがよく似合う数々の春を素通りしてしまって、「青さ」だけを身体の奥に秘めたまま、大人との恋の駆け引きをこなさねばならなくなってしまった。内心、大変だなぁといつも途方にくれている。つい先日デートした人には、帰り際「遊んだほうがいいよ」と言われ、「いや、遊びにきたんですけど……」と思った。暗中模索が続いてばかり。この先大丈夫なのだろうか。
そんなわけで不安ばかりなのだが、最近ある友人にこんなことを言われて、そんな自分もいいかな、と思ったりした。彼には友達が少ない。
「友達って難しくない? いつも皆と笑って過ごしてはいるけど、俺、友達なんてそんなにいないよ。恋愛は簡単じゃん。2回デートしていい感じなら3回目があって、3回目にセックスして、合えば付き合う。でも友達は3回飲みに行ったって、友達と思われているか分かんないじゃん」
まず「俺がいるだろうよ」と思ったが、それはさて置き、僕は自他ともに認める友達が多い人間で、こんな悩みをもったことがなかったから「考えすぎでしょ」とも言いそうになった。でもこういう時一番言っちゃいけないのが「考えすぎ」だと僕は知っている。そしてそれを教えてくれたのが僕の中で青黒く、硬くなってしまった「青さ」なのだ。人間みんな結局どこかが青い。自分の「青さ」を棚に上げて、誰かを笑うような人間に20代で仕上がらなかったのは、本当によかったと思う。
とはいえ僕はこれから、自分の「青さ」をゆっくり溶かしていく予定でいる。もしかしたら一発逆転、青さ爆発! みたいな恋もあるのかもしれないが、まぁ、まずないだろうと思う。
遅れてしまった何かを取り返すことは、時間を巻き戻さない限り正確に言えば無理で、これから僕が行く道は、決して平坦ではなく、どこか歪なものになっていくだろう。だけどその歪さが、不格好さが、僕の人間としてのコクをつくるのだと思う。考えすぎるほどに大人になった僕の目だけにとまる恋の光とか、もっと言えば新たな生きる意味の芽吹きとか、そういうものがあるはずだし、それはきっと、瑞々しいと言っていい何かだ。だから「遅れたことも悪くないよね、余裕じゃん」、そう僕は言っていたい。
20代、辛かった。でも本当に楽しかった。悔いは微塵もない。30代は恋をして、仕事も頑張ってもっと素敵な自分になろうと思う。今は何もかも分からないことばかりだけど、とにかく毎度言っているが、僕はもっと幸せになる。それだけが決まっている。