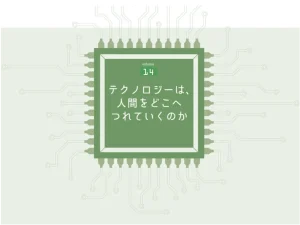2016年のノーベル医学・生理学賞は、日本人研究者・大隅良典氏のオートファジー研究に対する貢献に対して授与された。
今回は、これまでの本コラムのストーリーからちょっと離れて、この話題を論じてみたい。
ここ数年来、次々と日本人がノーベル賞に輝くことが続いた(忘れっぽい人のために列記すると、12年は、iPS細胞の開発で、山中伸弥氏が医学・生理学賞、14年は、青色ダイオードの発明により、赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏に物理学賞、15年は、寄生虫病薬の開発で、大村智氏に医学・生理学賞、ニュートリノ研究で、梶田隆章氏に物理学賞)ので、今回も大きなニュースになった。日本人がノーベル賞をとると、テレビは特別番組、新聞は号外が出て、お祭り騒ぎになる(片や、専門家しか知らない外国人が受賞すると、その研究がどれほど価値があるものであっても、一気に熱が冷め、記事もごく小さいものにしかならない。今年の物理学賞、化学賞がそうだった。)「日本人受賞を逃す」というヘッドラインを流した社もあったほどだ。これではまるでオリンピックのメダル競争と同じである(私自身も新聞社の依頼で、緊急座談会などに参加してお祭りの片棒を担いだので、これは自戒を込めて言っている)。
そしてお祭り騒ぎの内容はといえば、研究自体はごく大雑把にしか説明されず、むしろ受賞者の人となりや家族の支え、昔の同級生の証言といった人情話ばかりになる。結局、大隅先生は実はお酒が大好き、みたいな印象しか残らない。
そこで、ここではオートファジー研究の意義についてあらためて考えたい。生命科学研究の本質は「薬の開発や病気の治療に役立つ」といった実用的な成果ではなく「生命とは何か」という根源的な問いに対する答えの一端が明らかにされたということである。一言でいえば「生命は、つくることよりも、壊すことを一生懸命行っている」ということになる。
そのために少し過去を振り返っておこう。
2004年のノーベル化学賞は、A・チカノーバー、A・ハーシュコ、I・ローズ、3人の研究者に与えられた。ユビキチンシステムと呼ばれる細胞内タンパク質分解のしくみを解明したことが評価された。ノーベル賞講演の冒頭、チカノーバーは、おもむろにルドルフ・シェーンハイマーから話しはじめた。私は密かに快哉を叫んだ。私にとって、シェーンハイマーはヒーローだが、若くして謎の自殺を遂げ、科学史的には半ば忘れ去られた存在だったからである。シェーンハイマーは、ナチス・ドイツから亡命、1930年代から1940年代にかけて米国ニューヨークのコロンビア大学で研究を行った。
シェーンハイマーは、同位体を使って生体物質の動きを可視化し、私たち生物が食べものを摂取することの意味を問い直した。一般に、生物にとって食べものとは、自動車にとってのガソリンと同じ。つまりエネルギー源だと考えられていた(今もそう捉えている人は多い)。
しかし実はそうではない。確かに食物(主に炭水化物)はエネルギー源として燃やされる部分もあるが、タンパク質は違う。私たちが毎日、タンパク質を食物として摂取しなければならないのは、自分自身の身体を日々、作りなおすためである。シェーンハイマーはこの事実を鮮やかな実験で初めて示した。
たとえば私たちの消化管の細胞はたった2、3日で作り替えられている。1年も経つと、昨年、私を形作っていた物質はほとんどが入れ替えられ、現在の私は物質的には別人となっているのだ。つまり、生命は絶え間のない分子と原子の流れの中に、危ういバランスとしてある。私が自らの生命論のキーワードとしている「動的平衡」である。それまで静的なものとして捉えられてきた生命観に、シェーンハイマーは、新しいパラダイムシフトをもたらしたのだ。
動的平衡の流れを作り出すためには、作る以上に壊すことが必要である。それゆえ細胞は一心不乱に物質を分解している。チカノーバーたちは、シェーンハイマーの遺志を継いで、壊すことの重要性を明らかにしたのだった。
生命にとって重要なのは、作ることよりも、壊すことである。細胞はどんな環境でも、いかなる状況でも、壊すことをやめない。むしろ進んで、エネルギーを使って、積極的に、先回りして、細胞内の構造物をどんどん壊している。なぜか。生命の動的平衡を維持するためである。
秩序あるものは必ず、秩序が乱れる方向に動く。宇宙の大原則、エントロピー増大の法則である。この世界において、もっとも秩序あるものは生命体だ。生命体にもエントロピー増大の法則が容赦なく襲いかかり、常に、酸化、変性、老廃物が発生する。これを絶え間なく排除しなければ、新しい秩序を作り出すことができない。そのために絶えず、自らを分解しつつ、同時に再構築するという危ういバランスと流れが必要なのだ。これが生きていること、つまり動的平衡である。
このパラダイムシフトに新しい潮流が加わった。細胞にはさらに巧妙で大規模な分解システムが備わっていた。それが大隅良典氏のオートファジー研究である。
オートファジーとは自食作用のこと。細胞内にはミトコンドリアや輸送小胞など構造体がある。細胞は特殊な膜によってこれらの構造物を取り囲み、隔離してしまう。隔離したあと、この区画に酵素を送り込んで(この酵素が貯蔵されている小器官をリソソームという)、あっという間に構造体を分解してしまうのである。分解産物はリサイクルされたり、排泄されたりする。つまりエントロピーが捨てられている。大隅チームは酵母という微生物をモデルに使って、オートファジーのメカニズムを詳細に明らかにしたのだ。ユビキチンに続いて、オートファジー研究が、ノーベル賞に輝いたのは、シェーンハイマーから連綿と続く生命科学の系譜から見ると、当然の帰結といえる。