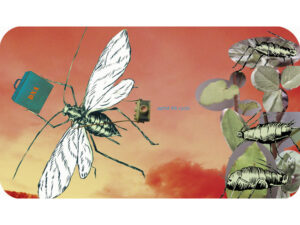私の好きな画家は何をおいてもフェルメールなのだが、ほかには? と聞かれれば、ぜひ葛飾北斎の名を挙げたい。フェルメールと北斎とはもちろん、時代も場所も画風も違う。でも共通項がある。ちょうどこの夏に葛飾北斎のリ・クリエイト展を企画しているので、このコラムの特別編として北斎について語るのをお許しいただきたい。
葛飾北斎は画家に生まれるべくして生まれ、画家になることを、一生を懸けて求道した。生まれたのは江戸時代半ばの1760年(宝暦10年)のことだから、フェルメールの没後、85年目のことである。北斎は画家としての自分を生涯、決して完成したものとは見なしていなかった。求道、と書いたのはそのような意味である。北斎は、74歳のとき「富嶽百景」を出版した。その跋文で次のように記している。「己六才より物の形状を写の癖ありて半百の此より数々画図を顕すといえども七十年前画く所は実に取るに足ものなし」。すなわち、自分は、幼少の頃から絵を描くのが大好きで、以来50年あまり、ずいぶんとたくさんの絵や本を出してきたが、70歳以前に描いたものの中には取るに足るものは何もない、というのである。そして90歳を迎える直前にはこんな風に吐露している。「天我をして五年の命を保たしめば 真正の画工となるを得べし」。天がせめてあと5年寿命を与えてくれたなら、わたしは真の画家となることができただろうに、と。そう言って彼はこの世を去った。
自らの画業完遂に対するこのあくなき追究の熱度と、冷徹なまでの自己懐疑の深さはいかばかりだろうか。何回も転居を繰り返し、幾度も名前を変え、あらゆる絵を描き続けた北斎。彼はいつも渇いていた。決して自らの芸術に満足することなく、絶えず学び続け、常に可能性を追究しつづけた。このストイックな求道精神は、私の愛する17世紀の“光の魔術師”、ヨハネス・フェルメールの衣鉢を継ぐものといってもよい。フェルメールは光の粒立ちをひとつ残らず捉えようとした。あるいは振り返ろうとする少女の表情のゆらぎと眼差しの震えを写し取ろうとした。北斎は、流れ落ちる滝を、赤く染まる富士山の際の風にたなびくうろこ雲の流れを、あるいは逆立つ大波の今、まさに砕け散るその瞬間を描き切ろうとした。つまり彼らが求めていたことはまったく同じなのである。移ろい変わりゆく光と影、流れゆく波や雲、あるいは一瞬たりとも立ち止まることのない自分の人生、これら動的なものを、本来的には動くことのできない絵画の中になんとか表現しようと努力し続けること。流れゆく命をとらえること。つまり、生命潮流の中に自らを投じ、そのまま生命を内側から描き出そうとした。
フェルメールと北斎には、もうひとつ極めて興味深い共通項がある。それは青への希求だ。青は不思議な色である。青は自然界のどこにでもある。空の青、水の青、遠い山の青。しかしその青は取り出して持ち帰ることができない。空気を集めても、水をすくっても、そこには青はなく、またその青で布を染めたり、色を塗ったりすることができない。でも青は限りなく美しい色である。青に美を感じるのは、おそらく世界が始まったとき、青は生命に必要な色だったからに違いない。澄んだ空は陽の光を保証し、清浄な空気を約束した。遠くに光る青は、水源を意味した。生命はそれを求め、求めるべきよきものを美しいと感じた。
美の起源は生命と密接に関連している。それゆえ、芸術家たちも、いかに美しい青を画面に描き出すかに腐心した。しかし古来、青い色を発する染料や顔料は限られていた。確かに、藍(インディゴ)は布を青く染めることができたが、藍染めには複雑な工程を要し、それは画材としては不適格だった。フェルメールは、少女の青いターバンを描き出すために、高価な宝石であるラピスラズリを削って青い粉を調整した。しかしその青は水には溶けず、にじませることや薄めることはできなかった。北斎の時代になってはじめて、プルシアンブルーという青い顔料が生み出された。この青は濃淡を描き出すことができた。存在をいち早く知った北斎は、この青を使って暮れなずむ空の青いグラデーションを見事に描き出すことに成功した。芸術の歴史は青に対する文化史だったといってもよい。
私からみなさんに新しい芸術鑑賞の仕方のご提案をしたい。絵の本質は、周りを額で囲まれた四角の中にあるのではない。むしろ四角いフレームに囲まれた絵と絵の「あいだ」にこそある。デジタル技術によって名だたる芸術家の作品を再現したリ・クリエイト・アートは、単なる複製あるいはコピーではない。芸術家の作品群を、彼の生きた時間軸に沿って整列させ、芸術作品の「あいだ」、つまり「文脈」を浮かび上がらせる試みなのである。このとき初めて画家の人生の生命潮流の全体が浮かび上がってくる。
北斎の作品群を一堂に集めることによって立ち上がってくる彼の躍動感と潮流。それと同時に絵の細部に宿る彼の試行錯誤や苦悩、そして渇望。北斎は自分の画業に決して満足することがなかった。しかし北斎は芸術に対する希求を決して諦めることもなかった。常に学ぼうとした。どんなに年を重ねても、何か始めることが遅すぎることはないことを知っていた。北斎は私たちを今もなお鼓舞し続けてくれる。この躍動感をぜひ感じてほしい。
今回の北斎展では、ちょっとした謎掛けをしてみた。かの北斎が「令和」の到来を予言していた!? というものである。ぜひお楽しみに。