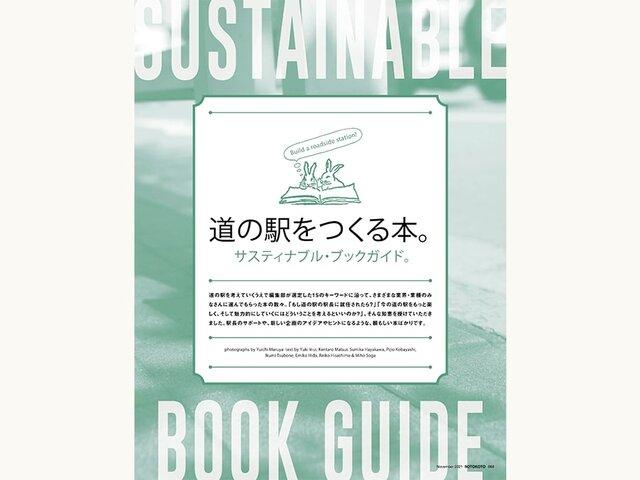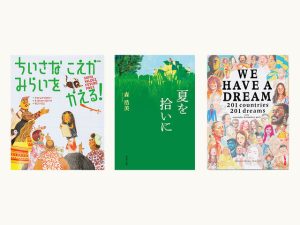白倉正子さんが選ぶ、道の駅をつくる本5冊
ただ、道の駅のトイレをメインテーマに書かれた本は見つかりませんでした。そこで、トイレ全般について書かれた本のエッセンスを道の駅のトイレの考え方やつくり方に反映できればと思い、5冊を紹介いたします。
1冊目は、私も運営委員を務める『日本トイレ協会』の副会長の山本耕平さんが書かれた『トイレがつくるユニバーサルなまち』です。山本さんは、「自治体のトイレ担当者のために書きました」とおっしゃっていました。公共トイレの基本を学ぶという点で、大いにためになります。道の駅は、自治体が国土交通省に申請して登録されるものですから、トイレ行政に携わる自治体職員は、ぜひ読んでほしいです。公共トイレと法律についても書かれています。
もう1冊は、『「進化する」日本のトイレ空間デザイン』です。道の駅のトイレに求められる要素には、清潔さや使いやすさなどがありますが、見た目、つまりデザインも大切な要素だと思います。とくに、トイレのデザイナーや建築家は、こうしたトイレにフォーカスした写真集を見ることは、アイデアを発想するための源泉にもなるのではないでしょうか。
この写真集の1巻で紹介されている、福岡県・大任町にある『道の駅おおとう桜街道』に行ったことがあります。通称、「1億円トイレ」が有名な優美なトイレです。入口付近の壁には桜と紅葉が表現された陶板のレリーフが飾られ、通路奥では透明なピアノが自動演奏をしていました。女性用トイレの個室一つ一つにも陶板の絵が飾られていました。
奇抜に思う方もいるかもしれませんが、実際に利用してみると衛生的で使いやすかったので、これも地方創生の一つのアイデアだと思いました。そんなふうにトイレが話題になり、道の駅が行ってみたい場所になれば、より多くの人が訪れ、地域振興につながるかもしれません。1億円かけなくても、清掃担当の方が育てた地域の花を飾っているだけでも愛情を感じ、心は温かくなります。そんな触れ合いを楽しめるのも道の駅のトイレの素敵なところです。