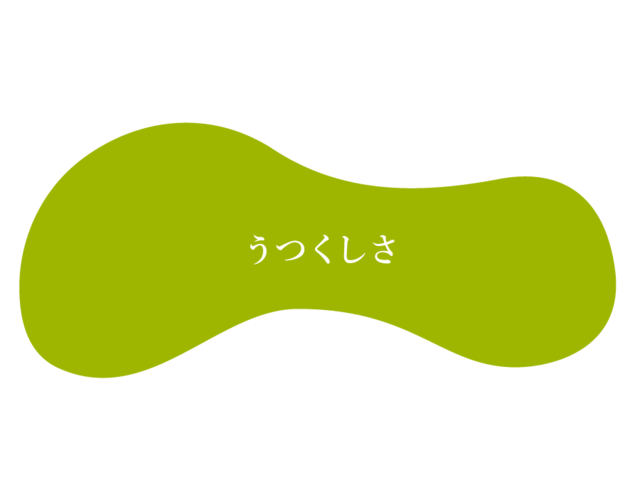「鹿が罠にかかったから解体するで、来るかい」、同じ集落に住む同年代のミッちゃんが誘ってくれた。「うん、行きたい」と張り切って駆け出していくのは、いつも妻である。もし僕だけだったら、興味はあるけれど、また今度にしてみようだとか、手をつけかけた仕事があるからと言って断ってしまうかもしれない。こういう時、誰かと生きているってよいなと思う。自分一人の人生では起こらないことが、次々と起こるのだから。
ミッちゃんの家に着くと、小学生のアラちゃん、イッちゃんも一緒に山に入るという。「山に入ったら、すぐにおるで。頭を硬い棒で叩くんやで。棒は僕が見つけたやんやで」と、少し興奮した様子で教えてくれた。
ガサガサッ、茂みが動いて、おおきな鹿が現れた。足にくくられた罠から逃げ出そうと一晩中試みたのだろう、足を痛そうに引きずっている。辺りには、おびき寄せの米ぬかが撒かれていた。夢中になって食べているうちに地面に隠された罠にはまったようだ。このおおきな生き物は、これから一体どうなるんだろう。
ドッ、長い棒が頭に振り落とされて、鹿は気を失った。ミッちゃんが刃物をスッと首の頸動脈に突き刺して、見開いた眼が、どんどん生きているものの眼ではないようになっていった。命がふうっと湯気のように抜けていった気がした。さっきまで躍動していた躰が、何倍にも重たそうに、しゅうっと何か別のものに変わったように思えた。
「じゃあ、運ぶで」、軽トラの荷台に積んだ躰は、確かにさっきまで生きていた鹿だったけれど、もはや、あちらのものではなく、こちらが扱うもの、扱わなければならないものになっていた。

はじめて体験する鹿の解体は、思っていた以上に美しいものだった。内臓を取り出し、ていねいに皮を剥ぎ、露わになった躰は、まるで僕たち人間のようだった。同じように、食道があり、内臓があり、筋肉があり、骨があり。胃袋の中には、さっきまで食べていた米ぬかが大量に収まっていた。
それぞれの器官にそれぞれの役割があって、それぞれが連結しあっていて、まるでこの世界そのものが、ひとつの躰の中にすっかり収まっているようだった。美しかった。
黙々とナイフで肉を切り分ける。できるだけ無駄な手を加えることなく、刃物を進めたいと願う。ちらりと横を見てみると、6年生のアラちゃんが神妙な面持ちで肉を骨から削ぎ取っている。子どものうちに体験できて、ほんとうによいと思う。僕はといえば、39年間も何も知らずに食べていたんだなと、その事実にクラッと、これまでの人生が揺らいでしまう。
一日掛けて無事に解体が終わって、部位ごとに分けた肉は冷凍し、皮は「持ち帰ってなめしてみたい」と案の定、妻が言い出したので、翌日さらにていねいに皮から肉を剥いで、みょうばんと塩をまぶした。心臓を焼いて食べてみた。すでに毎日繰り返してきたことだけれど、命をいただくということが、とても当たり前のこととして、こういうことなのかと躰に染み込んできた。
この鹿の一生が頭によぎる。母親から生まれた子鹿は、ひたすらに草木を食み、仲間たちといくつもの山々を渡った。気の遠くなるような時間と命の連なりがあった。いま、こうして僕たちの手に渡り、躰の中に入っていった。いったいどんな流れの中に自分がいるのか、いたのか。
空を見上げると、鳶や鷹たちがぐるぐると旋回している。生命があちらからこちらへ、こちらからあちらへ、ぐるぐると巡っている。