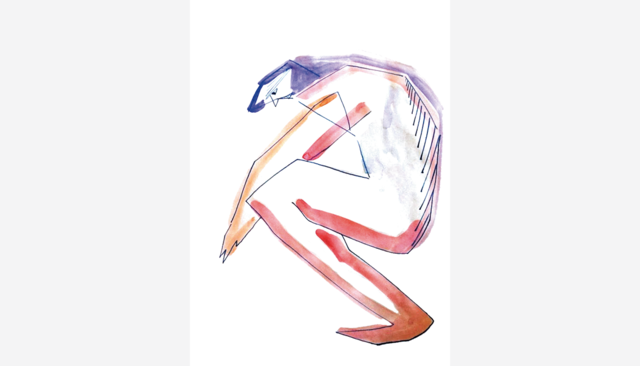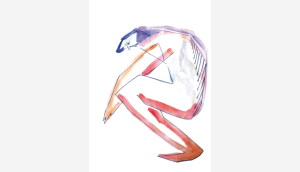2022年6月26日に『いのちの居場所』(扶桑社刊)という本を上梓した。仕事後は家族と遊ぶ時間でもある。家族が眠りについている早朝に書き続けて2年かかった。時代の違和感の正体を探るために、「書く」行為が推進力となった。改めて「書く」行為について書いてみたい。
大学生の時に転機があった。作家の田口ランディさんが大学のゼミに参加され親しくなった。他愛ないことを話していても、プロの作家の言葉の正確さと精密さに心底驚いた。即興的に紡ぎ出される言葉が、針の穴を通すように正確無比だった。言葉を自由自在に扱える人と出会ったことで、言葉を深めることに興味や憧れを持った。ここで得た教訓は、予期せぬ出会いにより唐突に未知の扉は開かれる、ということだ。その後、誰にも伝えずに個人ブログで日記のように考えていることを書き続けた。少しずつ言葉の苦手意識も薄れていった。もともと読書が好きだったため、読み手側だけではなく書き手側にも回りたい、と思うのは自然な流れだった。
最初の単著は『アノニマ・スタジオ』から、『いのちを呼びさますもの』として世に出した。本というメディアを総合芸術と捉えていることに共感してもらえたことが大きかった。本が物体である以上、そこには美が必要となる。陶芸家・河井寛次郎が著書『火の誓い』で「美しいものしかない みにくいものはまよい」と記していたように、「迷い」がなければすべてのものは美しいと思う。もし本が物体として美しくない場合、それは単なる「迷い」なのだと思う。ただ、本を書き始めたときにふと筆が止まった。「そもそもわたしが本を書く意味は何だろう」という疑問にぶち当たったからだ。「書く」行為の必然性に触れない限り、空疎な言葉を羅列をしている感覚に襲われたのだ。
わたしが書く必然性とは何か。文章の行き先を外側の世界ではなく内側の世界へと進路を変え、内なる深海へと沈むように「書く」欲求が湧き立つ「熱水噴出孔」を探した。自分自身の深層意識への進入は「書く」という身体的で具体的な行為のおかげで、3歳頃の原始記憶へと立ち返り、本を書く意味を発見した。
ここで得た2つ目の教訓は、「書く」ことは自分に立ち返る手段であり"通路"でもある、ということだ。生きてさえいれば、人は出会いにより何者にでも変化しうる。出会いの可能性が開かれているからこそ、生きるのだろう。
昨今の地球規模の疫病に端を発した一連の騒動は、人間も含めたあらゆる生命の「居場所」を巡る問題だと感じていた。わたしが「いのち」を所有しているのではなく、「いのち」がわたしを所有している。だからこそ、「わたしの居場所」は、より大きな「いのちの居場所」を考えることであると思う。それが本のタイトルとなった。本は、予想を超えた出会いの通路になると、わたしは強く信じている。
1979年熊本県生まれ。医師、医学博士、東京大学医学部付属病院循環器内科助教(2014-20年)を経て、2020年4月より軽井沢病院総合診療科医長、信州大学社会基盤研究所特任准教授、東京大学先端科学技術研究センター客員研究員、東北芸術工科大学客員教授を兼任(「山形ビエンナーレ2020」芸術監督就任)、2022年4月より軽井沢病院院長に就任。在宅医療、山岳医療にも従事。単著『いのちを呼びさますもの』(2017年、アノニマ・スタジオ)、『いのちは のちの いのちへ』(2020年、同社)、『ころころするからだ』(2018年、春秋社)、『いのちの居場所』(2022年、扶桑社)など。
www.toshiroinaba.com
記事は雑誌ソトコト2022年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。