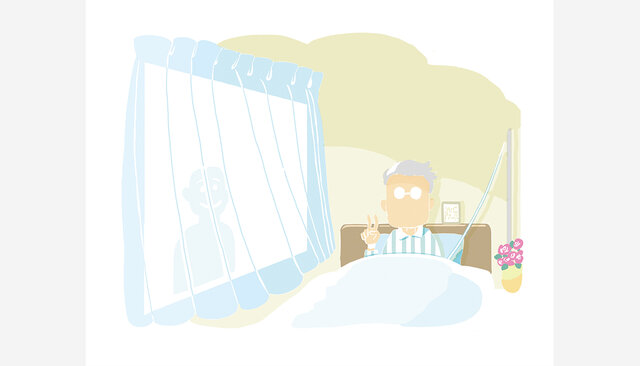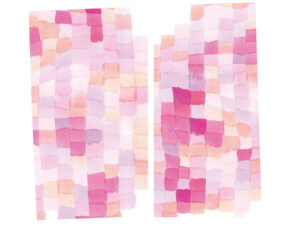先日観た『It’s a Sin』という1980年代英国を描いたドラマは、ゲイの主人公らがLGBTQやHIV/AIDSへの差別に対し、真っ向から抗議する様を描いていた(『It’s a Sin』は英国で記録的な大ヒットになった)。彼らの抗議はいくつかの「大きな一歩」につながるが、いじわるに言えばそれは一歩でしかなくもあり、僕は主人公に、そして未来の自分に、聞いてみたくなった。「それでも抗議してよかった?」と。
じいちゃんが初めて人を好きになったのは中学3年生の頃なんだ。そのときは誰にも言えなくてね。ん、シャイだったのかって? まぁ、それもあったのかも知れないね。だけど当時は男が好きだというだけで、気持ち悪がられる時代だったから、じいちゃんはそれが耐えられなくてね。あぁ、そうだね、そうしてくれるかい。薄いほうのカーテンだけでいいよ。うん、丁度いい。お前の顔がちゃんと見えるよ。へへ。
ところで、お前の世代でも、LGBTという言葉は知ってるものかい? そうか、聞いたことはあるか。そう、そういう意味だ。当時の日本じゃLGBTの人たちに暴力をふるうような人はほとんどいなかった。だけど、みんなLGBTは「いない」ということにする空気があってね。いるのはテレビの中と外国だけで、自分の世界には「いない」。じいちゃんはあの頃、自分が「いない人」になるのが怖かったんだろうね。
だからそうだ、42歳でHIVになったときも、数年間は誰にも言えなくてね。その頃じゃ、少量の薬を飲むだけでAIDSを発症することもなかったし、HIVで死ぬことはなかった。誰かにうつすことだってなかったのに、だけど、言えなかったねえ。じいちゃんは、また「いない人」にされるのかもしれないと思うと、怖かったんだ。20代で初めて自分はゲイだと友だちや家族に伝えて、運良く受け入れてもらえてね。やっと「いる人」になれたから、もう戻りたくはなかった。あぁ、そうだよな。今じゃAIDSも風邪みたいなもんなのにな。でもじいちゃんが若い頃というのは、そういう時代だったんだ。
お前の父さんの父親になるのも大変でね。当時は同性婚どころか養子をとることも同性カップルじゃできなかった。「両親が同性愛者だなんて、子どもがかわいそうだ」とか「子どもには父と母、両方が必要だ」とか、真面目に言う人たちがいてね。そんなことは無駄な心配だと社会に示していったのが、じいちゃんより少し年上の先輩たちだった。先輩たちの手で一身に愛された子どもらが大人になり、反論してくれたのさ。「私たちは幸せだ」ってね。じいちゃんはその言葉を北極星みたいに道標にしながら、お前の父さんを育てたよ。
LGBTのパレードも何回も歩いたねえ。いろんな署名もしたし、投票も必ず行った。仲間たちとLGBTに関する動画をつくったり、イベントをやったりもしたんだよ。立派だって? いやいや、立派なんてもんじゃないさ。私はね、正直ずっと考えていたよ。この一筆に、この一票に、なんの意味があるんだって。私は社会を変えられるような人じゃなかった。ずっと無力だったよ。
だけどね、社会はこうして変わったんだ。だから今、私の目の前にお前がいる。数えきれないほどたくさんの、もう会うことのない人たちの願いが、大きな川になって社会をあるべき場所に運んできたのさ。私は幸せだったよ。その川の流れをただ岸から眺めていたんじゃないのだからね。その流れの中に、私はいたのだから。寒くて、何度も溺れそうになった。笑うやつもいたよ。でも振り返ると、不思議なくらい温かかったと、そう思うんだ。
文・太田尚樹 イラスト・井上 涼
おおた・なおき●1988年大阪生まれのゲイ。バレーボールが死ぬほど好き。編集者・ライター。神戸大学を卒業後、リクルートに入社。その後退社し『やる気あり美』を発足。「世の中とLGBTのグッとくる接点」となるようなアート、エンタメコンテンツの企画、制作を行っている。
記事は雑誌ソトコト2022年3月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。