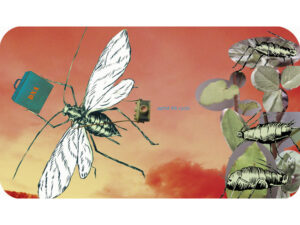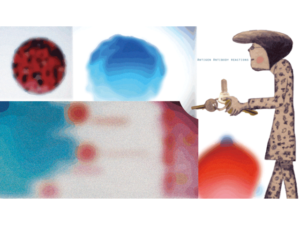前回のこの連載では、2020年のノーベル医学・生理学賞を受賞したC型肝炎ウイルスについて触れたが、新型の肝炎ウイルス(当時は、まだA型とB型肝炎ウイルスしか判明していなかった)の存在をつきとめたハーベイ・オルター、その遺伝子を解明したマイケル・ホートンの功績については述べたが、3人目の受賞者であるチャールズ・ライスについては、紙幅の関係で書き切れなかったので、ちょっと述べておきたい。実は、ライス博士のことはよく知っているので、今回の受賞はとても喜ばしい。
私は、京都大学の大学院で博士過程を終えたあと、さらに研究修業の場を求めて、米国に留学した。それが、ニューヨーク市にあるロックフェラー大学である。世界中の研究室に何通も応募の手紙を出したうち、たまたま拾ってくれたのが、ロックフェラー大学の分子細胞学研究室だった。これはほんとうの偶然で、たまたまポスドク(博士研究員)のポジションの空きがあったのだ。初めての海外生活、しかも花のニューヨークで暮らせると思って舞い上がり、取るものも取りあえず、赴任したのだが、甘かった。
ポスドクとは、いわば研究のための傭兵(さらには奴隷なのだが、わずかな給料が出る)。朝から晩までボロ雑巾のように働かされ、成果を常に求められるというプレッシャー下に置かれる。右も左もわからず、英語もおぼつかないので、ただただ一生懸命、研究に邁進するしかなかった。ニューヨーク観光をしている暇も精神的余裕も金銭的余裕もなかった。
しばらくニューヨークで研究をしていた私は、ボスが、ボストンのハーバード大学に転出することになり、一緒に連れて行かれることになった。私は、美しいながら静かすぎるボストンよりも、喧騒のニューヨークが好きだったが、雇われの身では嫌もなにもない。研究資材とともにボストンに送られた。
私たちが出て、空き部屋となったロックフェラー大学の研究室に、そのあと入ってきたのが、ライス博士のグループだった。ライス博士は、研究室を自分好みに大改装し、広い教授室をつくって赤い絨毯を敷き、毎日、自分の愛犬を連れて大学にやってきた。後に、私はかつて自分たちが研究していたその懐かしい場所を見に行ったのだが、当時の面影はことごとく消えてしまっていたので落胆した。実験がうまくいかないとき、密かに屋上に出るために使っていた狭い螺旋階段に通じる扉まで、壁に埋め込まれてしまっていた。
そのライス研究室が、C型肝炎に関する素晴らしい仕事を成し遂げたのである。先に述べたように、C型肝炎については、その原因としてウイルスが存在すること、そしてそのウイルスの遺伝子構造も解明できた。しかし、ここまででは原因ウイルスの存在の有無を調べることはできても、この病気を治療することはできない。ちょうど、現在、私たちを悩ませている新型コロナウイルスもまたこの段階にある。存在と検出はできても、その先はまだ、という状況。
予防はワクチンがつくれれば、なんとか可能となるが、感染してしまったあとのウイルス病治療はなかなか困難となる。ウイルスの増殖メカニズムを解明し、それを阻害するような薬物を見つけてこなければならない。C型肝炎ウイルスがやっかいなのは、ラットやマウスといった小型動物を使った感染実験ができないこと。ヒトに近いサルにしか移すことができないのだ。
そこで、ライス博士たちは、C型肝炎ウイルスゲノムの主要部分だけを切り出して、それを試験管の中で培養細胞に感染させ、増殖させることができる実験モデルをつくろうと考え、実際にそれを実現したのである。これをウイルスのレプリコン(複製単位)という。
レプリコンは、ウイルスの一部であって、ウイルスそのものではなく、また病気をもたらすことはないので研究者にとっても安全だ。一方で、試験管内で増殖が簡単に再現できるので、メカニズムの解析や、さまざまな薬物の効果を試すことができる。
こうしてレプリコンを使った大量のスクリーニングによって、C型肝炎ウイルスの複製を阻害する画期的な特効薬(ハーボニー)が発見されることとなり、今ではC型肝炎は、治療可能な病気、恐るるに足らない肝炎となった。特効薬の発見は、ライス博士とは別のグループによる業績なので、それはまた将来のノーベル賞候補となるだろう。
いずれにしても、C型肝炎ウイルスの研究史を見渡してみると、ウイルスの存在の発見から治療法の開発まで、およそ50年の歳月が費やされていることになる。研究の技術やテクノロジーは日々進展しているとはいえ、科学研究とその成果の収穫には長い年月がかかることのよい例と言える。
私たちも、新型コロナウイルスと長いスパンで対峙していかなくてはならないだろう。