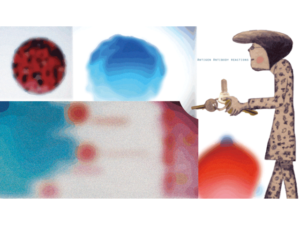アリマキは植物の茎に取りついて、細い口吻を表皮に差し込み、巧みに栄養分を吸い取る。これは蚊がヒトから血を吸い取る行為と非常に似ている。闇雲に針を突き立てても血は吸えない。皮膚の下を流れる毛細血管に向けて、正確にしかもすばやく針を下ろさなければならない。深度も重要である。蚊は、温度や血流を感知することができる。
植物の葉や茎にも、動物の血管に似たチューブ構造が張り巡らされている。根から吸い上げた水分を供給するためのチューブと、それとは別に、葉で光合成反応が行われた結果、作られた糖分を植物体に分配するためのチューブである。後者を篩管と呼ぶ。
アリマキはこの篩管に口吻を突き刺して、糖液を吸い取っている。おそらく蚊と同様、篩管の場所と深さを正確に探り当てる能力を小さな身体の中に宿しているのだ。
あまりにたくさん吸い取りすぎて、糖液はアリマキの身体からあふれ出すことさえある。アリはこの糖液を目当てにやってきて、アリマキのお尻に浮かんだ甘露の水滴を舐め取る。アリマキは漢字で、蟻牧であり、蟻を養ってあげているのだ。その代わり、蟻は“用心棒”として天敵からアリマキを守る。
アリマキの天敵はテントウムシだ。テントウムシには可憐でかわいいイメージがあるが、実は肉食の獰猛な昆虫である。アリマキを見つけると片っ端からバリバリと食い散らかしていく。細い手足で植物にしがみついているアリマキはひとたまりもない。こんなとき、アリは果敢にアタックして、テントウムシを追っ払ってくれるのだ。そのかわり甘露をいただく。さしずめ、“みかじめ料”というところである。
さて、アリマキの類いまれなる技に着目した研究者がいた。ケンブリッジ大学のケネディとミトラーである。彼らは、一心不乱に蜜を吸い続けるアリマキの姿を仔細に観察した。そして的確に篩管を探り当てる能力にたいへんな感銘を受けた。もしこんな能力が植物学者にもあれば、なんと便利なことだろう。植物学者たちは植物の光合成能力や糖分がどのように運搬されるかにとても興味を持っていた。しかしどんなに細い注射針を用いても、植物の篩管から栄養液を吸い取ることは至難の業だった。篩管はとても細いチューブで、断面は文字どおり、篩状になっている。カミソリやナイフで植物を傷つけると、篩管構造自体が破壊され、運搬システムを損なってしまうことになる。しかも、侵襲は植物にストレス反応を起こしてしまうので、正常な代謝を観察できなくなる。
吸蜜中のアリマキは、その行為にあまりにも熱中しすぎて周りのことは一切気にしない。たとえ研究者が、小型のピンセットでアリマキの身体をちょんちょんとつついても、動かされまいと足を踏ん張ることはあっても、吸蜜行動をやめる気配はない。
そこでケネディとミトラーは考えた。ならば、いささか残虐な行為ではあるけれど、薄くて小さなナイフを持って吸蜜中のアリマキに接近し、その口吻を顔の直下の部分で、スパッと切り離してしまえばどうなるだろうか?
実際に彼らはそれを試みた。うまくいくまでに何回かの試行錯誤や器具の工夫があった。そして最終的に成功した。スパッ。おそらくアリマキ自身は自分の身にいったい何が起こったのかわからなかったはずだ。ケネディとミトラーはアリマキの身体を茎からはずした。あとには、茎に刺さったままの口吻が残っていた。飲みかけのアイスコーヒーに入ったストローのように。切断された口吻の開口部からは、いままさに篩管から押し上げられてきた甘い蜜が透明のしずくとなって膨らみ始めていた。こうして篩管液を採取する新たなテクノロジーが開発された。
いや、テクノロジーというよりも、夏休みの自由研究を思わせる素朴な「発明」だった。しかし、その有用性は確かなものだった。実際、この方法で採取された純粋な篩管液の内容を分析すると、そこには高濃度の糖をはじめとする栄養素が含まれていることが判明した。ケネディとミトラーの「首チョンパ」実験法は、1953年3月21日号の『ネイチャー』誌に採択され、立派な論文として掲載された。同じ年のネイチャーにはワトソンとクリックによるDNAの二重らせん構造解明の論文が発表された。かの『ネイチャー』誌にもこのような牧歌的な研究が投稿された時代があったのだ。