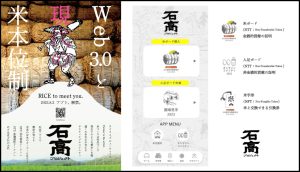山古志といえば、日本が誇る伝統的な産業の一つである錦鯉の発祥地として広く知られています。しかし、もうひとつ、千年以上の歴史を持つ文化が今もなお息づいています。それが「牛の角突き」です。
1トン前後の巨体を持つ牛が角を突き合わせ、激しくぶつかり合う「山古志の牛の角突き」は、一般的な闘牛とは大きく異なる伝統行事です。そこでは、家族の一員として大切に育てられた牛が、大きなダメージを負う前に引き分けにするという文化が守られているのです。
牛同士の闘いもさることながら、勢子(せこ)と呼ばれる人たちが素手で牛を引き離し、引き分けに持っていく様子は迫力満点。観る者の心を揺さぶります。
Nishikigoi NFTは、地域の象徴である錦鯉をテーマに生まれましたが、コミュニティの広がりとともに、山古志のもうひとつの伝統である牛の角突きにも注目が集まりました。そうした中で「牛の角突きファンクラブ」が立ち上がり、地域内外から応援する動きが生まれています。
この牛の角突きを守り続け、現場で支えているのが、勢子(せこ)として牛とともに闘うMCあっちゃんです。勢子とは、牛を巧みに操り、興奮した牛をなだめ、適切なタイミングで試合を終わらせる役割を担う存在。牛と深い信頼関係を築きながら、この伝統文化を支えています。
一方で、デジタル村民として「牛の角突きファンクラブ」を立ち上げ、外部から盛り上げようとしているのが RYUさんです。地域外の立場から牛の角突きの魅力を発信し、DAO(分散型自律組織)の仕組みを活用しながら、ファンクラブの新しい形を模索しています。
伝統とデジタルが交差する今、お二人は牛の角突きをどのように捉え、どのような未来を描いているのか。その言葉を紡ぎながら、牛の角突きが持つ魅力と今後の可能性について探っていきます。

クリプトヴィレッジ:まずは自己紹介をお願いします。MCあっちゃんさんが牛の角突きに関わるようになったきっかけについても教えてください。
MCあっちゃん:山古志の牛の角突きで勢子、牛持ち(オーナー)、MCをしています。妻と子供1人の3人暮らしです。実家が虫亀で闘牛場(現在は解体済)のすぐ下に家があったので、小さいころから遊び場は闘牛場でした。なので、角突きは何の違和感もなくハマりました。22〜23歳のころ、それまでアナウンスをされていた方が勇退されたため、MCを担当するようになりました。
クリプトヴィレッジ:牛の角突きを運営されていて、特に「ここが魅力!」と感じるポイントはどんなところですか?また、初めて観戦する方には、どんなところに注目して楽しんでほしいですか?
MCあっちゃん:牛たちの激突だけでなく、駆け引きなど、私たちの想像もつかないすごいことをやっているんですけども、それを1人でも多くのお客さんに知ってもらいたいです。現場での雰囲気なども含め、リモートでは感じることができないものを感じてもらいたいです。1ファンとしては、好きな牛を見つけて、その牛の取組を楽しみにしてもらいたいです。私は岩手の平庭闘牛にいる『魁乃翔』という牛のファンなんです。毎年の成長を見るのを楽しみにしてます。
クリプトヴィレッジ:この大切な山古志の伝統を守るためにどんな準備をされているのでしょうか?現在の課題などもあれば教えてください。
MCあっちゃん:課題はたくさんあります。牛の確保や後継者など、自分ができることをやっていきたいと思っています。準備ではいろいろなことをやっています。まもなく雪が消えたら闘牛場を整備して、牛たちの爪を切り体調を整えていきます。また開催日には会員みんなで準備して、お客さんを迎えます。これまで困難な場面もありましたが、角突きが好きで続けたいという思いから地方公務員として就職しました。そのおかげで、大変だと感じたことはないのかもしれません。
クリプトヴィレッジ:牛の角突きに出場する牛たちは、どのように育てられているのでしょうか?また、牛と飼い主の絆についてもお聞かせください。
MCあっちゃん:中越地震前は多くの牛が各自の家で飼育されていました。一部は自宅で飼育できないオーナー(地域外在住)のための共同牛舎がありました。なので、当時は牛持ち(オーナー)と牛のつながりが深かったと思います。今はほとんどの牛が共同牛舎で飼育されており、松井会長が飼育を担当しています。ただ、私のように休みの日に自分の牛のブラッシングなどをするために共同牛舎に行くオーナーもいるんです。実際、共同牛舎には40頭ほどの牛がいますが、私が行くと自分の牛は立ち上がって顔を見せてくれます。やっぱりブラッシングをしたり世話をしている分、私のことを認識してくれているし、絆を深められていると感じますね。
クリプトヴィレッジ:『牛の角突きファンクラブ』のような新しい取り組みが注目されていますが、こうした活動についてどう感じていますか?また、これが牛の角突きの未来にどんな影響を与えると思いますか?10年後、20年後の牛の角突きについての希望や考えも教えてください。
MCあっちゃん:同じ闘牛開催地である沖縄や徳之島では、グループで牛を持っていることもあります。なので山古志では「牛の角突きファンクラブ」がグループとして牛を持つこと、これが一つの目標になると思います。そして、自分たちの牛が出場するときに山古志に来てくれたら嬉しいですね。

さて、ここまでMCあっちゃんにお話を伺ってきましたが、次はデジタル村民であるRYUさんにお話を伺いたいと思います。これまでの話を踏まえ、RYUさんの視点から見たプロジェクトの現状や、今後の展望についても聞きたいと思います。
クリプトヴィレッジ:RYUさんが牛の角突きに関わるようになったきっかけは何でしたか?実際に牛の角突きを見たとき、どんなことを感じましたか?
RYUさん:初めて牛の角突きを観戦したのは、2023年5月4日で、2回目の山古志帰省の時でした。毎年5月4日は直売所まつり(山菜販売などおらたるで開催)と牛の角突き初場所の日です。牛串を食べながら初めての観戦を満喫しました。
一言で言えば「面白いな」と感じました。勢子さんが引き分けにするところや女性の牛持ちさんが牛を引き回すところがすごく印象に残っています。この感動を他の人にも味わってほしいと思い、5月5日の伊藤穰一さんのweekly gmで角突きの様子をビデオで流すなど山古志の魅力を紹介させていただきました。
クリプトヴィレッジ:牛の角突きファンクラブについて教えてください!どのような活動をされていて、どんな背景で立ち上がったのでしょうか?また、立ち上げのきっかけや込めた想いについてもぜひお聞かせください。
RYUさん:すっかり山古志の魅力に取り憑かれた私は、2023年6月17〜18日に仲間に声をかけて山古志ツアーを企画しました。もちろんメインプログラムの一つである牛の角突きが18日に開催されるのでこの日を選びました。ここで、なんと闘牛会のご好意で牛の引き回しを初体験させてもらったのです。間近の伊之助(牛の名前)に感動しました。
そして、7月16日の牛の角突きの後に開催される闘牛会のBBQ参加のお声がけをいただき、闘牛会の皆様と歓談させていただきました。この日は、牛の角突きを応援したいと言う気持ちからデジタル村民で初めて花金を出すことになりました。いつのまにか自分は初場所から3回も連続で角突きを観戦していました。
すっかり牛の角突きのファンになってしまい、同じくデジタル村民で角突きファンの金光碧さんとファンクラブを立ち上げようと言う話が持ち上がりました。再び山古志ツアーを8月26日〜27日に企画しましたが、8月26日が二十村郷盆踊りの最後ということで、ツアーから抜けて盆踊りに参加しました。そこで闘牛会の関さんとお話しさせていただき、翌日の8月27日の牛の角突きは、初めて会場設営の草刈りのお手伝いに参加しました。この辺から本格的にファンクラブ活動が始まっていくことになります。9月17日の牛の角突きでは、牛の角突きファンクラブとして初めて花金を出すことになりました。

クリプトヴィレッジ:地域外の立場だからこそ気づいた山古志や牛の角突きの魅力はありますか?また、どんな形で応援していきたいですか?
RYUさん:山古志の素敵な風景も牛の角突きも、山古志では当たり前のことなのですが、「よそもの」からしたらとても貴重な風景・体験であり、伝統文化です。人は日常のものにはあまり関心が高くないですが、失った時にはとても空虚な気持ちになるものです。
1トンを超える牛も珍しくない中で、人間が知恵と度胸と愛情をもって角突きを引き分けにもっていく醍醐味は、とても感動的です。自分がもう少し若かったら勢子になって鼻をとったり、綱をかけたりしたいものです。観ているだけでも躍動感が伝わる体験は変え難いと思っています。そして闘いを終えた牛は穏やかになり、いたずらっ子に戻って、とても愛らしくなります(勢子さんも実は同じかも)。
私は、この素敵な体験を、そして伝統文化を一人でも多くの人に知ってもらい、そして後世につないでいきたいと思っています。だからこそ、ファンクラブの輪をこれからも拡げて闘牛場に入れないくらいの観客にきてもらえるようにこの想いを拡散していきます。
クリプトヴィレッジ:NFTやWeb3は、これまで関われなかった人々が伝統文化を支援できる仕組みを生み出しています。この技術が今後どのように地域文化と結びついていく可能性があると考えていますか?
RYUさん:先日、「地方創生から日本を活性化」〜誰でも参加できるweb3がひらく未来〜」というnoteを公開しましたが、山古志での取り組みについて今執筆中で、その新しいnoteの一編をご紹介します。
ブロックチェーンは、時系列的に記録を残せる台帳で、その記録の改竄が容易ではない仕組みです。これが実はすごいことなんです。従来は、データ記録しようと思ったら、個別にサーバーを立てて、セキュリティ対策を考え維持管理してきましたが、ブロックチェーンを使えば、ガス代というわずかな利用料を負担することで自由に記録を残せる台帳が作れてしまうのです。この仕組みの可能性は無限大で、世界で流通可能なトークン(FT)を発行したり、デジタル証明書(NFT)も発行できてしまいます。まだユーザーインタフェースが難しいのですが、慣れれば個人でも小規模組織でもわずかな資金で様々なことが可能になるデジタルインフラなんです。「牛の角突きファンクラブ」もその恩恵に預かっている一つの事例です。ファンクラブの会員には、会員証NFT(デジタル証明書)が発行され、ファンクラブの方向性を決める投票権をもっています。会員証NFTをもっている人だけが投票できる仕組みです。ブロックチェーンを使っているので少しだけガス代がかかっていますが、無料で使えるツールを使うことで実現できています。これを個人レベルでつくれることがすごいところです。
妄想しているだけでも楽しくなるのですが、牛持ちさんに牛持ち証明書NFTを発行したり、リピーターのファンには、参加記念NFTを配布し、一定数貯まったらなにかプレゼントするとか?、推し牛NFTを発行するとか、餌代NFTを作って餌代の寄付を募るとか?いろいろなNFTがたくさん貯まるとファンのレベルが上がるとか?いろいろ考えなければいけないですが夢は広がります。
さいごに
牛の角突きを支える新たな形として生まれたファンクラブ。その背景には、長年受け継がれてきた伝統を守り、未来へつなげたいという熱い想いがありました。こうした取り組みを通じて、より多くの人が牛の角突きの魅力に触れ、応援の輪が広がっていくことで、この文化がさらに発展していくのではないでしょうか。ぜひ気になる方はチェックをしてみてください。
牛の角突きの日程について
MCあっちゃんのブログから抜粋。
詳しくはこちらをご覧ください。
2025年の開催日程
開催日程
- 4月29日(火)開幕前・プレイベントイベント
- 5月4日(日)令和7年初場所
- 5月25日(日)
- 6月15日(日)
- 7月20日(日)
- 8月2日(土)※長岡まつり場所(取組は7組程度を予定)
- 8月3日(日)※長岡まつり場所(取組は7組程度を予定)
- 8月24日(日)※午前開催
- 9月14日(日)
- 10月12日(日)
- 10月23日(木)※中越地震復興感謝場所
- 11月3日(月)令和7年千秋楽
今回のインタビュイーのご紹介
MCあっちゃん
山古志の牛の角突きで、勢子や牛持ち(オーナー)、MCを担当している。実家は虫亀にあり、闘牛場のすぐ下に家があったため、幼少期から闘牛場で遊んで育った。この環境が影響し、角突きには自然に魅力を感じ、深く関わるようになった。22〜23歳の頃、長年アナウンスを担当していた方が引退したのをきっかけに、MCを務めるようになった。
RYU
2021年12月より、「Henkaku Discord Community」に参加し、web3界隈での活動を開始、山古志の活動に興味を持ち、「NishigoiNFT(通称山古志DAO)」に参加、山古志の伝統文化「牛の角突き」に魅せられ、「牛の角突きファンクラブ(DAO)」を創設する他、小正月のさいの神、山古志小中学校運動会、盆踊りなどの地域行事のタイミングで帰省し、自ら楽しみながら山古志の魅力を発信中。最近では、360度画像を使ってVR空間での山古志の紹介も行っている。新しい組織のかたちであるDAOに関心を持っていたことから、「日本DAO協会」の創設(2024年4月)にも関わり、現在も協会運営に携わっている。
また、日本の宝である地方を元気にしたいという思いから、「Rule Makers DAO(SUBDAO-地域他)」「夕張メロン(夕張市)」「おさかなだお長崎(長崎市)」「石高(西会津町)」などに参加しながら、2024年6月にはイベント「地方が輝き続けるために」を主催するなど、地方創生につながるDAOやweb3技術の活用拡大へむけ活動中。
ぜひフォローをお願いします!