昨年、『「健康」から生活をまもる 最新医学と12の迷信』を上梓した医師の大脇幸志郞さん。そのタイトルの通り、健康を重視するあまり生活に不自由を感じることもある現代という時代に「ウェルビーイングな健康」とは何を指すのか。お話を伺った。
定義が流動的な、現代における「健康」。
健康、さらにウェルビーイングな状態の健康とはどんなものなのだろうか。医師の大脇幸志郞さんは言う。
「現代の医学でいう『健康』は定義が流動的ですね。何か理想的な状態としての健康ということをあまり示さなくなっていて、『こういうことをすると、こういうことが起こります』という原因と結果の関係まで分解するようになっています。だから『健康』をひとつの言葉やありかたで要約するのは非常に難しい」
現在は主に訪問医療に携わる大脇さんは、東京大学医学部卒業後、出版社勤務や医療情報サイトの運営に7年間関わり、その後医師になった。昨年6月に『「健康」から生活をまもる 最新医学と12の迷信』を上梓し、正しい情報収集をして健康であろうとするばかりにかえって不自由になってしまうことに、最新医学の情報に基づいた疑問を投げかけた。「食事のコレステロールは計算しなくていい」などの実例を挙げつつ、今の時代に即したかたちの医学知識の役立て方を提案している。
「ですが、人々がどんな健康観を持っていたのか、歴史をさかのぼることで見えてくることはあります。戦後の医学や保健行政では、完璧なウェルビーイングなことを『健康』と呼んでいました」
この場合の健康とは、体に病気がないというだけでなく、精神的、社会的な意味まで含んでいた。
「でもそのうちに、さすがにそれは言い過ぎではないかという意見が出てくるように。では『健康とはどう捉えたらいいのか』と考えることが、医学の世界ではひとつの軸として今も続いていると思います」
とはいえ、戦後のある時期までは冒頭の健康観は機能していた。栄養対策や感染症対策、衛生観念の普及などに伴い、人々の健康状態はみるみるうちに改善された。
しかしそれによりできることがなくなり、以降、何をしたらウェルビーイングになるのか迷走した、と大脇さんは考える。
「ひとつの答えとして、健康に見える人でもどんどん検査をして、病気を早期発見・治療しようという流れがありました。しかし1990年代に『エビデンスに基づく医学』という考え方が一般化したことが次の節目になります」

どんな状態を望むのか、常に自分に問いかける。
予防医学の思想から、今まで病気だと思っていなかった部分を見つけ出すことに意義があるのではという発想が生まれた。たとえばメタボリック・シンドロームなどだ。このことには良い面もあるが、「病気づくり」などとも言われ、議論の元にもなっている。
そしてエビデンスからは、意外にも予防医学の効果には限界があり、悪い面もあるとわかってきた。
加えて現代はさまざまな価値観が多様化・複雑化してきた時代。誰にとって何の優先順位が高いのか一概に測れなくなったことも、予防医学にブレーキをかけた。
「救われた人ももちろんいますが、かつては問題視されていなかったことで『自分は病気なのでは』と考える人も増えました。結果として過剰な治療でかえって不幸にしたり、やりすぎなところまで踏み込んでしまいがちなのが現代の医療だと思います」
その点を踏まえ、医師の立場からすると、ウェルビーイングな健康とは何かを考えるのは、患者にどこまで医療介入するべきか考えるのと同義であるという。逆に医療を受ける側からすれば、自分にとって医療の利益を最大限受けられるバランスを失わないことがウェルビーイングな健康に役立つ。
バランスを考えると、「完璧な健康を目指して何かを我慢すること」が最善とは限らない。
「それだけを是として食べたいものを遠ざけたり、飲みたくない薬を飲み続けたりすることがウェルビーイングなことなのか。もちろん健康であるに越したことはありませんし、体の不調があれば治ったほうがいいでしょう。ですが、そこでどちらを取るべきかは正しい答えのない問題です。一度決めても後になって考えが変わることもあります。だから自分が何を望んでいるのか、常に自分の心に尋ねることが大事です」
答えがないのは医師にとっても同様だ。
「『自分はこういう状態になりたい』と強い意志を持っている人は少数で、多くの人は『お医師さんに言われたから』で治療方針を決めがちです。そのうえでどうするかは、いつも本当に迷います」
だが、日々迷うのが正しいのだと大脇さんは思っている。
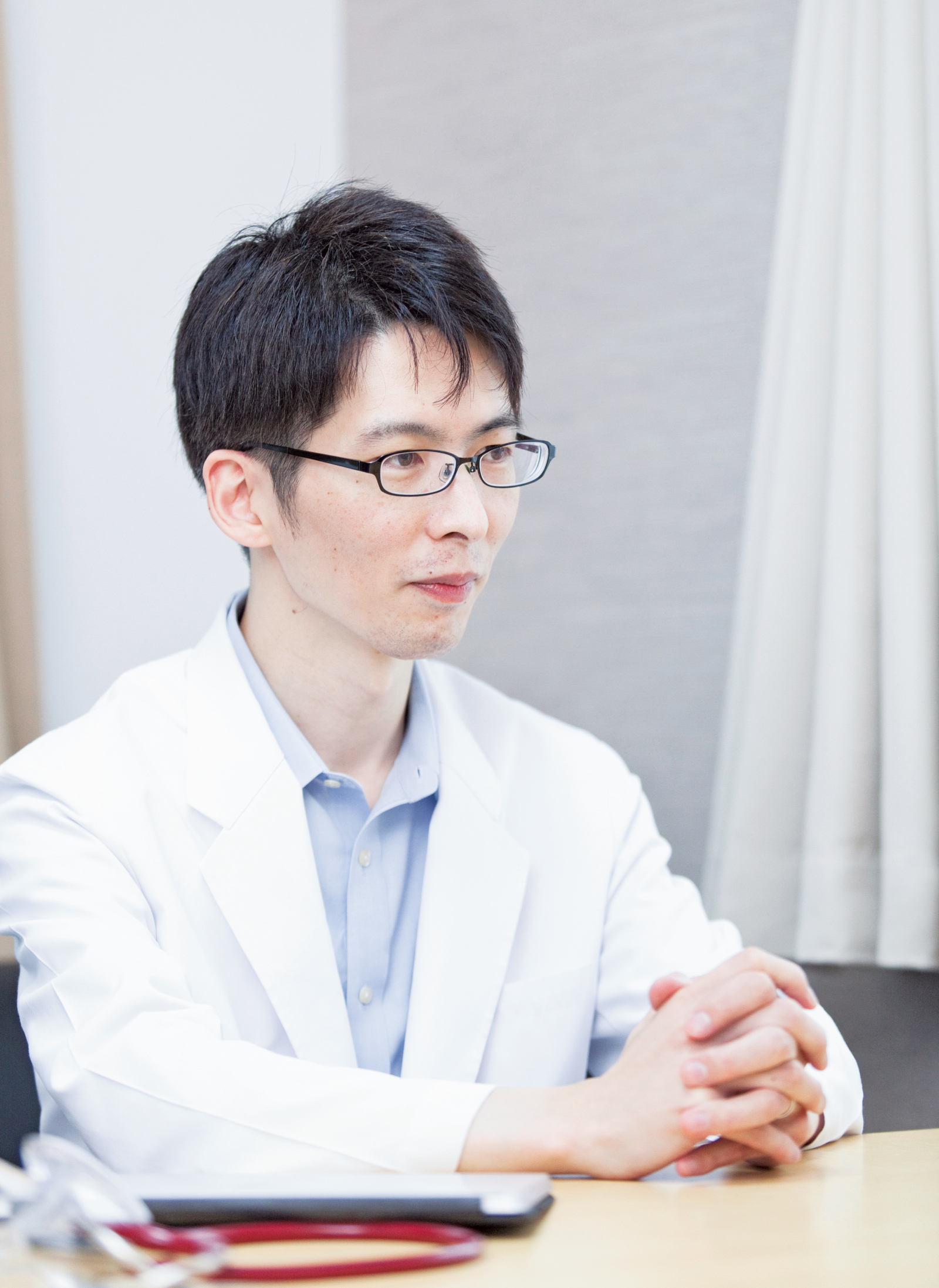
多様な背景の人たちから多様な『健康』を学ぶ。
「完璧な健康を目指すこと」だけを是としないのは、今後の高齢化社会におけるウェルビーイングな健康とは何かということにもリンクする。
「年を取れば落ちた体力はもう戻らないし、治らない体の不調も出てきます。そんな中で健康になったほうがいい、リハビリも一生懸命がんばりましょうというのは、あまりにやりすぎると本人が負担に感じてしまう」
さらに大脇さんは、高齢者施設で気づいたことがある。
「自分や周囲の人が健康ではないことに対して、あっけらかんとしているところがあります。『自分もそれでしょうがないし、ほかの人もそうだよね』と認め合う文化ができているんです」
この文化を他者との間でつくれるかどうかも、ウェルビーイングに関わってくるという。
「必ずしも健康でなくてもいいということは、『あなたが健康でなくても私たちは助け合えますよ』と受け入れてくれる他者がいるということ。健康ではない人を見下さないネットワークができてくると、みんなハッピーに過ごせるんですよ。だからウェルビーイングな健康というのは、コミュニケーションのありかたに関わることでもあるでしょう」
これは医師として、患者の治療目標を決める際にも強く感じることだそうだ。個人だけに聞くのではなく、家族の意思も必要とする。個人と家族の関係性を考慮しながら意見をすり合わせ、最終的な治療目標を決めていく。
人は不健康になってもいいし、なりたい姿に応じて時には健康の定義を自分なりに変えてもいい。だがそれは、今いる環境の中で周囲と一緒に決めることなのだ。
では、健康ではないことを認め合える文化やコミュニケーションが生まれやすい、育ちやすい“土壌”はあるのだろうか。
「いろんな年齢や背景の人が一緒に生活している場所で生まれやすいように感じます。たとえば若い人が、親しみのある年を取った人の体が不自由になっていくのを身近で見て、そうなるのは当たり前だと思えれば、自分が年を取っても自分を許せるのではないでしょうか。高齢者や障害者を施設に閉じ込めるべきではなく、地域に受け入れられるべきだと言われていますが、そこには『つながりをつくって、親しみを感じる』という面もあると思います」
大脇さんは前述した著書の中で、「人には不健康になる権利がある」と述べている。その権利を享受するために必要なこと──日々「自分はどう生きたいか」について考えること、健康はもちろん不健康も認め合い、自分や他者が不健康であっても受け入れる文化をつくろうとすること、必要があれば話し合い、相手がどんなウェルビーイングを求めているか知ろうとすること、医学的に見てどうかは置いておいて、自分なりのウェルビーイングの定義をつくり、それに応じて生きていくことなどが、逆説的にウェルビーイングな健康につながっていくのだろう。








































