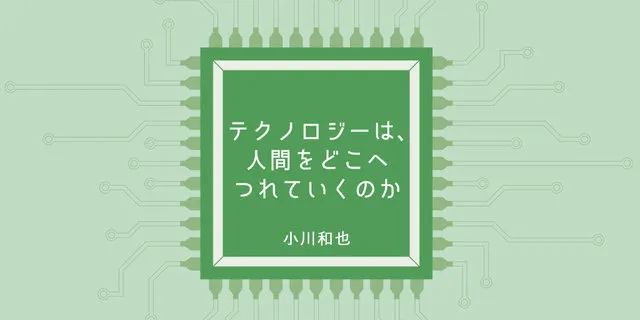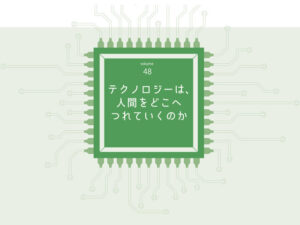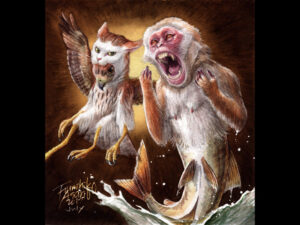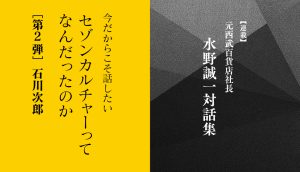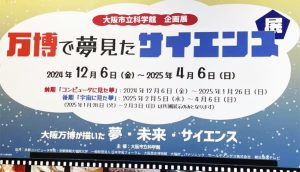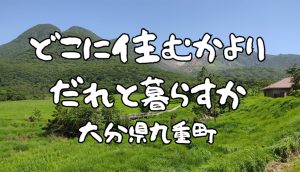廃墟となったチェルシーのマッキトリック・ホテル。地上6階・地下1階、約100の趣向を凝らした部屋からなる建物の中を、シェイクスピアの『マクベス』をベースとした物語をほとんど無言で演じる役者が歩き回る。客席と舞台が分離されておらず、観客と役者の間に境界線はない。白い仮面を着けた観客は、「アノニマス(見えざる者)」として舞台の参加者と化す。観客と役者が接近し、一対の関係性が生じる。方々に散らばった役者を追いかけ、受け取る物語も観客次第。
英国のパンチドランク(Punchdrunk)という劇団が、この『スリープ・ノー・モア(Sleep No More)』という作品をニューヨークで2011年に初公演して以来、ロングランとなっている。彼らの成功をきっかけに、英国や米国でイマーシブ・シアター(Immersive Theater)と称される体験型演劇が急増し、注目を集めるようになった。
観客と演者の境界線をなくし、観客も構成の一部とするタイプの演劇は昔から存在した。1981年にカナダのストラッチャン・ハウスで初演された『タマラ(Tamara)』は、11部屋ある一軒家の中を10人の役者が同時進行で物語を展開する。観客は特定の役者を選んで随行し、随行自体を役として演じ、物語の体験者となる。まさに、今でいうイマーシブ・シアターの走りであった。
定められた客席に座り、舞台の上の役者を傍観する予定調和な演劇と比べ、イマーシブ・シアターは観客に負荷を与える。固定の居場所はなく、自分なりの物語を求めてさまよい、劇の参加者となる。傍観者であればよかった演劇のようにはいかないのだ。それなのに、なぜイマーシブ(没入型)な体験を求める人が増えているのだろうか。
テクノロジー社会においては、コミュニケーションも映像もモニター越しにあり、デジタルのフィルターの向こうの世界と対峙している時間は長くなる一方だ。フィルターの向こう側はリアルであるはずだけど、“デジタル・フィルター”は生命的なリアリティを授受し合う機能が乏しい。確かに存在するものなのに、その息吹に直接触れることはできない。存在は認知できても総じて体感が弱いのだ。デジタル・フィルターが息吹を遮断している反動で、「もっと肉体的に感じ取りたい」という欲求があぶり出される。
だから、客席と舞台の間にある壁が溶け、劇全体の息づかいと一体化されることが心地よい。「これはバーチャルではなく、やっぱりリアルなのだ」。リアリティに没頭できることが、イマーシブ・シアターが人間を引きつけるようになった根源的な理由であると考えている。
人間がイマーシブを求める傾向は、ますます強まるだろう。身体すべてでリアリティに没頭し、自分という実存を確かめる。没頭しなければリアリティを感じられないほど、デジタル・フィルターによって分断された世界の境界線は、魔性なのだ。