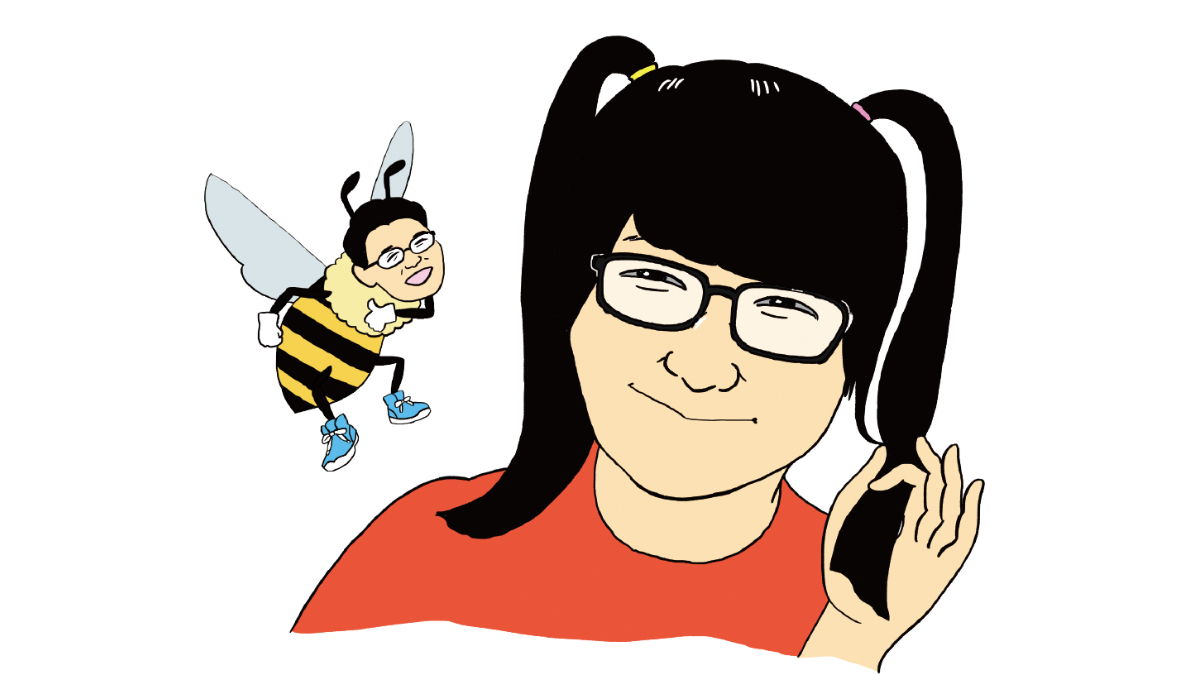大学を出て1、2年の、社会人だと胸を張って言えなかったグダグダの頃は、いつも新宿三丁目の『鳥貴族』にいた。「あれってびーとぅーびー? 」「いやあれはびーとぅーしーや」「びーとぅーびーって語感が恥ずいよな」覚えたてのビジネス用語を、180円のアテを雑につつくみたいに腐しながら、友人らと第3のビールを飲んだ。オトナの言葉を何度も口にしていれば、早くオトナになれるのではないかと期待していたのが本音だったが、社会という巨大な迷路に足を踏み入れたばかりの若者たちは、ヘラヘラとひねくれて平気なふりをするのがやっとだった。
「聞いた? LGBTって言うらしいね」4文字の英単語が海を渡って港に着いた、という話を聞くようになったのもあの頃だった。思春期にゲイであることを自覚し、みんな違ってみんないいなんて綺麗事だ、という薄淡い失望感に包まれながら成人した僕たちは、背後から迫りくる虹色の歓声をどう受け取ればいいのか分からなかった。前だけではなく、後ろからも漠然とした不安が迫ってくる。そんな時を生きていた。
「みんな違って、みんなキショいのにね~!」僕の目の前に座っていた友人のミシェウがそう言って、意識がテーブルに戻った。そうだそうだ、僕らはそもそも変わり者だった。ミシェウといると、おそらく天才とはこういうヤツなのだろう、と誰もが思わされた。気ままに音楽をつくれば、後に有名なシンガーになった友人が嫉妬するほどだったし、ショートアニメをつくればアニメーターとして身を立てた友人が驚愕するような、多才で、人とは違う感性を持っていた。
だけど彼には向上心がないというか、自分が持つ才能に対して執着がなかった。僕はあの頃、目の前の迷路に人一倍動揺していて、「いったいどこに行けばいいのだろう」とばかり考えていたけれど、ミシェウはいつも「どこにも行かなくてよくない?」と笑っていた。彼はどんなときも楽しげで、それは意識してそうしているというよりも、生きているだけで本当に楽しいのだと、心から感じているようだった。
明石家さんまが100回の輪廻を乗り越え、「生きてるだけで丸儲け」という真理に至ったとするならば、ミシェウには、初めて人間になったからそれを知っているような軽やかさがあった。彼はみつばちを待ち受け画面にするほど愛好しているから、前世はみつばちだったのだろうと真面目に思っている。毒々しくて、甘くて、優しい。それがミシェウだから。
「どこにも行かなくてよくない?」は、僕らの価値観になった。新宿二丁目にも踏み込めず新宿三丁目の『鳥貴族』で、LGBTの波にも乗る自信を持てないままに僕たちは、今自分たちがどこで何を思っているのかをそのまま発信することにした。それが『やる気あり美』というクリエイティブチームの始まりだった。
それからはいろんなことを経験した。大勢の人に自分たちのコンテンツを見てもらえたし、イベントにも何度も呼んでもらえて、こんな連載さえ始まった。どこにも行かなくていいと思った僕たちは結果的にいろんな場所に行くことになった。そしてその旅は、それぞれに自分の目的地を見つけさせ、ゆっくりと離別につながっていった。最後の砦みたいに6年間続けてきたミシェウと僕のラジオも今月で終わる。そしてこの連載も、今回で終えることにした。
僕にも行きたい所ができた。そこに向かうには山を何度も越えなくてはいけないだろうし、その道中で滑落するかもしれない。知らなかった絶景に感動することがあればいいなと思うし、別れはきっとたくさん待っていると思う。だけど最後には春の野原に辿り着いて、その気持ち良さを感じられたらいい。広がる草原は陽に照らされてツヤツヤと光り、花々は笑うように風に揺れている。僕は柔らかな空気を胸いっぱいに吸い込んで、みつばちのようにその野原を駆け回るのだ。
文・太田尚樹 イラスト・井上 涼
おおた・なおき●1988年大阪生まれのゲイ。バレーボールが死ぬほど好き。編集者・ライター。神戸大学を卒業後、リクルートに入社。その後退社し『やる気あり美』を発足。「世の中とLGBTのグッとくる接点」となるようなアート、エンタメコンテンツの企画、制作を行っている。
記事は雑誌ソトコト2024年5月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。