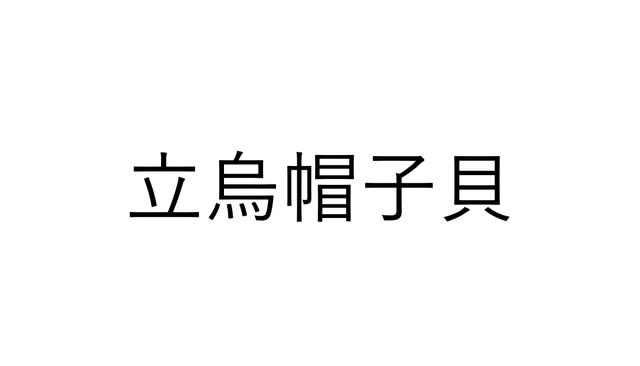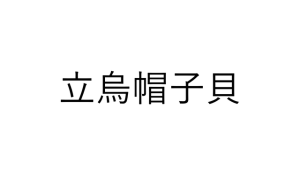目次
「立烏帽子貝」でなんと読む?
答え:タテボシガイ
答えは「タテボシガイ」でした!立烏帽子貝は琵琶湖固有亜種の2枚貝です。
立烏帽子貝の由来
なぜ立烏帽子貝と書くのかというと、平安時代に使用されていた冠の立烏帽子(たてえぼし)に似ていることから、その名が付いたのだとか(諸説あり)。
じゃ、少し休んだらタテボシ貝の煮付けを始めてもいいけど、2日くらい砂出しをやっても良いそうなので、もう少し様子を見るかも。漢字で書くと立烏帽子貝らしい。形が立烏帽子(たてえぼし)に似ているということですね。 pic.twitter.com/8jkbWlzoJV
— 再びまかないおじさんかなぴん (@kanapin00) April 9, 2020
旬は8月~5月末頃
立烏帽子貝の旬は8月~5月末頃です。琵琶湖で貝を中心に漁を行う「貝引き漁師」もおり、砂地や泥地にいる立烏帽子貝を「マンガン」と呼ばれる漁具で漁獲しています。1度のマンガンで漁獲できる貝のうち、7割ほどが立烏帽子貝なのだそう。
鮮度が命の立烏帽子貝
立烏帽子貝などの貝類は鮮度を保つために水揚げされるとすぐに湯がかれます。新鮮なむき身は人気が高く、漁師が直接注文を受けることもあるそうです。また湯がくことで淡水貝特有の臭みも軽減してくれるのだそう。殻付きのまま酒蒸しやワイン蒸しにして食すのもオススメであるほか、むき身の場合はポン酢をかけたり、天ぷらや佃煮などにしても良いのだとか。湯がく際には立烏帽子貝の貝が開き、ダシが出て汁が濁り出したタイミングで取り出すと身が硬くなりにくいそうですよ。
付け合わせは水蓮菜とタテボシ貝の酒蒸し炒め。適当に作ったオリジナルメニュー。タテボシ貝の酒蒸しをまず作り(下味はニンニクと醤油)、水蓮菜とガラ粉末と油を足してさっと炒めて水蓮菜のシャキシャキを味わう。娘に「うん、よく合ってて美味しいよ。センスあるじゃん」と上から目線で評価された。 pic.twitter.com/LHiT7YP16y
— 再びまかないおじさんかなぴん (@kanapin00) December 20, 2020
今回は「立烏帽子貝」をご紹介しました!
参考:滋賀のおいしいコレクション(https://shigaquo.jp/)