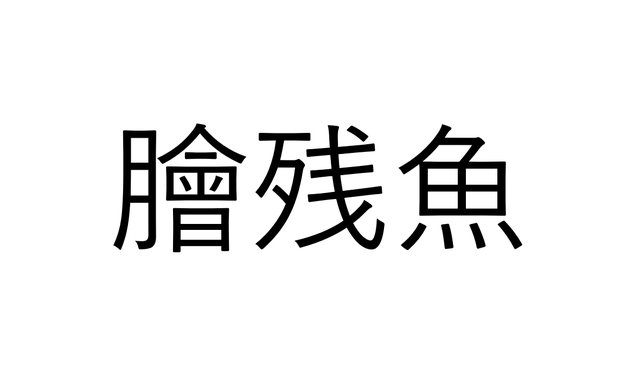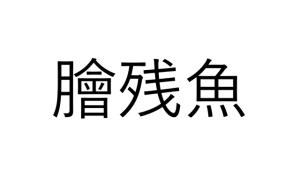目次
「膾残魚」でなんと読む?
答え:シラウオ
答えは「シラウオ」でした!膾残魚はほかにも「白魚」「銀魚」「鱠残魚」と書かれることもあります。膾残魚はシラウオ科の魚です。サイズは成長すると10cmほど。水揚げされた際に酸素に触れるとほとんどが死んでしまい白色になりますが、生きている時は無色透明の姿をしています。ちなみに、その色の変化から「シラウオ」と呼ばれるようになったのだとか(諸説あり)。俳句では春の季語として使われることも。
網走産のシラウオ!
プリプリです😆 pic.twitter.com/Ig2UHLFgGh
— 平野乃暉 ジビエラーメン研究所2号 (@Hojo2_Colonel) October 28, 2021
シラウオとシロウオの違い
シラウオによく似た魚と言えば「シロウオ」。シロウオは踊り食いが有名な魚ですが、ハゼ科の魚です。シラウオとシロウオの見分け方は様々ありますが、
・尾びれ付近にある脂びれがあるものが「シラウオ」、無いのが「シロウオ」
・上から見た時に頭の形がとがっていれば「シラウオ」、丸ければ「シロウオ」
なのだそう。
・尾びれ付近にある脂びれがあるものが「シラウオ」、無いのが「シロウオ」
・上から見た時に頭の形がとがっていれば「シラウオ」、丸ければ「シロウオ」
なのだそう。
青森県小田原湖の膾残魚
青森県小田原湖は膾残魚の産地で知られています。小田原湖は県内最大の湖で、膾残魚のほかシジミやワカサギなども漁獲されています。小田原湖の膾残魚の水揚げ量は日本一。9月~翌年3月まで行われる秋漁と、4月~6月に行われる春漁で水揚げされています。
bacchus gallery bunは本日10/29(金)もOPEN18:00-24:00通常営業です。◆今夜は青森県産(小川原湖)シラウオのお刺身が仲間入りです。 pic.twitter.com/pb4HyAzXjW
— Bungo Morita (@BungoMorita) October 29, 2021
今回は「膾残魚」をご紹介しました!
参考:青森のうまいものたち(https://www.umai-aomori.jp/)
参考:やまぐちの環境(https://eco.pref.yamaguchi.lg.jp/)
参考:夏井いつきのおウチde俳句くらぶ(https://ouchidehaiku.com/)