ワークスタイルの変化が加速度的に進んでいる昨今。今回取材した福岡市の中川一光さんは、バーやカレー店のオーナー、シェアハウス運営など、さまざまな仕事を持つパラレルワーカーだ。今から約10年前、20代で銀行員をやめ、いくつかの職種を兼任する働き方にシフトしていった中川さん。どのようにして、このライフスタイルにたどり着いたのか。彼の多彩な経験から、生き方・働き方に迷う世代にとって、選択のヒントが得られるかもしれない。(写真提供:橋口敏一さん)
元銀行員、5つの顔を持つ36歳の現在地
●シェアハウス運営
●バーオーナー
●カレー店オーナー
●旅のサブスクサービス運営会社 営業
●消防団員
これだけの仕事をこなしているというと、日々忙しく各地を飛び回っている人をイメージするかもしれない。しかし画面の向こうで笑う中川さんは、良い意味で力の抜けた軽やかな印象だ。
中川さん「特に今は緊急事態宣言中でバーは休業中(※)ですし、けっこう暇なんですよ。平日はだいたいオンラインミーティング、それ以外の時間でカレー屋のメニューの試作や打ち合わせという感じです。シェアハウスは共同経営なのでたまに顔を出すくらいで、消防団員の活動が時々。今は日曜を含め週に2〜3日は休むようにしていて、時間ができたのでバイクの中型免許を取りに行ったりしてます」
現在は自営業を中心としたフレキシブルな働き方をする中川さんだが、社会人生活のスタートは銀行員だった。
※取材は2021年9月上旬
入社式での違和感。でも人には恵まれていた
そう話す中川さんは関東の大学を卒業後、2008年4月に銀行に就職。企業の年金設計や不動産売買といった、資産コンサルティングを行う信託銀行で、まさに大学で学んだ社会経済や都市計画といった知識を活かせる分野だった。
中川さん「でも入社式の時点でなんか違和感があって…団体行動が苦手な自分を改めて認識しました。ただ後ろの席の同僚や同じ班のメンバーとはすごく気が合ったので、もう少し頑張ってみようかと」
東京での研修を経て配属されたのは、福岡支店の不動産部。仕事は順調で、同じ高校出身だった上司にも可愛がられ、さまざまな業務を身につけるため入社2年目で部署異動した。いわゆる“出世コース”である。しかし、ずっと心に押し込めていた違和感が、ついに体調不良となって現れてしまう。
中川さん「将来を期待されていることの喜びより、“レールを敷かれてしまった”という焦りが大きくて。ちょっと鬱病のような感じになってしまったんです」
休職しても周囲の期待と自分の気持ちとのギャップは埋められず、退職を決めたという。
退職したものの家がない…そうだシェアハウスしよう!
中川さん「お互い全然知らない職業もバラバラの4人で、11LDKの物件を借りました」
こうして2012年にスタートしたシェアハウス「ジャックオーランタン」は中川さんが退去した後も現在まで続いていて、他物件を含め全3棟を共同経営している。
中川さん「当時も今も、留学生などさまざまな国の人が住んでいますよ」
まさに“多様な生き方”のリアルを、はからずも目の当たりにすることになった中川さん。自身も、「しばらくお金を貯めたらワーホリにでも行こうかな」と考えていたが、また新たな転機が訪れる。
偶然の発見からDIYでバーオープン
中川さん「前職を退職してからも、ネットで不動産物件をチェックするのが習慣になってまして。ある日、六本松の居抜き物件を見つけて、バーをやろうと思ったんです」
福岡市中央区六本松といえば、かつて九州大学があった跡地に、裁判所や複合施設などが続々開業している、今や超人気のエリア。しかし2015年頃はまだ、広大な九大跡地は更地で町にも空き店舗が増加している状況だった。
中川さん「もとはスナックだった店舗を今では考えられない賃料で借りることができ、本当にラッキーでした。賃料はもちろん今でもそのままですよ。内装はほとんどDIYで、2カ月後に『Baguette(バゲット)』をオープンしました」
当時このエリアでは少なかったカフェバーという業態や中川さんの人柄もあり、オープン当初から人気は上々だった。さらに3カ月後には、同じ店舗で昼間だけ営業する、珈琲専門店「フスクコーヒー」を開業。しかしこちらは別の経営者がいる”シェアショップ”の形態で、この頃はまだ珍しかった。
中川さん「昼に使ってないのは勿体ないなと思い、バゲットのSNSで店をやりたい人を募集したんです」
学生時代も含め、都市計画や不動産経営に携わってきた、中川さんならではの視点が生かされている。
バーの常連客とアパートの一室で始めたカレー店
中川さん「バゲットの常連さんとの共同経営です。古いアパートの1室を1年くらいかけて、ちょこちょこDIYでつくっていきました」
アパートの一室という話題性はもちろん、カレー好き・スパイス好きの共同経営者がこだわって作ったメニューも人気で、売り切れになる日も珍しくなかった。一方でアパートの老朽化で解体を通告された時には、移転資金のためのクラウドファンディングを実施。目標の2倍を超える支援が集まったという。
現在は、創業時の六本松から少し離れた城南区城西に場所を移し、冒頭で紹介した新店舗としてオープン準備中だ(10月上旬予定)。
予想外の問題が起きても、その時々の状況を的確に判断しながら、乗り越えてきた中川さん。飲食店経営がまったくの素人だったとは信じられないほどだ。
中川さん「実は大学時代、演劇部で舞台監督をしていたんです。出演者やスタッフ、そして舞台全体を見ながら回す経験は、結構役立っている気がします」
大学の先輩から誘われHafH(ハフ)のスタートアップに携わる
旅のサブスクサービスを提供する「HafH(ハフ)」の業務に携わっているのも、運営する株式会社KabuK Style(カブクスタイル)の大瀬良亮社長/共同創業者が、たまたま大学時代の先輩だったからだという。
中川さん「時々飲みにいったりしていて、『起業するから手伝ってよ』と言われたんです」
業務委託スタッフとして、2018年の起業時には経理のサポートで参加。現在は事業連携責任者として、各地の宿泊施設にサービスを提案する営業を行っている。
中川さん「尊敬する先輩がやる会社なら、という感じで参画したので、他のメンバーのように『この分野がやりたい!』という情熱はあんまりないかもしれません。でもそれが逆に良かったのかも」
冷静な視点があるからこそ、目の前のやるべきことを的確に判断できる。これも、現代的な働き方のひとつかもしれない。
自分が好きな人、大事にしたい場所のために、役立つことをする。この考え方は、中川さんのもう一つの仕事のきっかけにもなっている。
気がつくと“おらが町”に。地域のためにできること
中川さん「バゲットのお客さんにスカウトされたのがきっかけです。あとは、自営業だと納税額が少ないので、『お金ではなく労働で地域に還元できないかな』と思っていたのもあります。自分の町がよくなれば、店のためにもなるかなと」
バゲットをオープンした2015年頃、まだ再開発途上にあった六本松の夜道は人通りが少なく、女性一人で入れる店も珍しかった。
中川さん「お客さんに『バゲットができて通りの雰囲気が変わった』、『イッコーさんがいるから六本松に来る』と言われて嬉しかったんです。そう言ってもらえる六本松をより良くするために、何かしたいなと。たまたま見つけた場所だったけど、いつのまにか”おらが町”になってました」
迷ったら、自分の中の「一番の理想」を目指してみる
中川さん「僕は流れに乗る方がうまくいくんですよね。自分がリラックスできている自然な状態のときに力が発揮されるタイプだと思うので」
無理をせず、その時々で自分にとって必要な生き方を選んでいく。シンプルではあるが、簡単なことではない。特に、就職や退職、転職、起業など、人生の岐路に立った時の選択は重要だ。
中川さん「悩んだら、社会的信用でもいいし単純な興味でもいいので、『今の自分が思う1番高いところ』にまずは飛び込んでみると良いかもしれません。僕も学生時代の就職活動は、大学で学んだ専門分野を活かせるというのもありましたが、『名前が知られている』という視点で選んだのが本音です。でも、自分が知り得るトップの環境に身を置くことで一流の人と出会えるし、一流の仕事を学べる。僕は退職しましたが、銀行時代に上司に学んだことや経験は確実に活きています」
結果的に退職を選んだことも、最初に妥協しなかったからこそ、自分の選択に正直に向き合うことができたという。
中川さん「組織の中でみんながやっていることに違和感を感じる自分は、社会不適合者だなと思い詰めた時期もありました。今でもそのギャップが克服できたとは思えないけど、少なくとも悩むことはなくなったし、無理せず暮らせています」
文:西 紀子
■ライタープロフィール
西紀子:福岡市出身。大学卒業後、フリーペーパー編集部や企画制作プロダクションにて編集・ライティング業務に従事。2017年よりフリーランス。2018年より岡山市在住。 2020年よりソトコトオンライン・ローカルライターとして記事執筆。現在に至る。




















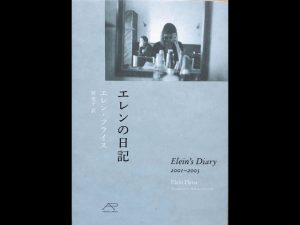












1985年、山口県宇部市生まれ。2004年に宇部高校を卒業後、筑波大学社会工学類に入学し、社会経済システムを専門に学ぶ。2008年、住友信託銀行(現・三井住友信託銀行)に入社。2011年に退職、2012年よりシェアハウスを経営。2015年、福岡市中央区六本松でバー「Baguette(バゲット)」、2018年に同エリアで「カレーアパート トキワ荘」をオープン。また、地域の消防団員としても活動中。 2019年より株式会社KabuK Style(カブクスタイル)が運営する定額制宿泊サービス「HafH(ハフ)」の営業を担当。現在に至る。(写真は本リモート取材中の様子、本人撮影)