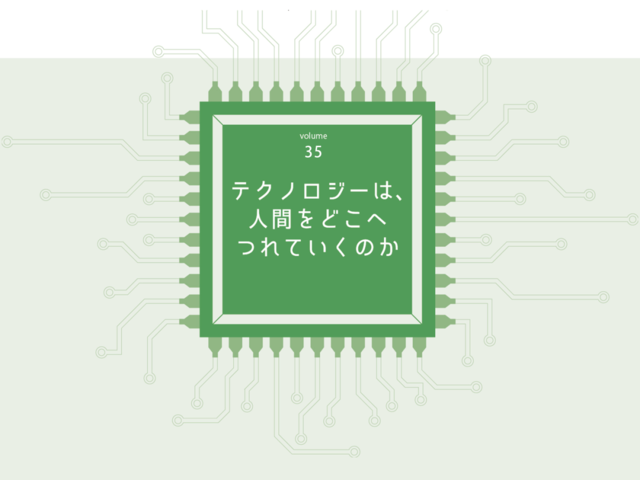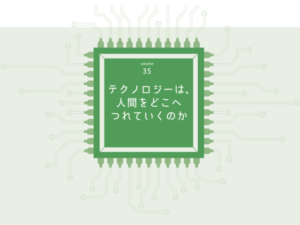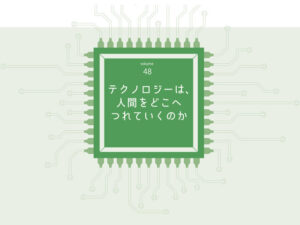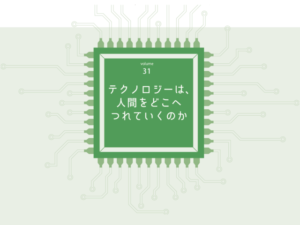お互いに恋をして、愛を感じるようになること。高揚した気分、恋い慕う感情。「恋愛」の定義は辞書上ですらまちまち、国や歴史によっても変わる。
恋愛の始まりの定説によると、12世紀のフランスへとさかのぼる。既婚で自分よりも身分が高い貴夫人に騎士が叶わぬ想いを抱き、トルバドゥール(吟遊詩人)が彼女を褒め称える詩として吟ずる。神の前に跪くかのごとく、貴夫人に跪いて崇高さを褒め称えるのは、キリスト教の神を崇拝する形式が流用されたともいわれる。叶わぬ想いというものが人間の心を打ち、恋愛が歌い継がれて文化となる。17〜18世紀頃、理想の女性を崇拝することに「愛の証しとしての苦しみ」が加わり、逆境のない恋愛は本物の恋愛ではないとする価値観が生まれる。19世紀になると、一対一の男女の間で結ばれる純愛を指す概念「ロマンチック・ラブ」が広まり、近代における恋愛の理想として扱われる。小説を読む層が増えるとともに、物語として描かれた恋愛に自分を重ね、小説と同じような恋愛をすることを女性が夢見るようになる。恋愛は西欧に生まれて育ち、日本に入ってきたのは明治時代以降。それまでの日本には恋愛という概念自体がなく、“恋愛文化遅咲き”の国である。
文化、宗教、哲学、時代背景によって、定義が固定化しない恋愛。人間を翻弄する正体不明な恋愛であるが、恋愛をすると眼球を覆う骨の上にある前頭眼窩野という脳の部位が活性化するなど、恋愛と脳の関係を示す研究成果が多数存在する。
脳科学者の中野信子さんは、恋愛と脳の関係についてこう語る。「脳は人間の体の中でも、大量のエネルギーを要する“浪費家”なんです。重量では2から3パーセントの小さい部位なのに、カロリーや酸素の4分の1から5分の1も使ってしまうのですから。それほど重要な部位でありながら、計算能力を麻痺させるような恋愛。脳にとっては無駄なことかもしれません。でも、脳内でドーパミンが分泌されるから楽しく感じるし、分かり合える喜びもある。女性は出産の苦しみを一瞬忘れたり、お互いのためだったらどうなってもよいと、理性の働きを一時的に麻痺させる脳内物質が、たくさん分泌されます」。ドーパミンが大量分泌して快楽を感じると、脳の扁桃体・頭頂側頭結合部の動きが鈍化し、正確な判断ができなくなるともいわれる。恋愛時に分泌される脳内物質には中毒性があり、恋煩いにかかる。これも脳の仕業なのだ。
一緒にいる時間が長くなると、神秘性が乏しくなることで脳から恋愛物質が分泌されなくなり、どれほど魅力的な相手でもドキドキし続けることが難しくなる。情緒的な物語であるはずの恋愛も、脳がつくり出す科学的な出来事だと表現してしまうと、「興醒めさせないで」と怒られそうだ。
恋愛の概念は、歴史が示すとおり同じ場所にとどまらない。恋愛を司る脳は、テクノロジーや生活のあり方でさらなる変化を遂げる。恋愛をしている時の脳内神経細胞の変化を人工的につくり、デジタルで理想的な恋愛相手を生み出せてしまう。人工知能やVR上の“更新し続ける”登場人物にドーパミンが分泌されて恋愛対象となるならば、「人間のように飽きさせずに、いつまでもミステリアスでいてくれるんだ」と没入する人も現れるだろう。恋愛を娯楽として扱う傾向が強まり、「尊い恋愛を遊び扱いにしないで」という声が沸き立つかもしれないが、中野さんが言うとおり、「恋愛は貴族の遊びだった」わけだし、トルバドゥールが吟ずる詩を楽しむことと本質的な差はない。
遊びだから悪いと、頭ごなしに決めつけなくてもよいのではないだろうか。遊びも人間の脳にとっての活性剤なのだから。人間はなぜ恋愛するのかを突き詰めていくと、結局脳と向き合うことになる。人工知能が計算を担うことで、脳のエネルギーを節約できる。恋愛を楽しむ余地が脳に与えられ、脳の無駄遣いを咎められずにすむ。人工知能を「恋愛の神様」にし、恋愛を楽しむための味方にすればいい。