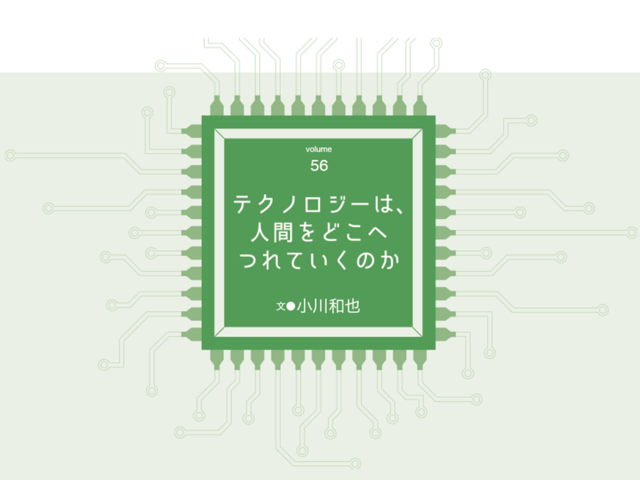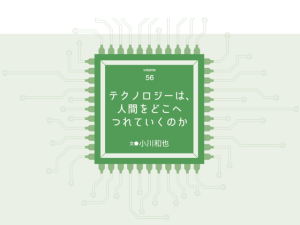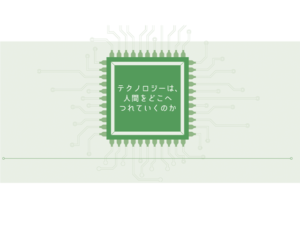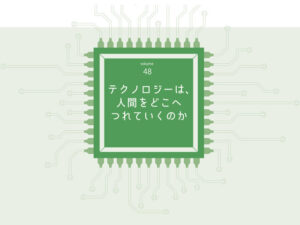先端テクノロジーが加速度的に新しい世界を生み出す。どのような世界を生み出すことが望ましいのか。その問い、哲学こそが、100年後の未来の命運を握る。
東京大学大学院総合文化研究科(科学史・科学哲学研究室)准教授で、科学哲学の研究者・鈴木貴之氏は、著書『100年後の世界—SF映画から考えるテクノロジーと社会の未来』(化学同人)を通して、生命、人間の能力、情報、人間の心の観点から我々に未来を問う。
例えば、人間が身体や脳の機械化を進めることはどこまで認めてよいのだろうか。
「テクノロジーで身体や脳を強化することで生じる個人差、不平等など、直近で直面する課題があり、制約も生じるけれど、“してはいけない”と言うことは難しい。これをどのような枠組みで論じるべきか自体が定まっていない。善いか悪いかの2極論では単純すぎる」と鈴木氏は語る。パラリンピックの陸上競技などでは、技術力を駆使した競技用義足を用いて好記録を出すアスリートはすでに存在し、オリンピック記録を上回ることも当たり前になるかもしれない。可能性に満ちているとワクワクする人もいるし、不公平だと捉える人もいる。白黒を明確に区分できる話でもないし、何らかの答えを与える根拠、方法もまちまちだとすれば、解を探す道を迷いながら歩むしかない。
また、人間のように広域な適応範囲と汎化能力を持つ汎用人工知能が実現したとすればどうだろう。現状の人間の仕事の多くを「人間らしい能力を兼ね備えた人工な彼ら」が担う可能性がある。それに対して、メリットよりも恐怖心や懐疑心を抱く人は少なくない。まだ漠としていて実体なき仮説ゆえ、能力的に人間が凌駕され、存在意義を失うのでは? という不安がつきまとうのも無理はない。
それならばいっそのこと、優秀な人工知能などは開発しないほうが、人間のためなのか。
「開発できたとしても、する必要のないテクノロジーもある。利便性と比例するテクノロジーばかりではない。汎用人工知能は想像以上に複雑で、自律型ロボットと一対で意味をなすこともあり、実現までにはかなり時間がかかる」。鈴木氏が考察するように、実現までにはまだ相当の時間を要するだろう。幸いなことに、どうすべきかを考え、道筋をつくる時間はたっぷりと残されている。汎用人工知能が一般化した時代に人間にしかできないことがあるとすれば何なのか。そもそも実現する必要があるのか。あるとすればなぜなのか。
100年後の未来にふさわしいテクノロジーとの共存共栄に対する答え合わせは、そう簡単ではない。絶対的な正解はなくとも、できる限りの共通の了解を探し求める。人間とテクノロジーの“関係哲学”を続けながら時を刻む以外に、人間がよりよく生きられる100年後は望めない。
紀元前から、人間は本質を洞察し、考え方自体を見出す営みとしての哲学を重ねてきた。石器、農耕技術、水車、羅針盤、活版印刷が先端テクノロジーとして君臨した時代があり、それらと向き合うための哲学があった。
しかし、身体や脳の機械化を進めることや人工的な知能を生み出すことは、生命とテクノロジーが歴史上最もクロスオーバーし、特異的な出来事となる。これから100年を共にするテクノロジーは、哲学についての哲学的な問い、メタ哲学の重要性も含めて、哲学のアプローチにも新しさを求めるかもしれない。