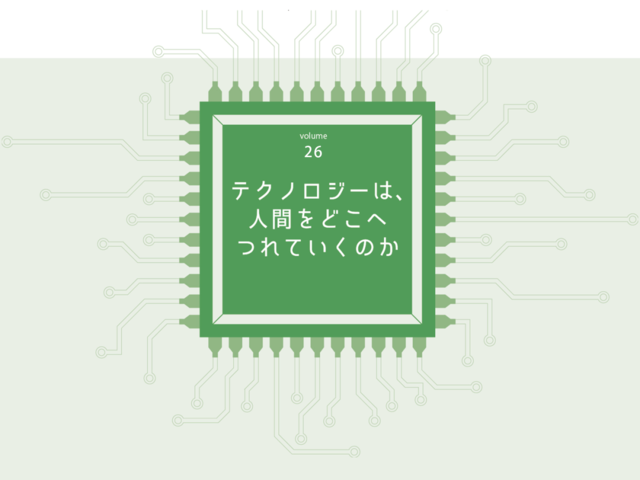イチゴ、レモン、メロン、ブルーハワイ。好みのかき氷のシロップを選ぶ。「やっぱりかき氷に合うのはイチゴだね」「いやいや、すっきりレモンが最高」と、好みの主張合戦が繰り広げられる。ところが、それらは全部同じ味のシロップ。違うのは、色だけ。
五感のひとつである味覚には、甘み、酸味、塩味、苦み、旨みの5つの基本味が存在する。生理学的な基本味を受容するのは舌。実際に行われたシロップの実験は、味覚には錯覚という調味料があることを浮き彫りにする。舌が、色にだまされたのだ。
「右が150グラムで3000円、左が同じグラムで5倍の価格の1万5000円のステーキです。食べ比べてみてください」と促され、味比べする。口に入れる前から5倍の価格差が調味料になっている。高いと認識したステーキを条件反射のようにおいしく感じてしまうならば、味覚の高機能センサーである舌が錯覚スパイスを食らいかねない。本当の価格が逆であっても、高いと触れ込まれたステーキをまんまと支持する。
視覚、聴覚、嗅覚、触覚、記憶などにより拡張された知覚心理学的な感覚は、味に影響を与える。だまされたというより、味覚とはそういうものなのだ。
「高級レストランで食べるハンバーグよりも、母親の手作りのほうがおいしい」と感じる調味料は、母親が自分のために一生懸命作ってくれたという“思い”である。いわゆる「おふくろの味」への肯定は、記憶や思いを土台に成立していることが多い。手料理に不慣れでありながら、徹夜して作ったチョコレートをメッセージ付きでバレンタインデーに贈られ、出来栄えはいまいちでもおいしく感じたことはないだろうか。やさしい気持ちを感じ取ることが味覚に影響するという実験結果があるとおり、「やさしさ調味料」が作用しておいしいチョコレートに変身したのだろう。相手のやさしさがチョコレートに溶け込んだかのように。
だとすれば、テクノロジーで知覚や心理をコントロールし、恣意的に味覚を変えることが可能になる。「テクノロジー調味料」とでも呼ぼう。VR技術を用いた映像でほくほくの湯気を出し、音響でじゅうじゅうと音を立て、ディフューザーによる香りも加えてシズル感を煽る。
おいしく感じるようにテクノロジーで錯覚を起こさせれば、冷凍食品を解凍するだけの料理でも何割増かになる。人工知能を搭載したロボットシェフに、食べたいものや調理方法、はたまた希望するカロリーを入力すると、手際よく完璧な味で仕上げてくれる。有名シェフのデータを保持した人工知能が家庭でプロの味を体現するとなれば、人間はお手上げ状態だ。しかし、想定しておくべき未来像である。
料理と錯覚を招く調味料の両方をテクノロジーが支配するとなれば、人間のように巧拙の差も失敗もない。好きな時に好きなものを簡単に食べられる。「もう最高!」と思えなくもないが、それは極端に合理性を重んじた場合である。「ロボットシェフ+テクノロジー調味料」の時代においては、むしろ「やさしさ調味料」こそが最強になるのではないか。知覚や心理こそが究極の隠し味だとして、おふくろでも恋人でも、その料理人は人間であってほしい。たとえロボットと恋愛ができる社会になったとしても、料理に乗せられるやさしい気持ちは人間から発するものが一番。僕はそう信じている。