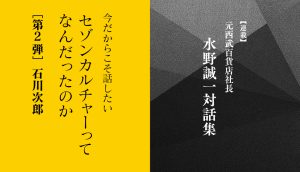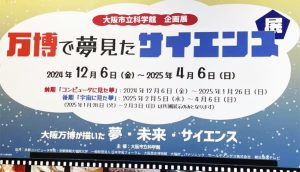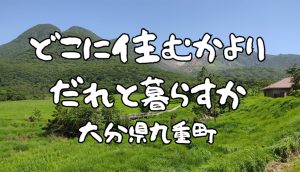1. 私がくまモンの上司です
ゆるキャラだったくまモンを営業部長に任命したことをはじめ、著者が県知事として県庁で行った数々の改革が紹介されています。地方自治の現場を知るだけでなく、それを変革していく戦略がみごとだと感じました。
書籍情報
著者:蒲島郁夫
出版社:祥伝社
著者:蒲島郁夫
出版社:祥伝社
2.スマートコミュニティ ─都市の再生から日本の再生へ
20年ほど前に書かれた本ですが、今でも色褪せず、新鮮に感じられます。日本やアメリカでの多様性のあるコミュニティづくり、都市づくりについて実践的に触れていて、“出る杭”の素晴らしさに感銘を受けました。
書籍情報
著者:細野助博
出版社:中央大学出版部
著者:細野助博
出版社:中央大学出版部
記事は雑誌ソトコト2022年3月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。