どこもかしこも、赤々と、命を熱し尽くすように紅葉し続ける山の樹々たちが、いよいよ、内に蓄えていた最後の水分を外に追いやって、からっからに、はらはらと葉を落とした。冬に向けて透明になってゆく空に、枝だけになった手を静かに掲げて、ぽつりと立っている。だけど、寂しくはなく、とても凛として、ほとけさまのような姿で立っている。
シヅさんが、寝床から起きられなくなって、ふた月、み月と過ぎて、夏には、あれだけ元気にテレビの取材を受けたり、日向にちょこんと座って塗り絵を楽しんでいたシヅさんが、すっかり躰を横にしたまま、意識が遠くのほうにいったり、また鮮明にはっきりしたりを繰り返しているようだった。
目の前にあるシヅさんの姿が、なかなか信じられなくて、どうしたらいいのかわからなかった。一緒にお見舞いにきたハマちゃんも同じ気持ちのようだった。幼い時分から「なあ、おばちゃん、あんなあ、おばちゃん」と慕ってきたハマちゃんが、精いっぱい大きな声で呼びかけると、ふうっとシヅさんに意識が戻って、懸命に何かを伝えた。ハマちゃんが手をとって「おばちゃん、ごめんな。もっといっぱい躰をさすってあげたらよかったな。えらいなあ、えらかったなあ」と、これまでずっと何度も何度も若い時からさすってきたように優しくやさしく背中をさすった。
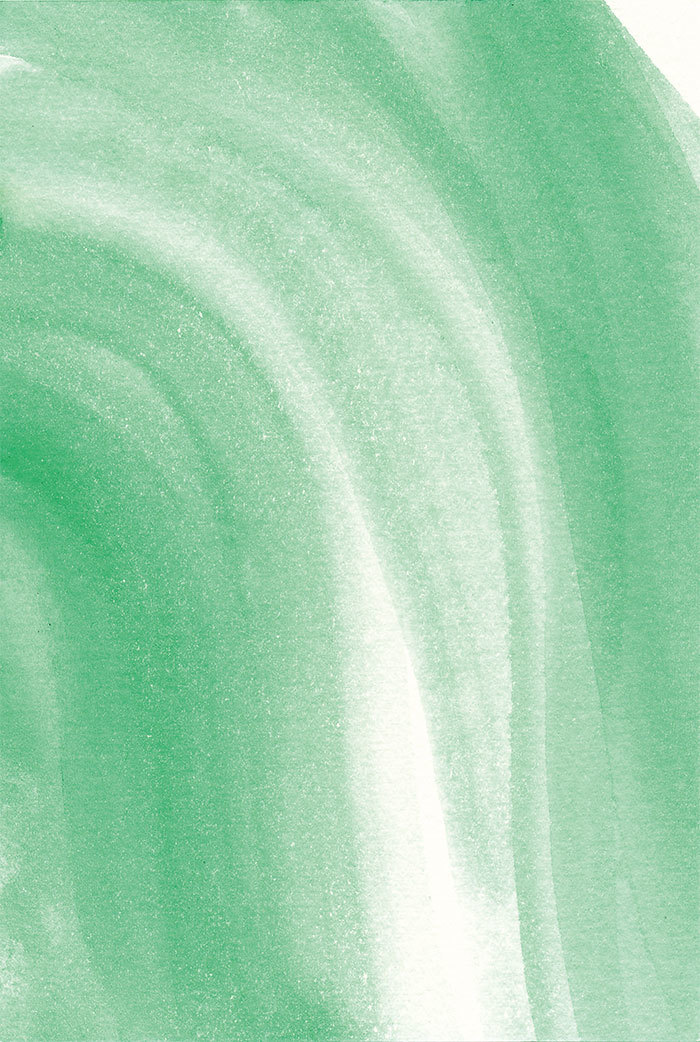
シヅさんは20代のはじめから女手ひとつで家を守り続けた。ひとり、家でこつこつと、畑をしたり編み物をしたり。遊びに行くと、電気もつけずに真っ暗な部屋で何か用事をしていた。暗がりのなか、ほんの隙間から差し込む陽の光が、ずっと昔からそこにある光のようで、シヅさんの佇まいそのものだった。「しーづさーん」とガラッと襖を開けると、可愛らしく少し震える声で「よう、来とうくれました。なんや、ごそごそ遊んどりました」と、優しい血色のよい笑顔でていねいに迎えてくれた。いつもたくさんの話があった。
「戦争が終わって、1間、2間と数えよったのがメートルになって、1分や1貫がグラムやなんかに変わりよって。世界がいっぺんに変わりました」という話はなぜか印象深く残っている。「本道は昔は違っとったんです。傘をさして誰かとすれ違いよったら、当たりよったんです」と、いまは車が楽にすれ違えるアスファルトの道が、ほんとうに狭かったんだなと、僕たちが知りようのなかった景色をたくさん分けてもらえた。
外に出ると、下の畑までそろりそろりとたっぷり時間をかけて歩く。土と一緒になるくらい屈み込んで、日がな一日、草取りや土寄せ。ふうっと谷間から見上げると、高い空があって。どこまでも樹々、どこまでも山々。おおきな風が吹き上げて、今日もあの場所で日向ぼっこ。またたく星空、まっかな日の出に手を合わせて。いつもいつもお陽さまと一緒にあったシヅさん。
最期のひと月。一日、また一日と、少しずつ水を天に返されてるようだった。躰から、水がなくなっていって、どのように言葉にできるのだろう、してよいものだろう、僕はあのように静かに美しく最期を迎えられるだろうか。この山の樹々と同じように、透明になっていく空に、水をお返ししているみたいだった。100年分の山の精。
シヅさんをお見送りをした後、しとしとと、やわらかな雨が降ったりやんだりして、今日は雨かな、曇りかな、あっ、晴れ間が差したと思ったら、輝く水の粒たちが辺り一面に、てらてらてら。「シヅさんの雨やな」と妻と空を仰いだ。
次の朝、ようやく完成した、僕たちのはじめての本『こといづ』が家に届いた。おそるおそる包みから取り出すと、優しい手触りの、なんとも、あたらしい命のような本が手の中にあった。ゆっくり開いてみると、目次があって、それから「はじめに」の文章があった。自分で書いた文なのに、涙があふれた。よい文章だというのではなくて、ほんとうにただ耳聞きしたことを書かせてもらっただけやから、ハマちゃんや耕作さんや、シヅさんも、うん、いっぱいおるなあ。
たっぷり時間をかけて降ったりやんだりする雨のなか、村のみんなに本を届けにまわった。みんなみんな、どこに降る雨も優しかった。とても凛として、村の人たちが笑って、笑う山がある。見上げると、見たこともないくらいおおきな虹が何重にもかかっていた。葉を落とした枝には、たくさんの蕾がついていた。









































