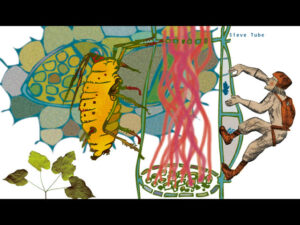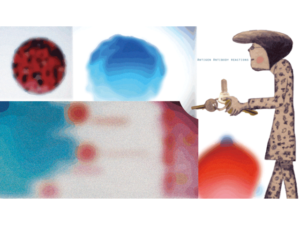毎年10月の第1週は、ノーベル賞のシーズン。私は、解説要員として新聞社で待機していた。まじめに大学で研究に邁進していれば、あるいはもらう側になれたかもしれないが、生半可なモノ書きになってしまったせいで、もっぱら解説する側に回っている……というのは冗談として、昨年の大隅良典氏、一昨年の大村智氏、梶田隆章氏、その前年の赤崎勇氏、天野浩氏、中村修二氏など、このところ日本人が相次いで受賞しており(中村修二氏は受賞時、米国籍)、まるでオリンピックのメダル獲得ニュースに似た様相を呈している。
日本人がノーベル賞に輝くことはもちろん喜ばしいことだが、注意しなければならない点は、日本人のノーベル賞受賞ラッシュが、そのまま現在の日本の科学水準の隆盛および科学行政の成功を示しているわけではない、ということだ。科学的な発見は、そのほとんどの場合、発見が行われた瞬間および直後は、それが大発見なのかどうかわからないことが多い。その発見が次の発見につながり、それが連鎖して新しい分野が切り開かれ、応用面でも成果が表れるためには時間がかかる。
また、発見の評価が定まるためにも一定のインキュベーション期間が必要となる。ノーベル賞の選考委員会はそれをじっと待つ。だから今のノーベル賞受賞者が、対象となる発見を成し遂げたのは、かなり以前のこと、場合によっては何十年も前のことであることが多い。つまり、このところの日本人ノーベル賞ラッシュは、いまから30年ほど前の発見が伏流水となって大きな水脈をつくり、その成果がようやく目に見えるかたちで湧水となったもの、といえるのだ。
さて、今年のノーベル生理学・医学賞は、生物時計の研究に対して、ジェフリー・ホール、マイケル・ロスバッシュ、マイケル・ヤングの3氏に授与された。このうち、マイケル・ヤング氏は、ロックフェラー大学所属であり、彼の研究チームがこの成果を発表しはじめた1980年代、ちょうど私も、かけだしのポスドク(博士研究員)として同じロックフェラー大学で研究修業を行っていたときだったので、感激もひとしおである。マイケル・ヤング氏は、一見、フォーク歌手のような風貌で、キャンパスをラフなジーンズ姿で歩いている光景を何度も見かけたことがある。
ヤング氏たちの研究がすばらしいのは、生物時計のような複雑な生命現象を、遺伝子から説明する道筋をつけた、という点にある。私たち生物は、昼間活動し、夜、眠りにつく。その逆の生活をする夜行性の動物もいる。一日のうち、何度かお腹が空き、食事をする。一定の間隔で、排便や排尿をする。身体の中の代謝も一日のサイクルで活性が上下する。このようなパターンをサーカディアン・リズム(概日リズム)と呼び、24時間で1回自転するこの地球上で生活するようになって以来、生命が進化の過程で身につけた特性である。
そして、このリズムを生み出すような体内時計が細胞のどこかに備わっているに違いない、と考えられるようになった。問題は、その分子レベルの仕組みにいったいどうやってアプローチすればよいか、ということだった。これは大変な難題である。複雑な問題を解くには、シンプルなモデルが必要である。ヤング氏たちが採用したのは、なんとハエだった。ハエといっても、私たちがうるさく思うような五月蝿ではなく、ショウジョウバエという小さなハエである。英語名では、フルーツフライ。自然界では花の蜜や果物の汁を吸って生きている。簡単に飼育でき、ライフサイクルも短い。約10日で成虫となる。大量に扱うことができ、短時間で世代交代する生物は実験に都合がよい。世代が長い実験動物だと、へたをすれば研究者のほうが先に死んでしまう。
ヤング氏たちは、大量のショウジョウバエの中から、体内時計が狂っている個体を選び出してきた。ハエにもちゃんとサーカディアン・リズムがあり、日中は元気に活動するが、夜間になると休む。しかし、ハエの中にこのリズムがずれている個体が見つかったのだ。しかもこのずれは単なるハエの気まぐれや個性ではなく、遺伝することがわかった。リズムがずれるハエの子孫は同じようにリズムがずれている。つまり、遺伝子のどこかに正常なハエとは異なるミスがあり、これが原因で体内時計に狂いを生じているのだ。
ショウジョウバエは、小なりとはいえ、多細胞生物であり、遺伝子の数はおよそ1万4000(ヒトは2万3000)、ゲノムサイズもかなり大きい(1億6500万文字。ヒトは30億文字)。この中から、正常なハエと、体内時計が狂ったハエのわずかな差を見つけてこなければならない。ミスがいったいどこにあるのか、壮大な探査が始められた。