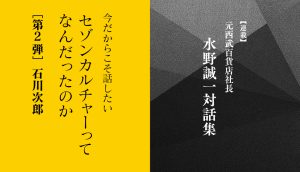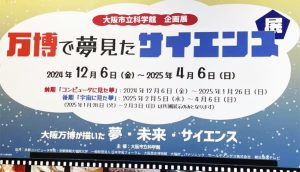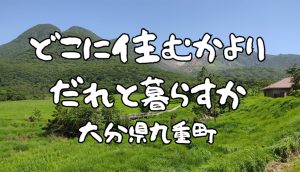CMや映画で、大森歩監督によってそっと示されるひとつの現実。それはあなたにとって、意外なものでしょうか、それとも当たり前のものでしょうか。
大学卒業後、CMの世界へ。
例えば、出版社『宣伝会議』発行の雑誌『ブレーン』主催のコンテスト『Brain Online Video Award 2014』で一般部門審査員特別賞/協賛企業賞を受賞した、参天製薬の目薬のCM『瞳の恋』。このCMでは、駅前の花屋で働く男性に恋をした女性が、今日こそは声をかけようと決意する朝を描いている。何を着て出かけようかと心躍らせながらも、きっと自分なんて相手にされないと悩む乙女心の独白が続く。そして、最終的に映し出される声の主は、白髪のおばあさんという展開だ。
ため込んでいた鬱屈を、映画に。
大森さんは「CMの仕事って社会とともに生きている感覚があるんです。こういう時代だからこういう企画にしよう。こんなセリフが合うんじゃないかなと考えながらつくるから。好きなんですよ、自分が商品や誰かに少しでも貢献してる気持ちになれるところが。でも、どこかで自分が消費されてる感じもしたんです。夢を持ってこの世界に入ったけど、朝から晩までただただ働いて。プライベートも全然うまくいかなくて。そんな時に、浪人時代と大学生時代の3年間、一緒に暮らしたじいちゃんが亡くなったんです。老人ホームのスタッフの方から、もうまったく食事を摂らなくなったと聞かされて、叔母と一緒に駆けつけました。ずっとじいちゃんのそばについて、手を握っていたんですけど、じいちゃんが目を閉じた瞬間に感触がふっと変わって、魂が抜けていったのがわかったんです。その時初めて、人が死ぬということを直接感じたんです。ああ、自分もいつか死ぬんだよな……。だったら今、やりたいことをやってみようと思ったんです」と話した。
映画は短くても数十分単位だが、Webで流れるCMでも長くて2分程度、テレビで流れるものであれば、たいていが15秒や30秒という世界だ。尺ひとつをとっても、違いがある。CMは、時代の空気を読みながら、効果的なメッセージを乗せて、クライアントの商品・サービスをどう伝えるのかを求められ、映画は、監督の内なるメッセージをどう表現するのかを、監督自らが追求する。CMも映画も映像を撮るという点では同じだが、まったく別のものだとわかる。
大森さんの場合は「人生このままでいいのか」「血迷ってる」「仕事ばっかりにならなくてもいいんじゃないか」「自分が主体になっていない」、そんな、ずっとため込んできた気持ちが、映画の製作へ邁進させたのだそうだ。
準備途中に脚本を見てもらったプロデューサーの、「オチがないけど、大丈夫?」という意見に揺らがなかったのも、このため込んだ強い気持ちがあったからだろう。「実際に『春』は、分かりやすく誰かが何かに打ち勝つ話ではないし、起承転結がはっきりしないと思う人は多いかもしれない。でも、短編映画だし、観た人の心に“引っかき傷”を残すことのほうが大事なんじゃないかって。だからこれでいいと思ったんです」。
祖父の認知症は、ひとつの変化。
例えば、映画に登場する祖父は、居合わせた相手に、「スーパーのレジ待ちの列に割り込んだ」と言って突然怒り出したり、「知らない人にずっと見られている気がする」と言い張ったりする。互いに怒鳴り合い、カッとなった孫娘が祖父を突き飛ばすシーンも出てくる。認知症が進行していくからといって、悲しいばかりではない。そこに映し出されていたのは、うれしいことも腹の立つこともいろいろある、ありふれた日常風景だ。
それはきっと、大森さんが実体験として、病気で衰えていくことは悲しいことではなく、生きていれば起こり得る変化のひとつだととらえているから。
「長生きが素晴らしい、健康が一番だって、最近よく聞きますけど、本当にそうなのかなって思うんです。私のばあちゃん、つまりじいちゃんの奥さんは、病気で早くに亡くなったんです。私が小学6年生の頃。ばあちゃんの日記には、死にたくない死にたくないとびっしりと書かれていて。それを見てしまって以来、死ぬのが怖くなったんです。高校3年生くらいまで、夜になる度に死ぬことについて考えたりしていました。でも、じいちゃんと一緒に3年間暮らした中で、早く死んだばあちゃんよりも、ひとり残されて、20年近く暮らしてきたじいちゃんのほうが寂しいのかもしれない。病気があるとかないとか、命の時間が長い短いにかかわらず、生きているうちに、主体的に何かや誰かと向き合えたかどうかのほうが、大事なのかもしれないと思ったんです」
そしてこう続けた。「じいちゃんはすごい頑固だったけど、認知症でまろやかな性格になったから、実は若い頃は優しかったのかなって。病気になった今がちょうどいいくらいと笑ったりしましたね」。
確かに存在する、現実。
大森さんから示されるのは、ささやかな日常の連続。誰も取り上げなかったかもしれない、言葉にしなかったのかもしれない、でも確かに存在している現実だ。大森さんは「あなたの視点だけで物事を見ていませんか? ほかの視点もありますよ」と、作品を通じて意見するわけではないが、「普通はこうだよね」という、経験則から来る一人ひとりの思い込みを軽やかに飛び越え、こうささやいてくるようだ。「これもまたひとつの現実。あなたはどう感じますか?」。